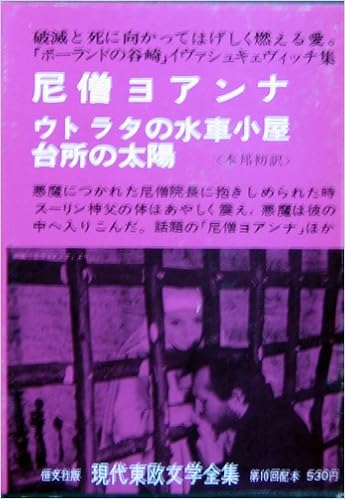18年2月の書籍雑誌の推定販売金額は1251億円で、前年比10.5%減。
書籍は773億円で、同6.6%減。
雑誌は478億円で、同16.3%減。
書籍マイナスは前年同月の村上春樹『騎士団長殺し』100万部発行の影響とされる。
雑誌の内訳は月刊誌が390億円で、同17.1%減、週刊誌は87億円で、同12.4%減。
返品率は書籍が32.2%、雑誌が44.2%と、いずれも高くなっている。
前回のクロニクルで1月の前年同月比マイナスが34億円だったので、今後その反動が生じるはずだと記したが、2月は前年同月比147億円マイナスで、すでに18年は2ヵ月で181億円の推定販売金額を失ってしまった。
それを回復できるような出版状況ではまったくない。
出版状況と出版流通システムは完全に臨界点に達しているというしかない。
1.大阪屋栗田が3月6日付で「当社に関する虚偽情報の発信に関して」という「ニュースリリース」を出している。
ここには大阪屋栗田の現在の実像がよく現われている。それは取引先の出版社や書店ではなく、株主にしか目が向いていない取次としての姿である。かつて街の中小書店と併走し、それなりの自負や矜持も備えた大阪屋や栗田の面影はない。それは取次が置かれている現在の状況を象徴していよう。
出版業界は何よりも言論の自由を前提として成立しているし、その流通を担う取次がそれを知らぬはずもあるまい。まして社長は講談社出身ではないか。それにまったくの「虚偽情報」であれば、まずダイレクトに本クロニクルに抗議し、反証を示し、論議を交わし、謝罪を要求すべきではないか。言論に関しては言論でというのが言論の根幹であることは自明のことだ。もちろん本クロニクルにしても、納得できる反証が示され、論議を尽くすプロセスを経ていれば、訂正謝罪もしたであろう。
しかし「一部のブログ」とされているだけで、本クロニクルにはまったく抗議も接触もなく、ここに示されているように、法的「恫喝」を加え、株主の大手会社と出版社名を並べ、出版業界における個人の言論を圧殺することに終始している。
実際に「本クロニクル118付記2」のような事態が生じ、削除を強いられることになるのだが、これも法的規制から具体的に書くことができない。だがネット事情に通じた読者であれば、すぐに事情はおわかりだろう。
本クロニクルがあえてこの情報を発信したのは、これが大手出版社に対する支払い条件改定とも考えられたが、この問題を通じて、現在の取次と大手出版社をめぐる金融問題が浮かび上がると想定したからだ。つまりそれは現在の正味と再販委託制に基づく出版流通システムがゾンビ化していることの証明になるはずだった。ところがそれは論議ともならず、とりあえずこのような経過をたどったことになる。
これは断わるまでもないかもしれないが、本クロニクルは出版業界のリアルタイムでの状況分析を目的とし、出版業界内の個人の無償の行為として発信されている。それゆえに誰でもフリーアクセスできるし、誰も公言しないけれど、出版業界では多くの人たちが読んでいて、業界の様々なシーンにおいて参照されている。
その一方で、私は『週刊エコノミスト』(3/27)が付している「出版評論家」を名乗ったこともないし、何の報酬も得ていない。しかし本クロニクルは10年間に及んだことで、紛れもない唯一の現代出版史を形成している。
それにもうひとつ付け加えておけば、本クロニクルを始めた目的は、出版業界に何が起きているのかを定点観測して記録することにある。それは戦前の大東亜戦争下から敗戦と占領に至る10年間の出版史の詳細が記録に残されていないことに起因している。現在に至る10年間こそは第二の敗戦と占領だったと考えれば、後世において、本クロニクルは出版業界のみならず、歴史を検証する不可欠の資料となるであろう。
かつて私は『ブックオフと出版業界』を上梓している。そこで街の中小書店を壊滅させたひとつの要因である、ブックオフ、CCC、日販、丸善の癒着と関係を明らかにしたが、著者にも発行出版社にも法的「恫喝」は加えられなかったことを記しておこう。もちろんブックオフが取材を拒否し、取次配本に問題が生じ、書店の一括返品などの話は伝えられてきたにしても。
そうした意味においても、出版業界は解体の危機ばかりではなく、言論の自由の危機すらも露呈し始めているといえよう。


【付記】
「日経新聞電子版」3月31日午後の発信によれば、楽天が大阪屋栗田に20億円を追加出資し、出資比率を5割超とする。大阪屋栗田の社名も「楽天」を含む商号に変更。
2.日販の平林彰社長が「出版社へ条件変更を求める」という見出しで、『文化通信』(3/19)のインタビューに応じている。それらをつぶさに要約してみる。
* 雑誌に関しては定価の0.55%だった出版社の「運賃協力金」を0.85%に上げてほしい。
輸送環境はこの数年急激に悪化しているし、20年以上「運賃協力金」も改定されていないからだ。対象出版社は現在100社だが、「運賃協力金」制度の改定なので、雑誌を発行するすべての出版社にお願いするつもりだ。
* 取次にとって書籍はずっと赤字で、雑誌で稼いだ利益で書籍への投資と赤字を補填してきたのが、取次の構造である。しかし雑誌の売上が減少する中で、遠くない将来、取次業が続けられないという危機感がある。だから書籍で利益を出し、書籍だけで食べられる構造にしなければならない。
* 書籍に関しては日販が営業赤字を算出し、対象出版社個別に赤字額を示し、話し合いをしたい。対象出版社は赤字金額が大きい100社で、最終的に200社になる。
* 書籍の赤字原因のひとつは文庫、新書、コミックの定価が低く、物流コスト負担が重いし、文庫は返品率が下がらない。
二つ目は出版社の日販への出荷正味が高いケースである。書店へのマージンやリベートを上げていかなければならないし、書店マージンを30%にする必要がある。取次仕入れ正味が70%を越えている出版社は改善してほしい。
三つ目は取次の場合、価格設定できないことと仕入れ商品を選ぶことができない構造で、赤字になる銘柄でも、消費者や書店に迷惑をかけるので、仕入れなければならない。そこに取次の社会的使命があるわけだが、経済活動としてはジレンマがある。
* 具体的に低価格書籍は価格帯別に1冊あたりの基準送料を負担してほしいし、それに高正味改定の両方が組み合わせのかたちになるだろう。それに書籍だけの流通を考えると、毎日出荷を1冊単位での配達が続けられるかという問題にも直面するだろう。
* 赤字幅の算出は出版共同流通の稼働により、単品返品データが取れるようになり、出版社個別の損益も把握できるようになっている。
* 出版社の出荷正味が高いと、取次から書店への出荷が「逆ざや」になるケースがあり、取次も書店も一定の利益を得る構造にしたい。
* 取次の現状は経営努力の範囲を超えた環境変化を受けていて、もし必要性がないのであれば、市場からの撤退も覚悟している。
* 今期決算の取次部門が黒字か赤字かのギリギリで、コンビニ部門はすでに大赤字、書籍部門も赤字で、雑誌の黒字がどこまで確保できるかという状況だ。会社全体としては不動産収入でようやく黒字を出しているだけで、経営的にはまったなしである。
* 出版社に負担を依頼するのは書店が減っている中で、書店に赤字補填を依頼すれば、さらに市場を縮小してしまうからだ。
* 出版社への依頼が実現すれば、書籍は安定した出版流通を維持できるし、販売努力でビジネスになる。
だが一方で、雑誌は難しい。雑誌全体の売上がどうなっていくのか雑誌要素が絡んでいるし、先が見えないので、経営計画はさらに雑誌のボリュームが減ると考えている。それに書店が運賃を負担する「返品」処理のコストの問題、専門流通センターからの出荷による「週刊誌」問題がある。週刊誌もかつてのように業量バランスが崩れてしまったからだ。
書籍モデルを確立し、そこに雑誌が載るという大転換により、マスの世界ではなく、個性化している書店に合うかたちで商品や企画の提案をしたい。
これは日販非常事態宣言というべきものであり、前回の本クロニクルとタイムラグなきことを考えれば、取次からの返答と見なすこともできよう。
実際にここまで踏みこんだ発言と危機状況を訴えたことは、管見の限り、取次史上でも初めてである。それにここでは言及されていないけれど、大手出版社に対する支払システムが限界に達していると推測される。
さらにここからわかるのは、日販傘下の書店とTSUTAYAが置かれている出版物も含めた売上状況の悪化で、マージンアップが切迫した問題となっていることだ。もちろんこれは他の取次にしても同様である。
だが出版社ももはや体力を失ってしまっていることからすれば、多くの出版社がさらなる赤字になってしまうし、これまでの出版業界の慣例から見て、そうしているうちに時間が経過していくばかりだろう。
それにここでいわれている書籍をベースとする出版流通システムの確立は可能なのか。大手取次はその誕生以来、たえざる雑誌の成長とともに歩んできたのである。その雑誌すら売ることが難しくなっている現在において、TSUTAYAを始めとして、書籍販売へと転換するのは至難の業というしかない。またTSUTAYAがグロスで売っているように見えるが、大型店にしても驚くほど出版物販売額が少ないことは本クロニクルで指摘したとおりだ。
さらに出店バブルの精算も待ち構えているし、アマゾンの出版社との直取引という「囲い込み」も加速していくにちがいない。将棋に例えれば、アマゾンによって出版社という角が取られ、取次と書店は王手飛車取りのような状況へと追いやられている。そうした中で、この日販非常事態宣言ともいうべきものが出されたことに留意すべきだろう。
またアマゾンの出版社「囲い込み」の資料として、本クロニクルのデータが使われていたように、取次と出版社の正味攻防にしても、双方が本クロニクルのデータと状況分析を正味戦争の武器として援用していると思われる。
3.『FACTA』(4月号)がジャーナリストの大西康之の「恐るべきアマゾン『異次元商法』」を掲載している。
それはアマゾンのジェフ・ベゾスの「あなたの利益は私のチャンスなのです」という言葉から始まっている。彼こそは「あらゆる市場を侵食している男」であり、「アマゾンとのビジネスは引くも地獄、進むも地獄」の例として、「トイザラスの悲劇」がまず引かれている。
トイザラスはこの12年から5年間、アマゾンで玩具を売ってきたことで、売上データを吸い上げられ、それを使ってアマゾン自身が本気で玩具を売り始めると、17年に経営破綻してしまった。
そして次なるターゲットはテレビかもしれないとされている。映画や音楽の見放題、聴き放題サービスの「アマゾン・プライム」、それに向けたスポーツイベント放映権の獲得やオリジナルコンテンツへのテレビをはるかに超える投資は、「世界の民放とメーカーが過去100年以上かけて形成してきた消費社会を打ち壊す革命」となるかもしれないとも述べられている。なぜなら「アマゾン・プライム」でドラマを観る人々はCMを見ないし、「アマゾン・ダッシュ」という小さなリモコンで商品も買われていくからだ。
このアマゾンの世界は「消費者にとっては天国だが、スーパーや民放、メーカーにとっては地獄」という事態を迎えつつある。
まさに「あらゆる市場を浸食している男」の体現としてのアマゾンは、テレビをも飲みこんでいくのかもしれない。それに考えてみれば、私たちのテレビの歴史にしても、半世紀ほどのものでしかないのである。
出版業界にしても、このようなアマゾンと対峙していかなければならないのだ。いみじくも2でいわれていた「消費者」の争奪戦となる。
3900円の年会費を払って「アマゾン・プライム」会員になれば、映画や音楽の見放題、聴き放題はもちろんのこと、配送費無料で、しかも翌日に届き、「プライム・ステューデント」ならば、さらに書籍に定価の1割のポイントがつく。それは高定価の書籍ほどメリットが生じる。書店にしてみれば、安さと便利さと早さでは太刀打ちできないし、複合店の映画や音楽のレンタルも同様である。
前回のクロニクルで、出版社が雪崩を打ったように、アマゾンとの直取引に向かっていることを既述しておいたが、その果てには何が待っているのだろうか。
4.丸善CHIホールディングスの29社からなる連結決算予想は1783億円だが、3億2500万円の赤字の見通し。
それは主として丸善ジュンク堂の退店費用の見直しから、減損損失17億7500万円を特別損失に計上したことによっている。
丸善ジュンク堂を中心とする店舗、ネット販売事業は売上高756億8300万円、前年比0.9%減、営業の損失3億2600万円。店舗数は93店。
また丸善ジュンク堂書店は退店時の撤退費用などの見積り変更と、将来の収益計画への見直しによる減損損失を計上したことで、財政状態が悪化。丸善CHIホールディングス保有の同社株式の実質的価値が低下したため、関係会社株式評価損として、23億4000万円の特別損失を計上。
この決算予想を取り上げたのは、ここで丸善ジュンク堂の退店時の撤退費用への言及がなされていたからである。
2で日販のバブル出店の清算がついていないことにふれたが、それはこの退店時の撤退費用の問題が大きく絡んでいる。これは出店メカニズムにつきまとう問題ではあるけれど、広く知られていないと思われし、私は郊外消費社会論の専門家でもあるので、少しばかり解説しておこう。
アパートやマンションなどの住居系契約と異なり、商業施設の場合、短期間で閉店すると貸す側の投資コストを回収できないことが生じてしまう。それは1980年代からのロードサイドビジネスの建物に顕著で、テナント側の要求に基づいて建築されるために、汎用性のないもので、撤退してしまうと次のテナントが容易に見つからないことが多く生じるようになった。それゆえに賃貸契約に撤退ペナルティが加えられるようになり、契約期間を待たずしての退店は、残存家賃の支払いといった項目がつけられるようになった。
それは次第にロードサイドビジネス以外にも及んでいき、広く商業施設の賃貸契約にも応用されていったのである。しかしこれはテナント側の売上が順調であれば、家賃を払うことができるけれど、売上が落ち、採算を割ってしまうと、営業を続けていくことも困難になる。しかし退店すると、先述したようなペナルティが生じるし、しかも原状回復という条件も重なり、退店時の撤退費用は大きな負担になってしまうのである。しかもかつてのその個々の契約内容の詳細は、開発担当者だけが把握しているケースも多く見受けられた。ハウスメーカーなどによるサブリースにしても同様である。
それゆえにとりわけ大型店の閉店の場合、予想以上のコストがかかってしまうし、まさに閉めるに閉められないケースも多くあると推測される。
このような出店と閉店の契約をめぐるメカニズムを、現在のナショナルチェーンと書店市場に当てはめれば、どのような事態が進行しているのか、想像がつくだろう。
だがこれが出店と閉店の現実に他ならないのだ。
5.『出版月報』(2月号)が特集「紙&電子コミック市場2017」を組んでいる。
17年のコミック市場全体の販売金額は4330億円、前年比2.8%減。
その内訳は紙が1666億円で、同4.4%減、電子が1711億円で同17.2%増。
そのうちの「コミック市場全体(紙版&電子)販売金額推移」と「コミック・コミック誌推定販売金額」を示す。
■コミック市場全体(紙版&電子)販売金額推移(単位:億円)
| 年 | 紙 | 電子 | 合計 |
| コミックス | コミック誌 | 小計 | コミックス | コミック誌 | 小計 |
| 2014 | 2,256 | 1,313 | 3,569 | 882 | 5 | 887 | 4,456 |
| 2015 | 2,102 | 1,166 | 3,268 | 1,149 | 20 | 1,169 | 4,437 |
| 2016 | 1,947 | 1,016 | 2,963 | 1,460 | 31 | 1,491 | 4,454 |
| 2017 | 1,666 | 917 | 2,583 | 1,711 | 36 | 1,747 | 4,330 |
| 前年比(%) | 85.6 | 90.3 | 87.2 | 117.2 | 116.1 | 117.2 | 97.2 |
■コミックス・コミック誌の推定販売金額(単位:億円)
| 年 | コミックス | 前年比(%) | コミック誌 | 前年比(%) | コミックス
コミック誌合計 | 前年比(%) | 出版総売上に
占めるコミックの
シェア(%) |
| 1997 | 2,421 | ▲4.5% | 3,279 | ▲1.0% | 5,700 | ▲2.5% | 21.6% |
| 1998 | 2,473 | 2.1% | 3,207 | ▲2.2% | 5,680 | ▲0.4% | 22.3% |
| 1999 | 2,302 | ▲7.0% | 3,041 | ▲5.2% | 5,343 | ▲5.9% | 21.8% |
| 2000 | 2,372 | 3.0% | 2,861 | ▲5.9% | 5,233 | ▲2.1% | 21.8% |
| 2001 | 2,480 | 4.6% | 2,837 | ▲0.8% | 5,317 | 1.6% | 22.9% |
| 2002 | 2,482 | 0.1% | 2,748 | ▲3.1% | 5,230 | ▲1.6% | 22.6% |
| 2003 | 2,549 | 2.7% | 2,611 | ▲5.0% | 5,160 | ▲1.3% | 23.2% |
| 2004 | 2,498 | ▲2.0% | 2,549 | ▲2.4% | 5,047 | ▲2.2% | 22.5% |
| 2005 | 2,602 | 4.2% | 2,421 | ▲5.0% | 5,023 | ▲0.5% | 22.8% |
| 2006 | 2,533 | ▲2.7% | 2,277 | ▲5.9% | 4,810 | ▲4.2% | 22.4% |
| 2007 | 2,495 | ▲1.5% | 2,204 | ▲3.2% | 4,699 | ▲2.3% | 22.5% |
| 2008 | 2,372 | ▲4.9% | 2,111 | ▲4.2% | 4,483 | ▲4.6% | 22.2% |
| 2009 | 2,274 | ▲4.1% | 1,913 | ▲9.4% | 4,187 | ▲6.6% | 21.6% |
| 2010 | 2,315 | 1.8% | 1,776 | ▲7.2% | 4,091 | ▲2.3% | 21.8% |
| 2011 | 2,253 | ▲2.7% | 1,650 | ▲7.1% | 3,903 | ▲4.6% | 21.6% |
| 2012 | 2,202 | ▲2.3% | 1,564 | ▲5.2% | 3,766 | ▲3.5% | 21.6% |
| 2013 | 2,231 | 1.3% | 1,438 | ▲8.0% | 3,669 | ▲2.6% | 21.8% |
| 2014 | 2,256 | 1.1% | 1,313 | ▲8.7% | 3,569 | ▲2.7% | 22.2% |
| 2015 | 2,102 | ▲6.8% | 1,166 | ▲11.2% | 3,268 | ▲8.4% | 21.5% |
| 2016 | 1,947 | ▲7.4% | 1,016 | ▲12.9% | 2,963 | ▲9.3% | 20.1% |
| 2017 | 1,666 | ▲14.4% | 917 | ▲9.7% | 2,583 | ▲12.8% | 18.9% |
16年までコミック市場全体の販売金額は4400億円台の横ばいで、紙が落ちこみ、電子が伸びるという回路をたどってきた。それは17年も変わっていないが、紙のコミックスは1666億円で、前年比14.4%の減となり、一方で電子コミックスは1711億円で、同17.2%増であるから、初めて電子コミックスが紙のコミックスを上回ったことになる。
しかしコミック全体では1995年の5864億円をピークとして、2005年まで5000億円台が保たれていたことからすれば、電子を合わせても26%マイナスとなっている。やはり17年も紙のコミックス全体の落ちこみは深刻で、推定販売金額は2583億円で、同12.8%減。これは統計を開始してからの初めての2ケタ減とされる。
それがとりわけ顕著なのはコミック誌で、ついに1000億円を割りこみ、917億円、同9.7%減である。その内訳を見てみると、月刊誌の子どもが155億円、同11.4%減、大人が313億円、同5.2%減、週刊誌の子どもが297億円、同14.1%減、大人が152億円、同6.7%減で、コミックス誌全体の凋落が浮かび上がってくる。1997年の3279億円に対し、3分の1以下になってしまい、それは推定販売部数も同様なのである。
それに紙のコミックスの場合、電子コミックスが成長することでバランスがとれているにしても、コミックス誌の場合、電子は36億円、16.1%増でしかなく、伸びてはいるが、そのシェアはわずか3.8%にすぎない。
ここで明らかなのは、紙のコミックスもそうであるように、電子コミック市場は、あくまで紙のコミックス誌が母胎となって出現しているという事実だ。その母胎としてのコミックス誌の凋落は、電子コミックスにしても、旧作の電子化が一巡してしまえば、それほど成長を見こめない分野と化してしまうかもしれない。
6.講談社は青年・女性コミック6誌を月額720円での定期購読サービス「コミックDAYS」、それに紐付けたマンガ投稿サイト「DAYSNEO」を開設。
「コミックDAYS」で配信されるのは、『ヤングマガジン』『モーニング』『アフタヌーン』『イブニング』『Kiss』『BE・LOVE』のコンテンツで、月刊ユニークユーザーは3月1日開始から13日現在で、30万人に達している。20代から40代をターゲットに、書店に足を運ばない読者にコミックを読んでもらうことをコンセプトとする。
「DAYSNEO」はウェブを通じての編集者と漫画家志望者の出会える場を想定し、開発された。
前回の本クロニクルで、講談社の電子・版権サービス部門の「事業収入」が357億円で、総収入の30%を超えたことを既述しておいた。
その電子版路線としての企画がこの「コミックDAYS」などのような具体的なかたちとなって現実化していく。
その一方で、集英社も「週刊少年ジャンプ50周年」キャンペーンとして、マンガアプリ「少年ジャンプ+」の無料配信、「ジャンプPARTY」で100作品の無料公開を発表している。
これは5で記したことに関連するが、こうした試みが紙のコミックス誌のような読者を生み出せるかどうかは未知数で、まだ時間を必要とすることは確かであろう。
7.主婦の友社の月刊誌『S Cawaii !』は6月号をもって季刊ムックに変更。
2001年創刊だが、急速なデジタル化と読者の思考の多様性を鑑みてのリニューアルとされる。

8.枻出版社の月刊メンズファッション誌『2nd(セカンド)』は紙版の発行を休止し、デジタル版へ移行。2007年創刊で、30代から40代の男性読者を対象とするカジュアルファッション情報誌だったが、電子講読数のほうが上回ったことによる。

本クロニクル114などで、2016年はついに雑誌銘柄数が3000点を下回ってしまったことを既述しているが、17年も同様に減少し、18年も続いていくことは確実であろう。
その中でもファッション関係はデジタル環境の急速な変化によって、多大な影響を受けている。それはコミックにおける紙と電子の関係に似ているかもしれない。
odamitsuo.hatenablog.com
9.『選択』(3月号)の「社会文化情報カプセル」がヤマト運輸の料金値上げが経済誌に波及していることを報じている。
ヤマトは東洋経済新報社の『週刊東洋経済』とダイヤモンド社の『週刊ダイヤモンド』に定期購読者の配送料の抜本的値上げを要請。
前者の場合、それは倍となり、総額では六千万円近くで、年間売上20億円の利益が飛びかねないとされる。
日本郵便へ切り替えると、同誌の4割を占める定期購読者に土曜日に届けられず、店頭発売と同日の月曜日にずれこんでしまい、そのメリットがなくなってしまう。それは『週刊ダイヤモンド』も同様で、ヤマトに配達を依存していた出版社は深刻な問題に直面していくことになる。


両社だけでなく、定期購読者を多く抱えている雑誌出版社は同じ事態を迎えているはずだ。ここではヤマトだけが取り上げられているが、日本郵便のゆうメールの値上がりも深刻で、アマゾンのこともあり、送料を出版が社負担すると、安い本では利益が出ないといった状況となっている。
この数年、中小出版社の書籍通販状況をヒアリングしていないが、今後そのことに関して聞いてみようと思っている。
10.『朝日新聞』(3/25)に「夢枕獏の変態的長編愛」と題する全面広告が掲載されている。
そこには『大江戸恐龍伝』(小学館)、『東天の獅子』(双葉社)、『陰陽師』(文春)の広告に加え、積み重ねた自筆原稿の山と自身のポートレート、「虫に生れかわっても」という一文、しかもそれは「物語作家として生きたい」と続いていくのである。



これだけ見ると、出版社の広告だと思われるだろうが、実は夢枕が自費掲載料を負担したものである。作品の書店店頭での寿命の短命化、歯止めがかからない書店の廃業の中で、「忘れかけている過去の作品をもう一度、多くの人に読んでほしい」との思いからで、230書店でのフェアも連動している。
自費出版ならぬ「自費広告」の時代に入ってきているのかもしれない。それにきっと夢枕も「物語」を求め、小田原の書店や貸本屋や古本屋をさまよって時代を思い浮かべているのだろう。そういえば、高野肇が『貸本屋、古本屋、高野書店』(「出版人に聞く」シリーズ8)において、夢枕が常連客だったと語っていたことを思い出した。

11.日本出版社協議会理事で、リベルタ出版の田悟恒雄が『出版ニュース』(3/中)の「ブックストリート」において、「紙と共に去る」ことを告白している。
田悟によれば、リベルタ出版を立ち上げたのは1987年のことで、86年のチェルノブイリ原発事故をきっかけとし、処女出版は『石棺 チェルノブイリの黙示録』だった。それを彼は「無謀な起業に踏み切ったのは、まだ若さとエネルギーを持ち合わせていたから」だと回想している。
それから30年が経ち、田悟とリベルタ出版は「シューカツ」の時期を迎えざるをえなかったことになる。そしてこの一文は次のように結ばれている。
「それにしても、店をたたむというのは容易なことではない。いま零細出版人の脳裏には、むかし耳にした「通りゃんせ」の一節がしきりに去来している。『ゆきはよいよい、かえりはこわいー』」と。
よくわかります。傷が浅からんことを祈る。

12.『FACTA』(4月号)が「コメを売る『ベースボール・マガジン』の落日」を伝えている。
ベースボール・マガジン社は1946年創業で、『週刊ベースボール』と『週刊プロレス』の看板雑誌を中心とし、様々なジャンルのスポーツ雑誌を発行する老舗出版社で、2004年には売上高120億円を計上していた。
しかしその後は業績が低迷し、売上高が100億円を割りこみ、連続減収で、メーンバンクもメガバンクから地銀、信金と二度も替えている。それに加え、栗田と太洋社の破産により、焦げ付きが発生し、16年には本社ビル不動産を売却し、現在では南魚沼産コシヒカリ「ベーマガ米」の販売も手がけるに至ったとされる。


ベースボール・マガジン社で思い出されるのは、子会社の恒文社のことで、1960年代には『現代東欧文学全集』が出された。それは画期的な企画で、映画化されたカザンザキス『その男ゾルバ』やイヴァシュキェヴィッチ『尼僧ヨアンナ』などの収録もみられた。
だが当然のことながら、東欧文学が売れるはずもなく、恒文社は資金繰りに行き詰まり、67年にベースボール・マガジン社も会社更生法申請に至った。
それもあって、当時はこの『現代東欧文学全集』がどこの古本屋でも安く売られていたので、1冊ずつ買って読んだものだった。だがそれもすでに半世紀前のことだったのである。
 (第2巻『その男ゾルバ』)
(第2巻『その男ゾルバ』)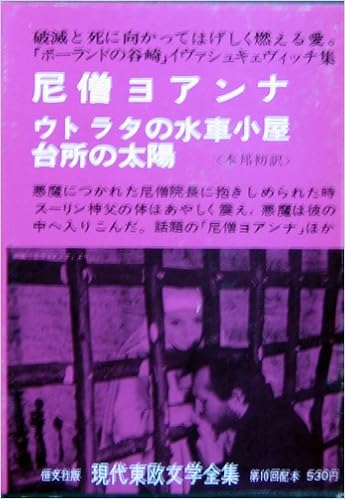
13.『出版ニュース』(3/中)に鈴木久美子「『東京都公立小・中学校司書配置状況』調査を続けて」と、菊池保夫「都立高校図書館の民間委託の問題点」が掲載されている。
前者では具体的にそれらの職名、身分、資格要件、契約期間、報酬などがリストアップされ、小中の学校司書の実情が示されている。
後者ではこれも民間委託業者名が挙げられ、それらに図書館関係の会社は1社もなく、ビル管理会社や清掃などの会社が多いとされる。そして学校司書は神奈川県や埼玉県では新規採用が行なわれているのに、「このまま委託が進めば一番の富裕自治体である東京都は、一番貧しい学校図書館をもつ恥ずかしい自治体となるであろう」と結ばれている。
これらを取り上げたのは、最近地方自治体の公立図書館関係者から委託業者が代わってしまったことで、司書や職員が減ってしまい、困っているとの相談を受けたからである。
それによれば、委託業者はTRCなどではなく、これも多くが生まれているようで、そのキャパシティと実力はそれぞれに差異があり、先に上げた事態は全国で様々に起きていることが確認できた。
やはり公共図書館の現場においても、都立高校図書館のような民間委託、同じく小中学校状況のような司書と職員の配置が進行しているのだろう。
私の場合は門外漢なので、知り合いの大学図書館関係者を紹介しただけで終わってしまったが、日本図書館協会こそはこのような図書館状況をレポートすべきだろう。
14.『出版ニュース』(3/上)の「図書館ウォッチング」28が、「ツタヤ図書館は準備中も営業開始後も、張りぼて様の華やかさと、それとは裏腹の危うさがあります」と始め、その2月の動向を報告している。
それによれば、「和歌山市ツタヤ図書館談合疑惑」を始めとして、問題は続出しているようだ。
しかし驚いたのは周南市の新徳山ビルのツタヤ図書館の開館によって、駅前の徳山銀座商店街の老舗地元書店の鳳鳴館が「閉店を決断」したというニュースだった。ツタヤ図書館開館による地元書店の閉店は初めて伝えられるものだったからだ。
『出版状況クロニクル4』において、その始まりだった武雄図書館に関してはかなり詳細に記しておいたし、地元の書店が影響を受け、売上が悪化していることにもふれておいた。だが地元書店の閉店までは追跡できていなかった。
アルメディアの『ブックストア全ガイド96年版』で確認してみると、鳳鳴館は徳山市銀座の本店の他に、本部、営業部、山口県だけでも10店近い郊外店を展開していたとわかる。所謂典型的な老舗書店だったが、TSUTAYAを始めとするナショナルチェーンによって、郊外店をすべて失い、最後の本店もツタヤ図書館によって閉店に至ったことになる。おそらく他にもそのようなケースが多発していると推測される。

15.このような出版状況を背景にして、『出版状況クロニクル5』は4月下旬に刊行される。
ゲラを校正していて確認したが、2016年から17年にかけての出版シーンは、これまで以上に深刻で生々しい。
1冊になったクロニクルを読むことは、ネットとは異なるものであることを付記しておこう。
なお今月の論創社HP「本を読む」㉖は「エパーヴ、白倉敬彦『même/borges』」です。




 (ちくま文庫)
(ちくま文庫)