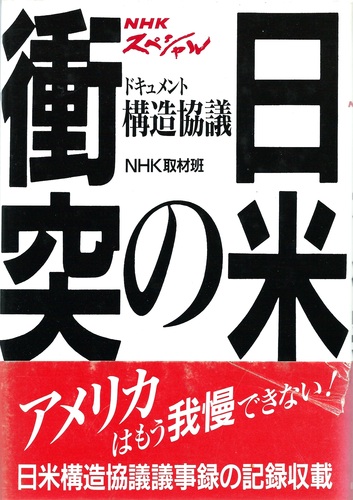一九六九年の二子玉川の高島屋を起源とする郊外ショッピングセンターは、九〇年代における大店法(大規模小売店舗法)の改正と規制緩和、それに続く二〇〇〇年の大店法廃止と大店立地法(大規模小売店舗立地法)の施行によって、大型ショッピングセンターの開発が推進され、九〇年代以後、全国各地で急激に増殖していった。
このような郊外ショッピングセンターの急激な増殖の背後にあるのは、九〇年の日米構造協議に基づくアメリカの要求で、まずそれは都市部の農地の住宅や商業用地への転用の推進、土地の有効利用を制限している借家借地法の改正や大店法の撤廃などが含まれ、第二の農地改革を想起させる内容でもあった。
これは『ドキュメント構造協議 日米の衝突』(NHK)や拙著『出版業界の危機と社会構造』(論創社)を参照されたいが、私見によれば、農村に続いて商店街をも壊滅させ、アメリカ的郊外消費社会をさらに拡大させようとするものだった。五〇年代から六〇年代にかけての日本社会は商店数が多く、人口千人当たり16店あり、それはアメリカの8店に比べて二倍に及び、しかも零細な店が多く、朝は早くから夜遅くまで労働時間は長く、生産性は低いのだが、勤勉な家族労働に支えられ、農村と類似するものと見なされていた。
しかし八〇年代の郊外消費社会の成立によって、幹線道路沿いの田や畑はロードサイドビジネスが林立する風景となり、それは農村を消滅させ、さらに商店街をも衰退させていく。六〇年代まで日本の社会を支えていた農村や商店街という共同体が消えていくことは第二の敗戦であり、アメリカ的郊外消費社会による占領のように思えるし、東京ディズニーランドの開園もまた八〇年代であった。
それに続いて九八年からあらゆる分野の消費者のための「日本における規制撤廃、競争政策、透明性及びその他の政府慣行に関する日本政府への米国政府要望書」(以下「要望書」)が出され始めた。これについては関岡英之の『拒否できない日本』(文春新書)に詳しいが、それは大店法の規制緩和と廃止、大店立地法の施行とパラレルな関係にあるといっていい。

しかしここで留意しなければならないのは、八〇年代に形成されたロードサイドビジネスを中心とする郊外消費社会は、生活者の視点から考えるならば、すでに飽和状態となっていて、さらなる超郊外にショッピングセンターを出店する必然性はなかったのである。だがこの大店立地法の施行によって、市街化調整区域内の広大な農地にも出店できるようになり、全国各地で大型ショッピングセンターの開発が始まった。それはバブルとよべるほどの出店ラッシュと店舗の大型化を伴い、面積に至っては5万平方メートルから9万平方メートルへと、年を追うごとに、まさに巨大なものへと変容していった。いってみれば、それらのショッピングセンター、もしくはショッピングモールとは、超郊外に急速に出現した商店街で、これによってかつての駅前商店街や地域の中心にあった商店街は息の根を止められてしまった。
そうしたショッピングセンター出店状況の中で、その隆盛と繁栄を謳い上げるかのように、二〇〇八年に『日本ショッピングセンターハンドブック』(『商業界』編集部編、八月号別冊)、〇九年に『イオンスタディ』(『販売革新』編集部編、『商業界』一月号臨時増刊)が刊行されたことになる。この二冊は、グルーエンの『ショッピングセンター計画』の四十年後に刊行された日本版に相当するもので、それに出版社も同じ商業界であることは偶然ではないし、流通業界とそのイデオロギー的出版社であり続けた商業界と、ショッピングセンターの深い関係を伝えていよう。
具体的に指摘すれば、『日本ショッピングセンターハンドブック』が本論、『イオンスタディ』がイオンのショッピングセンターやモールに焦点を当てたケーススタディであり、その組み合わせによって、二一世紀を迎えてのショッピングセンター計画の現在とその位相が浮かび上がる構成になっている。それは『日本ショッピングセンターハンドブック』のサブタイトルに示された「SCを理解せずして今日の流通を語れず」との言葉にも示され、また編集協力は日本ショッピングセンター協会とある。これは前回既述しているが、七三年に設立されているので、六〇年代に革新的な経営者たちが立ち上げたA・S・C・C(Advanced Shopping Center Conference)の後身だと考えられる。
『日本ショッピングセンターハンドブック』は次のような章立てと内容になっている。
第1章 SCの特性とSC業界 1 SCの機能 2 SCの俯瞰、相関図 3 SCの変遷 第2章 SCビジネスの主役たち 1 ディベロッパー 2 テナント 第3章 SC最前線 1 都市再開発・まちづくりとSC 2 SCの新たな創造・開発 3 変貌するSCの運営・マネジメント
これらのそれぞれに写真、図表、様々なデータ資料が添えられ、「白書」的な役割も加わり、〇八年における最も包括的なショッピングセンターに関するレポートといえよう。その資料的な意味は現在でも後退しておらず、数字を含んだデータ資料にしても、最新のものは日本ショッピングセンター協会のホームページなどで補足すればいので、ショッピングセンターについての基本的文献としての価値を失っていない。
以前に広瀬勲の『実践ショッピングセンター開発』(誠文堂新光社、八四年、新版九四年)に目を通したことがあったが、それに比べて『同ハンドブック』は記述にしても内容にしても、その後のショッピングセンターのあり方と進化を誇示するかのようなトーンに包まれている。
まずショッピングセンターは「一つの単位として計画、開発、所有、管理運営される商業・サービス施設の集合体で、駐車場を備えるものをいう。その立地、規模、構成に応じて、選択の多様性、利便性、快適性、娯楽性等を提供するなど、生活者ニーズに応えるコミュニティ施設として都市機能の一翼を担うもの」とされる。アメリカの「要望書」はあからさまに「消費者ニーズ」を主張しているが、ここではまだ「生活者ニーズ」となっていて、それは日本のショッピングセンターが「コミュニティ施設」であるとの定義に接触しない配慮だと考えられる。
そしてアメリカにおけるネイバーフッド型ショッピングセンターの誕生から、グルーエンによる郊外ショッピングセンターへと至る歴史、それを継承しての二子玉川高島屋ショッピングセンターの出現が語られ、現在の到達点と概括的状況が示される。それによれば、ショッピングセンターは約3000、市場規模は約30兆円、平均面積、テナント数は5000坪で50、年間売上高は100億円で、小売業売上高の20%、総売場面積の30%を超えている。八五年のショッピングセンターの売上高は10兆円だったので、この二十年間で三倍に至ったことになる、九〇年代以後のショッピングセンターの成長が、八〇年代の郊外消費社会の主役だった、単店からなるロードサイドビジネスと同様のものだったとわかる。
この流れはまさに消費者が九〇年代になって、郊外のロードサイドビジネスから、超郊外の大型ショッピングセンターへと移行していった事実を物語っている。九〇年代はバブル崩壊とともに始まったにもかかわらず、大店法の規制緩和と改正によって、千を超えるショッピングセンターが開業し、様々なバリエーションが開発されていったからでもある。そして二〇〇〇年以後は大店立地法の下で、さらに大型化、多様化したショッピングセンター時代を迎え、それが現在まで続いていると考えていいだろう。
その一方で、この間に何が起きていたかをも、『日本ショッピングセンターハンドブック』はレポートしている。それはいうまでもなく、従来の商店街の衰退と商店数の減少であり、〇七年の「商業統計」は113.7万店とあり、過去最大の落ち込みを示している。
日本の商店数は、ピークの82年で172万店。従ってこの25年間で、58.4万店もの商店が全国から消滅したことになる。これを年間に直すと2.3万店で、(中略)わが国の小売業商店数が恐るべきスピードで減少していることがお分かりいただけよう。
言うまでもなく、それら減り続ける商店の主体は「零細小売業」である。実際、従業員4人以下の「小規模店」は、ピーク時の145万店(82年)から75万店(04年)へと、何と5割近い大激減だ。
そしてこれら「消え行く零細店」のほとんどが単独店か、あるいは商店街や市場など「非SC立地」の商店と見なされる。
それに対して、ショッピングセンターに入居するテナント総数は八二年の5.3万店から〇七年には13.7万店と2.6倍になり、「『SCに出店する小売店』は、淘汰されないどころか増加の一途をたどっていて、集合商業施設としてのショッピングセンターでなければ生き残りが難しく」、また百貨店などにとっても郊外モールが「都市型商業最大の“天敵”になっている」状況を招いているとされる。
ここに簡略に示した見取図だけでも、一九八〇年代から二〇〇〇年代にかけて起きた消費社会の変貌をうかがうことができるだろう。それは駅前や中心地の百貨店や商店→郊外のロードサイドビジネス→超郊外のショッピングセンターへと、消費者の移行していく流れに他ならないし、フリースタンディングの個人・零細商店は生き残れず、退場するしかない。そうでなければ、コンビニに代表されるようなフランチャイズシステムに組み込まれるかの選択しかない。その事実はコンビニか、ショッピングセンターに入居するナショナルチェーンだけが現在において存続を許されていることを告げている。
とりわけそれは出店をめぐるメカニズムにも表われている。八〇年代におけるロードサイドビジネスによる単独出店は、シンプルなオーダーリースシステム=借地借家方式を主としていたが、ショッピングセンターに至っては、デベロッパーによる大型商業施設の開発、いわばひとつの消費社会の創出プロジェクトと化し、その資金調達と運用は複雑な金融工学が駆使され、テナントとの関係は定期借家契約によって管理され、超郊外の管理された消費国家の運営のような業態となっていく。
マイク・ディヴィスは郊外とショッピングセンターに包囲されたロサンゼルスをCity of Quartz(Verso,1990),『要塞都市LA』(村上敏勝、日比野啓訳、青土社、〇一年)として描き出した。「水晶都市」とはロサンゼルスのメタファーで、ダイヤモンドのように見えるが安物で、透明のようだが何も見えない都市を意味している。ディヴィスはグルーエンやジェイコブスのCities とはまったく異なる、都市における土地開発と経済の再構成によって生まれる権力構造、アメリカの土地投機の系譜学とそれに連なるショッピングセンター問題、郊外デベロッパーとケインズ的郊外化、さらには一望監視施設的ショッピングモールと都市のセキュリティ化にまで言及している。
 |
 |
それゆえにディヴィスは自著を次のように称している。ベンヤミンがロサンゼルスにやってきてバーに入り、ブローデルとエンゲルスと会い、ベンヤミンはロサンゼルスの権力と記憶、ブローデルは世界史に連なるファクター、エンゲルスは労働者階級を分担して書いたプロジェクトだと。そしてまたディヴィスの著作はジェイムズ・エルロイの『ブラック・ダリア』 (文春文庫)に始まる「暗黒のLA四部作」と併走しているといっていい。なおエルロイに関しては本ブログ「ゾラからハードボイルドへ」26の「ジェイムズ・エルロイと『ブラック・ダリア』」を参照されたい。

別のところでと考えていたが、思わず『要塞都市LA』にふれてしまい、『イオンスタディ』への言及がおろそかになってしまったけれど、九〇年代以後の急激なショッピングセンター開発もディヴィスが指摘するような様々な問題がつきまとっているはずだ。そのようなショッピングセンターに包囲され、現在の日本の消費社会は稼働しているのである。しかしそれは少子高齢化が進行する中での出来事であることに留意すべきだろうし、このような現実の行方に対する注視を続ければならない。やがて本連載35の『ゾンビ』におけるショッピングセンターの風景が出現するかもしれないからだ。
なお近年になって、若林幹夫『モール化する都市と社会―巨大商業施設論』(NTT出版、二〇一三年)が刊行されているが、矢作弘の「各地に広がる大型店の郊外開発包囲網」(『世界』〇七年七月号 )や、亀井洋志のルポ「イオンは地方の救世主なのか」(『文藝春秋』一四年四月号 )といった「イオン化する日本」批判も参照すべきであることも付記しておく。