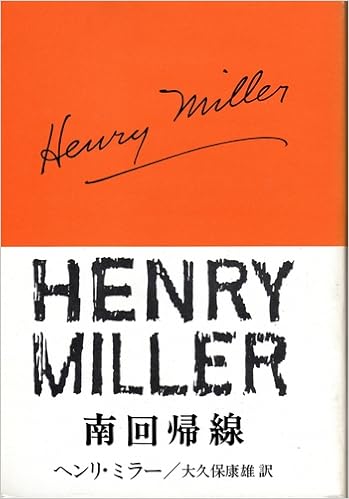前回の有吉佐和子の『非色』の舞台となったマンハッタンのハーレムから、さらに南に下ったところにイースト・ヴィレッジがある。『非色』にはプエルトリコ人たちのスラムとして、スパニッシュハーレム=イースト・ハーレムが描かれていたけれど、イースト・ヴィレッジへの言及はなかった。

有吉の作品から十五年ほどを経て、イースト・ヴィレッジそのものを物語のトポスとする宮内勝典の『グリニッジの光りを離れて』が刊行された。『非色』において、主人公の笑子が「戦争花嫁」として後にしたのは、まだ敗戦と占領下にある、まさに戦後の日本だったが、『グリニッジの光りを離れて』の「私」が出立してきたのは高度成長期を迎えていた日本であり、そうして三年間のカリフォルニアでの様々な肉体労働生活を経て、晩秋にニューヨークへとやってきたのだ。物語の時代設定は一九六八年から六九年にかけてだと見なせよう。
「私」は片道切符で五万円相当のドルを持ち、観光ヴィザでアメリカへと渡ってきた。そしてカリフォルニアで不法労働に従事し、不法滞在者の身だったから、もしそれが露見すれば、留置場にぶちこまれ、国外追放か、日本への強制送還、もしくは刑務所か、軍隊送りとなるだろう。それに当然のことながら日本へ逃げ帰る旅費もなかった。
また手持ちの金は二ヵ月の食品分しかなく、このニューヨークで住む場所と職を見つけなければならないのだ。それらを求めて、「私」はマンハッタンの真ん中にあるペンシルヴェニア駅から歩き出す。まずは文化と芸術の聖地グリニッジ・ヴィレッジからで、そこは日本でビート族にかぶれ、鎌倉の円覚寺で禅の真似事をしたり、ヒッチハイクで日本中を放浪していた「私」にとって、「憧れの地」だったからだ。しかしそこはすっかり観光化し、生活の匂いが希薄だった。それもあってその東側の街に居を求めようとする。
イースト・ヴィレッジに住もうと決めた。五日間、マンハッタンをほっつき歩いて、そこが一番気に入った。プエルト・リコ人移民の多いスラム街である。煉瓦造りの古い建物がひしめきあい、まわりの高層建築群のなかできわだった低く陥没し、焦げ茶色の沼のように沈んでいる。街が気に入った。それにプエルと・リコ人に本能的な親しみを感じた。まず皮膚の色がちょうど同じくらいだし、カリフォルニアで肉体労働をしていた頃、よく出稼ぎのメキシコ人とつき合っていたから、スペイン語も片言なら話すことができた。同じように髪も黒く縮れており、脚はこちらの方が短いが背丈そのものは、ほぼ同じぐらいだった。この真黒に日焼けした皮をかぶっているかぎり、プエルト・リコ人街にうまく紛れ込んでしまえるだろう。それに黒人もいるし、少数だが白人も住み、中国人の経営するクリーニング屋もある。イタリア人街も、チャイナ・タウンも、ユダヤ人街もさほど遠くなかった。このスラム街は、どんな民族、どんな人種でも呑み込んでしまう多様性や混沌があり、しかも、まっとうな生活の匂いが満ちていた。ここに潜り込んでしまえば、私がどこから来たのか、国籍がどこか、だれひとり気にもかけないだろう。
 (河出文庫版)
(河出文庫版)
このような「私」の人種の混住する生活に対する親和性は引揚者の子、他所者の子として扱われてきた子供時代の体験に起因している。家族は敗戦後に満州から九州南端の港町に引き揚げてきたのである。それは幼時の記憶もなく、辺鄙な土地に運ばれ、他所者と呼ばれながらも、この土地しか知らず、根源的な場所がないという不安をもたらすものだった。それゆえに「外地」「外国」こそが自らの地であり、その象徴たる「アメリカ」こそは自分が他所者ではなく、「完全な外国人」としての居心地のよさを感じさせてくれる。そこにはもはやどこにも帰れない、また普通の市民社会には加われない偽名の下層労働者の群れが棲息しているにしても。いってみれば、戦後の日本社会の閉塞状況からの脱出が試みられ、そのような視座から観測されることによって、イースト・ヴィレッジという人種の混住するスラム街も異化され、その「私」ならではの街が浮かび上がってくる。その瞬間のシーンを引いてみる。
スラム街の夕暮れを歩いていると、よく海の底に立っている気がした。遠くの摩天楼に突き刺されて天蓋に穴があき、そこから宇宙が漏水しはじめて、この煉瓦造りの老朽ビルの谷底まで青い水が満ちてくる。横なぐりに射す光りが、スラム街の上空を超え、高層ビルだけを金色に照らしている。街角に立ち止まって見つめていると、この青い水底から、水面の上へ突きだした岩礁や、明るい光りの世界を仰いでいるような淋しさがこみあげてきた。脚もとの影も溶けだし、いつも海底のスラム街から世界が昏くなっていく。
そして「私」の「海底のスラム街」での生活が始まっていく。ガスレンジと冷蔵庫があるだけの二部屋のアパートを月八〇ドルで借り、JIRO SAHARAという偽名の身分証明書を入手し、仕事を探して、街を歩きまわり、場末の小さなバーの仕事を見つけた。そこは六十過ぎのドイツ移民の小柄な老人が経営するバーで、四メートルほどのカウンターがあり、中央に玉突台が置かれていた。「私」の仕事はバーテンと雑役係を兼ねるものだったから、第二次大戦前に大西洋の豪華客船のチーフバーテンをしていたことを誇りとする店主からカクテルの作り方を学んだ。そのバーテンの仕事はこれまで体験してきた移民向きの肉体労働と異なり、「生きるすべ」を備えた「一つの技術」のようにも思われた。
といっても、そのバーはポン引きらしい移民たちと様々な人種の娼婦がたむろする場所で、娼婦たちはビールの小壜一本で何時間もカウンターにねばり、客を待ち受けていた。その中にエズメラルダというプエルト・リコ移民の、何歳くらいなのか見当のつかない娼婦がいて、下手な英語とスペイン語をごちゃ混ぜにして喋り、「まっとうな人間がこの世で時間を経ていくのとは全く異質な、もっと加速された時間に躰をさらし、どんどん老化しているように見えた」。さらに彼女は麻薬中毒者でもあり、その姿はムンクが描いた女性を想起させるし、それは精神病理学のミンコフスキーの著書タイトルをもじっていえば、プエルト・リコ人移民の娼婦のスラム街での「生きられた時間」、すなわち「全く異質な、もっと加速された時間」を表象していよう。
「私」はほとんど客のつかないそのエズメラルダがスラム街に昇天していく幻像を見て、彼女を買う。エメラルドを意味するらしいエズメラルダは、ジョルジュ・バタイユのマダム・エドワルダのようにして、「ジャパン」からやってきた「私」と性交するのだ。またそのような娼婦との関係や描写はヘンリー・ミラーを喚起させる。この時代にあって、ミラーはアメリカ文学を代表するように、『北回帰線』『南回帰線』『セクサス』(いずれも大久保康雄訳、新潮社)も文庫化されていたことを思い出させる。
そうして「私」は暮らしていくくちに、「海底のスラム街」のみならず、この「摩天楼の街全体」が廃墟となることを夢想する一方で、スラム街の荒涼とした悲しみの中にも、生活の多様な匂いや情景が独特の懐かしさを感じさせることにも気づいた。それらはかつての日本の生活とも共通するものだったからだ。おそらくイースト・ヴィレッジに居を定めたのも、そうしたアトモスフィアに引き寄せられてであろうし、戦後の日本の記憶はアメリカのスラム街とも共通するものだったといえよう。
それは娼婦たちが「夕暮れの青い水槽に群れる極彩色の熱帯魚」のようにうろついている風景も同様で、「私」の父は引揚げてきた港町で女郎相手の派手な看板をつけた化粧品屋を営み、そこには女郎たちが群がり、繁盛していて、「私」はよく店番もしていたのである。猥雑でありながらも、それは「私の記憶の中の黄金時代」だったし、それに同じ他所者仲間は彼女たちの連れ子だった。しかしそのような情景も売春禁止法の発令による遊廓の閉鎖とともに消えていき、終わりを告げるのだが、それがアメリカのスラム街で見出されたことになる。そして雪が降るスラム街は生まれた土地のハルピンをも彷彿とさせ、街のイメージは「私」自身も投影される重層的なものとして造型されていく。
バーには娼婦やプエルト・リコ人たちだけでなく、ブラジル人やロシア人の亡命者も集い、混住のトラブルも起き、「私」のほうは強盗に襲われたり、アパートに空巣狙いに入られたりして、スラム街の冬が過ぎていく。路上には凍死者が増え始め、無料で食べ物を与えてくれる救世軍施設の前には老いた浮浪者や失業者たちが行列をなしていた。それらの光景は「多様な移民たちを受け入れ、むしゃぶり尽くしたあと、そのぬけ殻を凍りついた路上に吐き出しているように見えた」。これもスラム外の現実で、何としてでもその列に入ることだけは避けなければならなかった。
それでもスラム街は春を迎え、夏になり、「私」はアメリカにきてから四年近くが過ぎ、二十六歳になっていた。そんな時にプエルト・リコ移民の若者から、ニューヨークの避暑地ロング・アイランドの会員制のビーチクラブでのバーテンの仕事を教えられた。そこを飛び込みで訪れると、幸いにして採用され、翌日から働くことになった。バーを辞め、アパートも引き払った。給料はバーの二倍で、それにチップもついたし、今度の仕事はバーに比べれば、休息しているも同然で、体力を回復し、次の旅に備えている思いにかられた。夏が終わる頃には二千ドルが貯まり、それは生まれて初めて手にする大金だった。ニューヨークに戻り、イースト・ヴィレッジよりもスラム化しているロワー・イーストサイドの木賃宿に入った。これ以上安いところはないところのアルコール中毒者や失業者たちの最後の吹き溜りで、三段ベッドが並び、一泊六〇セントだった。あのバーを訪れると、フランクは驚くほど老けて見え、娼婦のエズメラルダが死んだことを知った。「私」はその野辺の送りをするかのように、LSDを買って口に放りこみ、その幻覚作用に襲われながら街を徘徊する。「見なれた街が、見なれる外見でそこにありながら、どこか世界の源、宇宙の涯に投影されている自分の記憶のなかのスラム街を歩いている」。そして無数のエズメラルダが幽霊のようにまとわりついてくるのだ。
その「reincarnation」=「輪廻」「再生」ともいうべき体験からめざめ、「私」はメキシコへと出国し、インドへ向かおうと決意する。サンディエゴの国境から車でメキシコへと至るのだ。
ふたつの丘の谷間、赤銹を吹いた鉄条網の切れ目に、踏切りをおもわせる木の遮断機が見えた。道は、半砂漠の荒地を真南につらぬき、さらに遠くへ奥まっている。長い、遠まわりの旅をしている気がした。曲りくねり迂回しながら、いま、おれはインドへ向かおうとしている。ほんとうに辿り着けるだろうか。緑の菩提樹の森、ガンジス河のほとり、光が路、人間の生死が彫深く刻まれ、それら全てが発光している土地へ……。
一九六〇年代後半から七〇年代にかけて、宮内のような戦前生まれの世代や私と同じオキュパイド・ジャパン・ベイビースの多くがアメリカやヨーロッパやアジアに向かい、それをテーマとする多くの作品が提出され、七〇年代後半からひとつの戦後文学とノンフィクションの潮流を形成することになった。後に出された宮内のエッセイ集『LOOK AT ME―おれを見てくれ』(新潮社、一九八三年)を読むと、そうした背景の大半が含まれていて、この『グリニッジの光りを離れて』は、そうした作品の典型にして、それらを代表する作品と見なすことができよう。またそれは有吉の『非色』に続いて、アメリカのスラムでの日本人の混住を描き、もうひとつのアメリカを開示してくれたことになろう。しかし現実のハーレムやイースト・ヴィレッジはグリニッジ・ヴィレッジではないけれど、観光化されたトポスのようにして、ニューヨークのガイドブックなどに紹介されている。だがスラム街が消滅したはずもないし、それらはどこにいったのであろうか。