 |
 |
米軍基地や前回言及したデペンデント・ハウスに象徴される占領軍住宅を日常の風景として、また目に焼きつけて成長した少年がいる。彼はまさに「基地の街に生まれて」というエッセイを書き、そこで佐世保には米軍基地があり、朝夕にはアメリカ国歌に合わせて星条旗がはためいていたと述べている。そしてアメリカは日本の歴史が初めて体験した「占領軍」で、そのオンリーの生活を通じて、「私は『武装した外国人によって自国の女が飼われる』のを目撃した最初の世代」だとも記している。
『村上龍全エッセイ1982−1986』(講談社文庫)の一編だが、同じく所収の「森永製菓への脅迫文」において、「占領された者だけが文学へ向かう。彼は掠奪されているのだ」とも書いている。こちらに引きつけていえば、占領とは強制的混住を意味しているし、それは基地のある郊外に否応なく表出してしまう。それは大江健三郎の、日本人によるアメリカ兵の「飼育」ではなく、アメリカ兵による日本人の「飼育」のようなかたちをとるだろう。そのために佐世保ならぬ横田基地を背景として、村上は占領と郊外の風景を『限りなく透明に近いブルー』の中に描き出す。

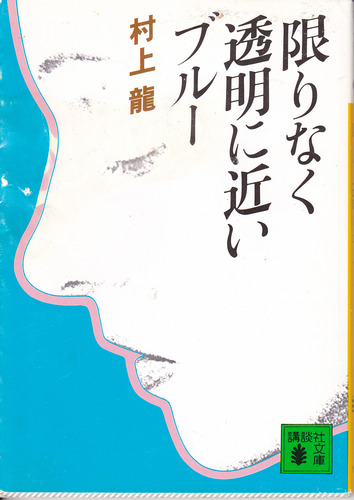
この「ブルー」とは、続いている占領下における基地と郊外の「憂鬱」に他ならないことを、『〈郊外〉の誕生と死』で論じておいたが、もうひとつの郊外消費社会の「憂鬱」に関しては少ししかふれられなかったので、ここで取り上げておきたい。それは八二年から八四年にかけて、『ブルータス』に連載され、八五年に刊行された『テニスボーイの憂鬱』である。

この作品は書かれた時代が八〇年代前半ということもあって、バブルに向かいつつある郊外、「二十年前は山ばかりだった横浜北部の、新興住宅地」を舞台としている。主人公のテニスボーイの青木は開発による土地成金の一人息子で、三十歳である。地元でステーキハウスを二軒経営していて、妻と一歳半になる息子がいる。車はメルセデスベンツだ。父親は億万長者だが、残ったわずかな土地でナスとトマトを作り続け、浪費に走ることはない。母親は子宮癌で、薬の副作用のためにからだは腫れ上がり、顔も歪んで死んでいたが、家庭不和や精神的退廃はないと説明されている。
このようなイントロダクションの説明からすれば、首都圏郊外の土地成金一家の息子で、実業家としての豊かな生活が書割であっても、少しばかりほのめかされてもかまわないのに、村上龍特有のナラティブと文法によって、奇妙なまでのアンバランスな生活が浮かび上がり、それは時としてグロテスクなイメージをももたらしている。飼っているアイリッシュセッター犬の吠え声は「お前らは人間のくずだ」といっているようだし、女中は自由が丘のキャバレーの元ホステスで、目前に迫ってくると死んだふりをしたくなるほどの「ものすごい顔の女」である。父親はこれまでにイノシシを八十九頭撃ち殺し、女房はコンバースのジョギングウェアを着て、ジバンシーのサングラスをくもらせ、テニスボーイの昨夜の素行を疑い、子供を連れ、実家に帰ろうとしている。
しかも他ならぬ第一章の始まりにおいて、「テニスボーイは犬の吠え声で目が覚めた」と書き出されているのだ。それらのイメージと妄想が重なり、テニスボーイは「自分が世界一恵まれない男に思えてきた」。車で出かけようとしたが、路上で幼児が遊んでいたので、ブレーキを踏み、母親が現われるのを待つと、太った眼帯の女が出てきて、バンパーの金文字板に十一回頭を下げた。テニスボーイはその視線の奥に憎悪を見てとり、呟く。「ねたむなよ貧乏人、メルセデスベンツに乗っていてもむちゃくちゃ不幸な人はいっぱいいるんだからな」と。その言葉は八〇年代を迎え、かつての「占領軍」のような豊かな生活を送ることができるようになっても、「不幸な人はいっぱいいる」ことが暗示されているように思える。
そしてテニスボーイは店にチーフやコックなど総勢十九名を前にして、訓示する。
おはようございます。実は昨夜、つい道路一本向こう側に来春オープンするデニーズさんの営業の方と席を同じくしていたのですが、最近の統計によりますと、アメリカの外食比率は二食に一回に近づき、日本のそれは三食に一回に近づいているそうです。そして日本の外食市場の需要そのものの大きさは十兆円から十五兆円あるといわれ、二十兆円台にのることも予想されています、このマーケットの巨大化は経済が豊かになればなるほど進むとみられております。豊かな生活を求める気持ちと、女性が社会に…………………
この後に「社員の一人があくびをした。テニスボーイもあくびをしそうになった」と続いている。それからタイトルにある「テニスボーイ」のテニスとの関係やゲームの内容なども語られていくのだが、ここではあえてそれらにはふれない。この作品にこめられたテニス小説としての一面、及びテニスボーイとテニスに表象されるメタファーは承知していても、ここではバブル前期ともいえる八〇年代の郊外と、彼の「失われた時を求めて」に焦点を合わせてみたいからだ。
 (幻冬舎版)
(幻冬舎版)
これまで紹介してきた『テニスボーイの憂鬱』の主人公青木をめぐる家族と仕事の見取り図は、物語の始まりからわずか十ページ足らずで提出されている。それは村上ならではの特異なナラティブに加えて、青木のモノローグ、書割のような夫婦の会話や父親の毎日繰り返される言葉、店のチーフのスワッピング報告などがポリフォニックに織りなされ、進行していく。前述したように、そのような物語の構成と進行は、この作品にアンバランスにしてグロテスクな効果を与えている。それは戦後かつてないバブル期を迎えようとしているのだが、第二の敗戦ともいうべき占領が完成した八〇年代の歪みの反映のようにも思われる。それを映し出す鏡がアメリカ的風景に覆われた都市郊外であることはいうまでもないだろう。
したがって物語における色彩の濃淡はあるにせよ、それらのファクターをまずラフスケッチのように示し、テニスボーイの「憂鬱」の内側へと誘導していこうとしている。しかもそれが「ステーキハウス」=ロードサイドビジネスとつながっていることにも注目すべきで、引用した「訓示」は郊外の外食市場の拡大を伝えると同時に、そのパロディ的ニュアンス、郊外におけるありとあらゆるものの混住をも伝えようとしているかのようだ。だがその基調音は「ゆううつだゆううつだゆううつだゆううつだゆううつだゆううつだ………」という呟きである。
テニスボーイの原風景として常にフラッシュバックされるのは、開発される前の情景である。
赤田、この一帯は昔からそう呼ばれてきた。横浜のチベットと呼ばれ、開発が最も遅れたのもその赤土のためなのだ。テニスボーイは雨の日の赤土を決して忘れない。滑って危険だというので大人達は赤土の登校路に砂利を撒いた。ゴム長の靴底に尖った砂利石がくいこみ、雨は地面で赤く跳ねた。水溜まりは鮮やかな茶褐色で濁り、転んだりすると汚れるし砂利石で怪我をするので子供達はすぐ前方の地面をしっかり見て一歩一歩真剣に歩いた。(中略)ヨシヒコ(テニスボーイの一歳半の息子―引用者注)はそんな道を歩くことはないだろう。テニスボーイはそう思った。雑木林や畑はどんどんなくなっていく。ヨシヒコが歩くのは東京や他の街と変らないコンクリートやアスファルトの道だ。
かつてどこの道も舗装されておらず、雨が降れば、いつもぬかるんでいた。テニスコートがある場所も以前は沼だったのだ。変わったのは風景や道ばかりでなく、生活そのものも同様である。雑木林にいた雉子や小綬鶏、沼の蛙やホタル、山の峰の子やあけびを失った代わりに、「家は新しくなり、外車や毛皮や宝石や家具が、つまりそれまではテレビや雑誌でしか知らなかったものが、勝手に押し寄せてきた」。そいれまでは道路も電車もない山の中だったから、魚を食べるのは正月だけで、あとはいつも干物だった。それがシャンペンと美食とテニスの日々へと至ったのである。
そのようなプロセスを村上は丁寧に注釈している。「それらを得て、失ったものが見えなかった。どうしようもない雑木林が失くなっても何かを手放したなどという実感があるわけがない」と。この言葉は、八〇年代におけるロードサイドビジネスの増殖によって成立した郊外消費社会の実態をえぐっているようにも思える。外食産業を始めとするロードサイドビジネスの各店舗はかつての田や畑に建てられていったのであり、田や畑の風景が失われたところで、「何かを手放したなどという実感」が生じるはずもなかった。そのような風景の転換を経て、均一的なロードサイドビジネスに覆われていき、郊外消費社会が出現するに至ったのである。
しかしテニスボーイが思い出す歌は、ユーミンの「あの日に帰りたい」や小林旭の「さすらい」で、特に彼はメルセデスベンツの中で後者を聞くことを好み、時として涙ぐむのだ。それを子供の頃、映画館で馬に乗ったまま歌う小林旭の姿を何度も見たこと、「さすらい」に喚起され、今は建売住宅が並んでいる昔の山道を一人で登り、公民館で田舎芝居や奇術の興行をうっていた道化師の一団と一緒になり、オート三輪に乗り、一人で置き去りにされたことを思い出すのだ。それが彼の原風景であり、現在の彼をも呪縛して止まない。
ところがテニスボーイはステーキハウスのテレビコマーシャルのモデルである吉野愛子と知り合い、愛人関係となる。彼女は長野県出身で、彼と同じような原風景と体験を共有していた。それを機にして、テニスボーイは実業家として飛躍し、次々に新しい店を出店し、五軒のオーナーとなり、順風満帆な生活に彩られていく。だがそれでも原風景にも似た「寂しい町」で暮らしたいという思いに駆られる。それは「マクドナルドとかケンタッキーとか絶対にないような町だ」。それに対して、新たな愛人は答える。「難しいわよ、そんなの、今、どこにでもあるもの、あたしの田舎にもできたって言うし、そりゃやっぱり寂しい町しかだめね(後略)」
このように絶えず、テニスボーイは開発された郊外消費社会からの脱出を願い、そのために「憂鬱」がはれることはない。声高に反米や占領が語られているわけではないにしても、この作品は、八〇年代におけるそのようなバブルの底に流れるアトモスフィアを描いていると見なせよう。それが「憂鬱」であり、嘔吐として表われている。彼は最初から嘔吐に言及し、彼の周りの人間もよく吐き、彼自身も吐き気をもよおし、時として吐いている。
そうした『テニスボーイの憂鬱』を読みながら思い出されたのは、サルトルの『嘔吐』だった。これは当初のタイトルを『メランコリア』、すなわち『憂鬱』として書かれたもので、主人公のロカンタンも邦訳名のように「嘔吐」していないが、常に吐き気を感じている。その吐き気は第二次大戦を前にしたヨーロッパ秩序と存在の崩壊に起因するとも解釈できようが、それに対し、テニスボーイの吐き気は占領と第二の敗戦による日本的アイデンティティの喪失と考えられるかもしれない。

なお村上は九〇年代になって、『メランコリア』という作品も書くことになる。これはまた別の機会に譲ろう。

| ◆過去の「混住社会論」の記事 |
| 「混住社会論」11 小泉和子・高薮昭・内田青蔵『占領軍住宅の記録』(住まいの図書館出版局、一九九九年) |
| 「混住社会論」10 ウラジーミル・ナボコフ『ロリータ』(河出書房新社、一九五九年) |
| 「混住社会論」9 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(早川書房、一九五八年) |
| 「混住社会論」8 デイヴィッド・ハルバースタム『ザ・フィフティーズ』(新潮社、一九九七年) |
| 「混住社会論」7 北井一夫『村へ』(淡交社、一九八〇年)と『フナバシストーリー』(六興出版、一九八九年) |
| 「混住社会論」6 大江健三郎『万延元年のフットボール』(講談社、一九六七年) |
| 「混住社会論」5 大江健三郎『飼育』(文藝春秋、一九五八年) |
| 「混住社会論」4 山田詠美『ベッドタイムアイズ』(河出書房新社、一九八五年) |
| 「混住社会論」3 桐野夏生『OUT』後編(講談社、一九九七年) |
| 「混住社会論」2 桐野夏生『OUT』前編(講談社、一九九七年) |
| 「混住社会論」1 序 |