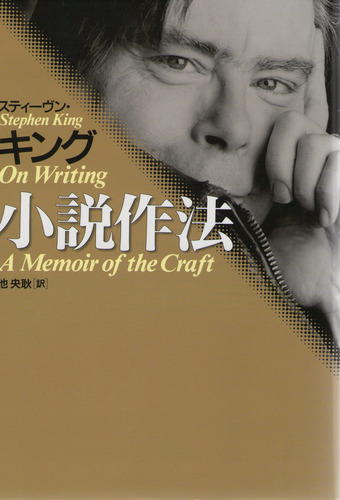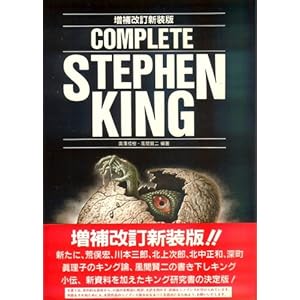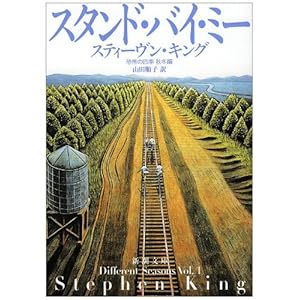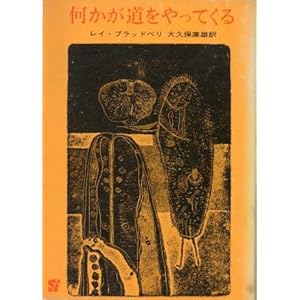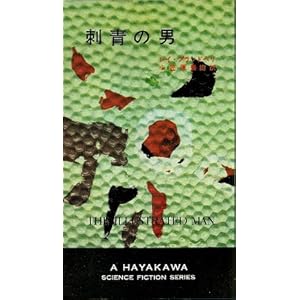大友克洋の『童夢』と岡崎京子の『リバーズ・エッジ』におけるスティーヴン・キングの影響に関して指摘したこともあり、ここでキングについても一編書いておきたい。それは大友と岡崎のコミックのみならず、キングは一九八〇年代以降の日本の小説や映画に多大な影響を及ぼしたと考えられるからだ。おそらく日本のホラー小説の成立もキングの作品群の存在を抜きにして語れないように思える。
さらにキングの生まれ育った時代と状況をたどってみると、彼は一九四七年生まれなので、五〇年代に少年期を過ごし、ホラー映画やSF小説に目覚め、六〇年代には多くの習作を書き、七三年に『キャリー』(永井淳訳、新潮文庫)でデビューしている。それは同時代の七一年に刊行されたW・P・ブラッティの画期的なホラー『エクソシスト』(宇野利泰訳、新潮社、創元推理文庫)の大ベストセラー化や映画化とも無縁ではないにしても、キングの『キャリー』に始まる初期のホラーは、ハルバースタムが『ザ・フィティーズ』で描いた郊外消費社会の出現に象徴される五〇年代をルーツとしているし、そこから始まるアメリカの六〇年代から七〇年代にかけての歴史を描いてきたと見なせるだろう。
キングは『小説作法』(池 央耿訳、アーティストハウス)において、影響を受けた「参考図書」九六冊をリストアップし、その中に『ザ・フィティーズ』も挙げられている。私見によれば、アメリカのSF黄金時代は郊外の五〇年代の成長過程に寄り添っていたはずで、キングは六〇年代を経て、七〇年代に至ったその郊外の行き着いたイメージや没落をふまえ、ホラー小説を書き出したとも考えられる。
しかもキングは佐藤守彦の「アメリカ文化とスティーヴン・キング」(奥沢成樹編『コンプリート・スティーヴン・キング』所収、白夜書房)に引かれている言によれば、「自分のは、ほとんど凡庸な人々むけの素朴な作品で、マクドナルドのビック・マックとフライド・ポテトの大と同じ文学的価値しかない。なにか自分に取り柄があるとしたら、それを知っていることだ」と語っている。これは自らの物語がロードサイドのファストフードと同じ凡庸さに基づき、それゆえにベストセラー作家として商業的に成功したと述べていることになろう。この発言はやはり同書所収のインタビューにおける、自らを「プロットつきのシアーズ通信販売カタログ」、その作品を「大量生産されるスーパー・マーケット・ホラー小説」とよんでいることとも通底している。
しかしそれらもキングの文学のベストセラー化の一面であるにしても、『小説作法』の中に示された「文章は飽くまでも血の滲むような一語一語の積み重ねである」という言葉、及びそのホラーの特質が『エクソシスト』などの先行する作品と異なり、本質的に外から襲ってくるものではなく、郊外それ自体や日常の家族や夫婦が孕んでいる罅(ひび)のようなものが生み出してしまうものによって形成されていることを忘れるべきではないだろう。
それらは第一作の『キャリー』における狂信的母親による異常な家庭環境が少女にもたらす超能力、第二作『呪われた町』における郊外化の果てに生じた限界集落のようなセイラムズ・ロットという町、第三作)『シャイニング』に見られる夫婦関係の破綻と危機が呼び寄せてしまうホテルの悪霊などに表出している。
だがここではキングの第五作目にあたる『デッド・ゾーン』(吉野美恵子訳)を取り上げてみる。それは作品の完成度と五〇年代から始まり、七〇年代末に至り着く物語の流れもさることながら、デイヴィッド・クローネンバーク監督、クリストファー・ウォーケン主演の映画も秀作で、その得たものというよりも失ったものに対する悲しみを想起させる寒色系の映像がひときわ印象に残っていることにもよっている。
 |
 『デッド・ゾーン』BOX版 『デッド・ゾーン』BOX版 |
またさらに近年にアメリカでテレビドラマ化もされ、その映画とは異なるはるかに長い連作をDVDで観ることもでき、こちらも楽しませてもらったからだ。こちらは精神分析的フィクションも含め、エンターテインメント、サイキックストーリーに仕上がり、原作を巧みに膨らまし、生かしているといえよう。
『デッド・ゾーン』の物語の起点は五〇年代に設定されているが、実質的には七〇年代から始まり、七九年に終わっていることを考えると、まさに七〇年代というディケードを描いているともいえる。したがって、それはハルバースタムが提出した『ザ・フィティーズ』に接木された、六〇年代を経て七〇年代へと至るアメリカ社会状況が舞台であることを意味している。
『デッド・ゾーン』の主人公ジョン・スミスの住むクリーヴス・ミルズという町は、次のようなものだ。それは連続殺人が起きるキャッスル・ロックも同様のイメージがあり、そこはまた『クージョ』(永井淳訳)や『スタンド・バイ・ミー』の舞台ともなっている。
クリーヴス・ミルズは、横断信号(午後六時以降は点滅灯にある)のある交差点一つと、二十軒余りの商店と小さなモカシン工場のある本通りが町のほぼすべてだった。メイン州立大学のあるオロノ市周辺の田舎町の多くと同じく、クリーヴス・ミルズも学生が消費するもろもろのものの供給を町の主要産業としていた―ビール、ワイン、ガソリン、ロックンロール・ミュージック、ファースト・フード、麻薬、食糧雑貨類、貸家、映画館。(中略)
大学の教授団と経営陣は大学の学生ともどもクリーヴスを彼らのベッドタウンとして使い、おかげで町は人も羨む税基盤を得た。(中略)町民たちは大学の連中の才走った会話、アカがかった反戦デモ、町政に対する口出しを苦々しく思ったろうが、優雅な教授村と、(中略)アパート群とから毎年はいる現収に対しては、間違ってもノーとは言わなかった。
アメリカの戦後のベビーブームは一九四六年から六四年まで続き、この十九年間に八〇年代のアメリカ人口の三分の一を占める七千七百万人が生れたとされる。キングもその一人であり、このようなアメリカ版団塊の世代とでもいうべきベビーブーマーの出現とパラレルに郊外の隆盛を見たのだが、それは大学も同様で、急増したベビーブーマーに対して多くの大学が新たに開設され、『デッド・ゾーン』に述べられたクリーヴスのようなベッドタウンも、アメリカの郊外の各地に誕生していたにちがいない。もちろんそこにはキングが成長したメイン州の郊外の風景も織りこまれているはずだ。そうしたアメリカならではの戦後的トポスであったゆえに、キング固有のホラーが召喚されることになったのだ。
一九七〇年、時代と社会はベトナム戦争に起因する様々な事件の余波を受けていたが、大学と町は「安全地帯」にして、「いつまでも大人にならずにいられる一種の理想郷」に見えた。ハイスクールの教師ジョン・スミスは大学も同窓で、同僚でもある恋人のセーラとハロウィンに、二十マイル先で開催されているカウンティ・フェアに出かけた。カウンティ・フェアとは「農産物フェア」の訳語もあてられているけれども、フェア会場におけるホットドッグ、揚げたタマネギ、ベーコン、綿あめなどの食物、観覧車のネオン、メリーゴーランド、小型ローラーコースター、射的場、大テントから流れてくるビンゴの数字といった描写、「子供のころのカウンティ・フェアを再体験する」とか、フェアというものは「どれもみんな同じ、それに何年もたってもたいして様変わりしないもの」との思いから想像すると、戦前から続いているアメリカならではの巡回縁日と見なしていいのではないだろうか。
そのように考えてみると、農業フェアを描いた映画『ステート・フェア』が思い出されるが、『デッド・ゾーン』とは異なるものだとわかる。このようなカーニバルを例に取り、SFからホラーへの流れを記せば、レイ・ブラッドベリの『何かが道をやってくる』(創元推理文庫)や『刺青の男』(ハヤカワ文庫)から『デッド・ゾーン』への変容ということになろう。
そのフェアの「運命の車」という屋台のギャンブルで、ジョンはなぜか当たりが予測できて、五百ドルを儲ける。そして彼はホットドッグを食べたことで具合が悪くなったセーラをアパートまで送り、その後交通事故に遭い、四年半にわたる昏睡状態に陥ってしまう。郊外のベッドタウンの近傍で催されていたフェアは、ギャンブルの勝利とセーラの身体の不調を伴って、ジョンの長期に及ぶ昏睡へと導くタイムトンネルのように機能し、戦後的トポスと平穏な日常生活のかたわらにぽっかり開いている陥穽を象徴しているといっていい。大学と町が表面的には安全地帯にして「理想郷」であったことに対し、フェアは悪夢的なカーニバルに他ならなかったのである。レイ・ブラッドベリにとっては幻想へと誘われる魅惑的な存在であったのに。ジョンの母親はいう。「罪と悪の場所だわ」と。
ジョンの昏睡と並行して、ベトナム戦争敗北、ドルショック、ウォーターゲート事件、ニクソン大統領辞任などが続くアメリカの七〇年代前半が過ぎていく。そうした年月の中で、セーラもまた「一種の冥界」にいるようだった。そしてジョンが目覚めたのは七五年になってのことであり、彼は四年半にわたって意識を失っていたことになる。ただ彼は単に覚醒しただけでなく、透視予知能力を身につけて目覚めたのだ。失われた四年半の間に、両親は年老い、母親は狂気へと誘われ、恋人のセーラは他の男と結婚し、すでに子供も生まれていた。それは悲しみに満ちた目覚めに他ならなかった。
キングはそれがジョンの宿命であるかのように覚醒の回路を描写している。
夢を見ているのだろう、と彼は思った。
彼は暗い陰気なところにいた―一種の通路だろうか。天井は高すぎて見えなかった。暗がりに没して見えない。壁は黒ずんだクロム・スチールだった。それが上にいくにつれて広がっている。彼は独りきりだったが、はるか遠くから伝わってくるような声が、彼のもとに流れてきた。聞き覚えのある声、いつかどこかで彼にむかって発せられたことのある言葉。その声は彼をおびえさせた。声が呻いて、彼の子供のころの記憶にある捕らわれた小鳥のように、暗いクロムの谷間にこだまをはねかえらせながら消えていく。(中略)死んでしまった(中略)遠い昔のその小鳥の鳴き声と同じ宿命的なものが、その声にもあった。それは永久にこの場所から逃れられないのだ。
そして彼は生者と死者の世界の間のような荒涼として暗い影に閉ざされた通路を独りで歩いていく。このイメージはクローネンバーグの映画の中でも象徴的なシーンとして組みこまれ、『デッド・ゾーン』そのもののように出現している。
そうして覚醒したジョンは失われたものを確認しながらも、看護婦の自宅の火事や医師の母親の生死の透視から始めて、昏睡中に起きていた連続殺人事件の捜査にも関与していく。ジョンの超能力はアメリカの未来をも予知することになり、彼は図らずも暗殺者となる道をたどっていく。それは目覚める前に見ていたあの通路の行き着く先だったことを明らかにする。キングは『デッド・ゾーン』において、失われたものを代償にして超能力を得てしまったジョンの内的葛藤と苦悩を、悲しみをこめて描き出している。それは郊外に生きる人々の何らかのメタファーのようにも読めるし、大友克洋の『童夢』や岡崎京子の『リバーズ・エッジ』にも引き継がれ、流れこんでいるメランコリーな水脈ではないだろうか。
そのようなキングの、日本における受容を考えてみると、『キャリー』『呪われた町』(永井淳訳、集英社文庫)『シャイニング』はいずれも七〇年代後半に単行本として刊行されたが、いずれも売れ行きはよくなかったようで、しばらく品切、絶版状態にあった。その中でも)『シャイニング』は七八年に翻訳、八〇年代にスタンリー・キューブリックによる映画化もされたけれど、出版社の倒産もあり、八六年文春文庫として復刊となるまで、ずっと入手困難だった。
しかし八〇年代に入り、文庫化され、新作も文庫で出版され始め、『スタンド・バイ・ミー』に代表される映画化と相俟って、キングのホラーは日本でも定着し、日本版ホラー小説へと継承されていったと思われる。その時代における受容の地平を考えると、本連載でも既述してきたように、日本の八〇年代において、郊外消費社会が成立し、東京ディズニーランドも開園し、アメリカと同じ風景に至ったこと、それゆえにキング的ホラーもリアルなものとして受け入れられるベースが築かれていたことにもよっているはずだ。日本版ホラー小説に関しては後述するつもりである。
| ◆過去の「混住社会論」の記事 |
| 「混住社会論」17 岡崎京子『リバーズ・エッジ』(宝島社、一九九四年) |
| 「混住社会論」16 菊地史彦『「幸せ」の戦後史』(トランスビュー、二〇一三年) |
| 「混住社会論」15 大友克洋『童夢』(双葉社、一九八三年)) |
| 「混住社会論」14 宇能鴻一郎『肉の壁』(光文社、一九六八年)と豊川善次「サーチライト」(一九五六年) |
| 「混住社会論」13 城山三郎『外食王の飢え』(講談社、一九八二年) |
| 「混住社会論」12 村上龍『テニスボーイの憂鬱』(集英社、一九八五年) |
| 「混住社会論」11 小泉和子・高薮昭・内田青蔵『占領軍住宅の記録』(住まいの図書館出版局、一九九九年) |
| 「混住社会論」10 ウラジーミル・ナボコフ『ロリータ』(河出書房新社、一九五九年) |
| 「混住社会論」9 レイモンド・チャンドラー『長いお別れ』(早川書房、一九五八年) |
| 「混住社会論」8 デイヴィッド・ハルバースタム『ザ・フィフティーズ』(新潮社、一九九七年) |
| 「混住社会論」7 北井一夫『村へ』(淡交社、一九八〇年)と『フナバシストーリー』(六興出版、一九八九年) |
| 「混住社会論」6 大江健三郎『万延元年のフットボール』(講談社、一九六七年) |
| 「混住社会論」5 大江健三郎『飼育』(文藝春秋、一九五八年) |
| 「混住社会論」4 山田詠美『ベッドタイムアイズ』(河出書房新社、一九八五年) |
| 「混住社会論」3 桐野夏生『OUT』後編(講談社、一九九七年) |
| 「混住社会論」2 桐野夏生『OUT』前編(講談社、一九九七年) |
| 「混住社会論」1 序 |