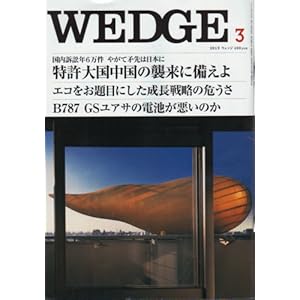出版状況クロニクル60(2013年4月1日〜4月30日)
イオンがダイエーを子会社化すると発表された。ダイエーが創業以来、初の経営赤字に陥ったのは1998年で、2001年創業者の中内㓛が退任し、02年産業再生法の適用認定を受け、04年産業再生法の支援、07年丸紅、イオンとの業務提携を経て、今回の事態を迎えたのである。60年代において、消費社会を出現させる過程で、最も過激なアジテーターにして革命家であった中内㓛のダイエーは、もはや消滅したと見なせるだろう。
なぜこのことにふれたかというと、同じように98年から露出してきた出版業界の危機は、このようなダイエーの失墜とパラレルで、しかも当時の出版業界の売上は、ダイエーの有利子負債の2兆6000億円と同様だったからだ。ダイエーグループの負債と出版業界全体の売上が同じだと笑い話のように語られていたのが十数年前のことだった。
そうしてダイエーは実質的に終焉を迎えてしまったことになる。そのかたわらで、今度はパナソニック、ソニー、シャープの赤字決算が発表され、その赤字合計は1兆6000億円だと伝えられている。これもまた笑い話のようになってしまうが、13年度の出版業界の売上もほとんど変わらないものになるだろう。
家電業界の危機も深刻で、ダイエーのように消滅するところも出てくるのではないかと伝えられている。出版業界に至っては、本クロニクルの読者であれば、あらためていうまでもないことだが、さらに加速してバニシングポイントへと向かっている。
1.2012年の雑誌の売上状況だが、そのうちの月刊誌、週刊誌、コミックについては本クロニクル59でふれたので、今月はムックを取り上げておこう。販売金額は1045億円で、前年比0.6%減。
*ムック扱いの廉価軽装版、コミックスを除く
■ムック発行、販売データ 新刊点数 平均価格 販売金額 返品率 年 (点) 前年比 (円) (億円) 前年比 (%) 前年増減 1999 6,599 11.5% 915 1,320 1.9% 43.5 ▲0.5% 2000 7,175 8.7% 905 1,324 0.3% 41.2 2.3% 2001 7,627 6.3% 931 1,320 ▲0.3% 39.8 ▲1.4% 2002 7,537 ▲1.2% 932 1,260 ▲4.5% 39.5 ▲0.3% 2003 7,990 6.0% 919 1,232 ▲2.2% 41.5 2.0% 2004 7,789 ▲2.5% 906 1,212 ▲1.6% 42.3 0.8% 2005 7,859 0.9% 931 1,164 ▲4.0% 44.0 1.7% 2006 7,884 0.3% 929 1,093 ▲6.1% 45.0 1.0% 2007 8,066 2.3% 920 1,046 ▲4.3% 46.1 1.1% 2008 8,337 3.4% 923 1,062 1.5% 46.0 ▲0.1% 2009 8,511 2.1% 926 1,091 2.7% 45.8 ▲0.2% 2010 8,762 2.9% 923 1,098 0.6% 45.4 ▲0.4% 2011 8,751 ▲0.1% 934 1,051 ▲4.3% 46.0 0.6% 2012 9,067 3.6% 913 1,045 ▲0.6% 46.8 0.8%
[このムックについて、繰り返しになるにしても、定義づけておく。なぜならば、これもコミックと同様に、日本特有の出版物と見なしてもいいからだ。
ムックは返品期限のある月刊誌や週刊誌といった定期誌と異なる雑誌であり、1970年代における平凡社の「別冊太陽」の創刊などから始まったとされる。したがって雑誌は月刊誌、週刊誌、コミックに加え、ムックの4種から成立している。
このムックが月刊誌と週刊誌の落ちこみをカバーするように、2000年以後増加し、ついに12年は9000点を超えたことになる。しかし販売部数こそ微増したものの、販売金額は一貫して減少し、ムックも明らかに衰退に向かっている。
このことを示すように、近年の返品率は46%前後に高止まりし、雑誌平均や書籍の37%をはるかに超え、送品や返品流通コストから考えれば、赤字になっているのではないかとも考えられる。それにこれだけの点数が出され、現在の大型店に占めるシェアが高いとすれば、書店市場の縮小につれて、ムックの返品率はさらに高まり、50%を超えてしまう事態となるかもしれない。
そうなれば、書籍以上に出版流通の根幹を揺さぶるであろうし、それはすでに現実化しているとも思われる]
2.続けて同じく12年の文庫の売上状況にもふれておく。販売金額は1326億円で、前年比0.5%増。
■文庫マーケットの推移 年 新刊点数 推定販売金額 返品率 冊 (増減率) 億円 (増減率) 1995 4,739 2.6% 1,396 ▲4.0% 36.5% 1996 4,718 ▲0.4% 1,355 ▲2.9% 34.7% 1997 5,057 7.2% 1,359 0.3% 39.2% 1998 5,337 5.5% 1,369 0.8% 41.2% 1999 5,461 2.3% 1,355 ▲1.0% 43.4% 2000 6,095 11.6% 1,327 ▲2.0% 43.4% 2001 6,241 2.4% 1,270 ▲4.3% 41.8% 2002 6,155 ▲1.4% 1,293 1.8% 40.4% 2003 6,373 3.5% 1,281 ▲0.9% 40.3% 2004 6,741 5.8% 1,313 2.5% 39.3% 2005 6,776 0.5% 1,339 2.0% 40.3% 2006 7,025 3.7% 1,416 5.8% 39.1% 2007 7,320 4.2% 1,371 ▲3.2% 40.5% 2008 7,809 6.7% 1,359 ▲0.9% 41.9% 2009 8,143 4.3% 1,322 ▲2.7% 42.3% 2010 7,869 ▲3.4% 1,309 ▲1.0% 40.0% 2011 8,010 1.8% 1,319 0.8% 37.5% 2012 8,452 5.5% 1,326 0.5% 38.1%
[村上春樹『1Q84』やライトノベルの三上延「ビブリア古書堂の事件手帖」」シリーズなどの寄与もあり、前年に続いて販売金額は微増となっている。しかし新刊点数の大幅な増加は、初版部数の減少を告げているし、その平均価格4円アップの632円、前年比0.6%増も同様であろう。
それからムック以上に新刊点数が増加していて、1998年に比べ、2012年は3000点増となっている。しかし販売部数は98年の2億5千万冊に対して、12年は2億1千万冊で、こちらもムック同様に、販売部数の減少を新刊点数の増加で補っているとわかる。またそれは既刊が売れず、新刊依存へと文庫市場が推移していることを示す。
いうまでもなく、月刊誌、週刊誌が最新号しか売れないように、ムックも文庫も、新刊しか売れない書店市場の現在の状況が浮かび上がってくる。それは各分野の単行本も同じだと思われる。かつての書籍の売上は、出版社にしても書店にしても既刊本によって支えられていたことを考えると、出版業界そのものが過剰消費社会の中に組みこまれてしまったことを痛感せざるを得ない。それでいてそのバブルの終わりに立ち会っているような気にもさせられる。
結局のところ、現在の日本の出版業界は、月刊誌、週刊誌、コミック、ムックからなる雑誌売上、それに同じく雑誌のパターンで刊行される文庫の売上がシェアの半分以上を占める。ちなみに12年のそれらの合計は1兆711億円となり、出版物販売金額1兆7398億円の62%に及ぶ。
これに新書も加えれば、この十数年、低定価の雑誌と低定価本によるシェアが、書店の大型化と相まって、ひたすら拡大してきたことを意味しているし、それがまた書店市場を疲弊させてきた原因ともなる。
しかもこの出版業界の現実が限界にきていることは誰の目にも明らかだろう]
3.楽天の三木谷浩史社長が出版社向け事業の戦略説明会を開き、2016年までに楽天の電子書籍事業を500億円、20年には5000億円の売上高をめざすと発表。20年には国内電子書籍市場は1兆円に達するので、その50%のシェアを狙うとも発言。
その三木谷の発言に対し、講談社の野間省伸社長が、電子書籍の売上は拡大し、楽天はその大きな役割を担っているので、5000億円の売上を期待すると語っている。
[アマゾンに対抗するリップサービスも含んでいるのだろうが、これらの数字は何の根拠もない出鱈目な発言だと思う。このような裏づけのない数字が、何も出版業界のことを理解していない三木谷によって出され、それに出版社を代表して野間が追随するといった光景、それに批判もなく従う大手出版社やマスコミ報道こそが、電子書籍問題の倒錯的内実を露呈させている。
もし仮に20年に電子書籍が5000億円市場になったとすれば、それは1と2で示した売上シェアの問題、及び日本の出版業界の欧米と異なる特殊性から考え、低価格雑誌、低価格本も必然的に電子書籍市場へと移行することになり、出版社、取次、書店からなる出版業界は消滅してしまうだろう。
そしてさらに問題になるのは、30兆円を超えると思われる既刊在庫書籍で、これらはもはや需要もなくなり、断裁処分を余儀なくされるだろう。つまり講談社に例を挙げれば、既刊のコミック、文庫、新書の大半が不良在庫となるのだ。
現在の出版業界のめざすべきは、既刊本の時限再販しかないのだが、三木谷の発言に従えば、それどころか、既刊本の大半が読まれなくなる事態を迎えてしまうのである。そのことに大手出版社がまったく無自覚であることを、野間の発言は証明している。思わず「売家と電子書籍で書く三代目」なる一句が浮かんだ。
なおこの説明会に関して、Business Journalが碇 泰三による「楽天がぶち上げる『打倒アマゾン』に出版社は眉唾…kobo事業説明会に出版界から非難轟々」というレポートを掲載している。このような電子書籍市場の売上高に関する思いこみと誤解は、本クロニクルで繰り返し言及してきたが、出版デジタル機構が17年に100万点、2000億円の売上をめざすと発表したことから始まっている。出版業界の歴史と構造、現状分析に無知なままで、このような何の裏づけもないスキームを立ち上げたJPOの責任はあまりにも重いと考えるしかない]
4.本屋大賞受賞の百田尚樹『海賊と呼ばれた男』(上下)が一気に100万部に到達、村上春樹の新作『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』もたちまち100万部を突破。
[1から3の出版状況を背景にして、このふたつのミリオンセラーが生まれたことになる。
このような光景は「ハリー・ポッター」から顕著になり、近年でも『KAGEROU』などでも見たし、もはや出版業界においても恒例の行事のようなものと化している。だがそうした光景の背後で、出版業界に何が起きていたのかは本クロニクルで見てきたとおりだ。それだけでなく、そのミリオンセラーの末路も知っている。とりわけ「ハリー・ポッター」シリーズも『KAGEROU』もブックオフの棚にあふれ、今でも売れ残っている。
かつて寺山修司は「ベストセラーの読者になるよりも、一通の手紙の読者になることの方が、ずっとしあわせなのだ」といった。とすれば、現在のベストセラーの読者たちは「しあわせ」ではないからこそ、それらの本を読んでいるともいえる。またそうしたミリオンセラー化は、作者にとっても作品にとっても「しあわせ」ではないことを告げているのではないだろうか]
5.このような出版状況下においても、売上を伸ばしている出版社があり、『新文化』(4/11)が一面で�斈出版社を特集している。
�斈出版社はバイク、自転車、登山、サーフィン、旅行などの19の雑誌とムックの他に、書籍やDVDも刊行し、12年は477点の新刊を出している。売上高推移は07年68億円、12年83億円と、25年連続増収となっている。
その出版戦略は大部数の雑誌よりも、一定の部数が見こめる専門的雑誌を持つべきだというもので、そのコンセプトによって、先に挙げた分野の雑誌が次々と立ち上げられていったことになる。
[確かに近年�斈出版社の雑誌やムックは書店のどの雑誌分野でも目立ち、またブックオフでもそれらのバックナンバーがよく売られているのを見かける。現在の若い読者の趣味とニーズに見合った「モノとコトマガジン」の出版社の印象があった。また逆にいえば、郊外店から始まり、TSUTAYAなどの複合店が開発した読者層にフィットし、成長してきたことになるのだろう。25年連続増収はまさにその証明となる。
しかしそれでも雑誌群は他社と同様に前年を下回り、代わりに生活実用ムックと書籍が大きく伸びているという。
このような版元に口をはさむ資格はないのだが、あえて私見を述べれば、21世紀のマガジンハウスになれるかどうか、この数年が過渡期、もしくは端境期のようにも見受けられる]
6.大阪屋は来期の売上高減少に対応するために、東京支社の売却を決め、早期退職者制度による特別募集で、60人の従業員を削減。
7.日販は企業年金制度を廃止。04年に厚生年金基金の代行業務を返上した際に、確定給付企業年金を導入したが、これは企業保証型の企業年金で、リーマンショック以後、予定利回りが成立せず、運用損失が増え、利回りの回復も見こめないことから、労組との合意で廃止に踏みきった。
8.栗田出版販売とワンダーコーポレーションが、合弁会社ニューウェーブディストリビューションを設立し、大型複合店を開店する。5月に開店するワンダーグー川越店が3世代で楽しめるライフスタイル提案型店舗のモデル店とされる。ワンダーコーポレーションのグループ規模は売上高980億円、330店舗。
[6から8は取次の動向である。6と7はリストラの一環、8はミニMPDのような業態のように思われるが、複合店の行方自体が不透明な時期ゆえに、どのような道筋をたどるのだろうか]
9.6に見られるリストラとは逆の、13年度「出版業界、主要社の新入社員数」調査が『文化通信』(4/15)に掲載されているので、参考までに示しておく。
これは出版社32社、取次8社、書店9社で、新卒は311人、中途採用(契約社員含む)59人となっている。新卒の内訳を示せば、出版社171人、取次102人、書店38人でということなる。
ちなみに新卒の推移を追うと、04年382人、05年252人、06年494人、07年475人、08年601人、09年420人、10年403人、11年254人、12年256人である。
[見てわかるように、新卒採用は08年がピークで、この3年間は半分以下になっているとわかる。12年以前の出版社、取次、書店の内訳は確認していないが、いずれにしても、出版社、取次、書店の危機と余裕のなさが透けて見えるように思われる。
13年度の出版社だけをみても、講談社と集英社が各17人、ハースト婦人画報社31人、学研HD19人、ぴあ12人の5社で96人と3分の1近くを占め、その他は数人かゼロで、これが大手出版社の新入社員状況なのだ。
それゆえに中小出版社、取次、書店のさらなる余裕のない状態が想像できるだろう。はっきりいって、出版業界は後の人材を育成することができなくなっているというしかない]
10.小出版社95社が会員である日本出版者協議会会長で、緑風出版の高須次郎が『出版ニュース』(4/上)に、「どうなる出版者の権利と再販制度」という一文を寄せている。これはアマゾンの問題と経団連の電子出版権案への要望というふたつを主眼としているが、ここでは前者にしぼり、それを要約してみる。
出版協はアマゾンジャパン株式会社(以下アマゾン)の大学生を対象とする10%ポイント還元特典に対し、再販制に違反する値引き行為であるので、中止を求め、アマゾンの価格表示についても、再販対象書籍には「定価」の表示を求め、実際にアマゾンに申し入れを行なった。こちらも後者については省略する。
それに対し、アマゾンは申入記載の事項に関して、回答する立場にないとの返事だったので、出版協は取引取次の日販、大阪屋に再販契約順守指導を申し入れた。
すると日販の回答は、Amazon. comと再販契約を締結しているが、業務はアマゾンに委任され、同じ契約を適用すると合意しているので、アマゾンに10%ポイント還元について、再販契約に抵触する指摘を通知し、協議したが、問題解決は困難だというものだった。
一方で大阪屋の回答は、アマゾンと守秘義務契約を結んでいるので、内容に関してはふれられないが、出版社とその再販契約を遵守するかたちで契約を結んでいる。それゆえにアマゾンが違反した場合、個々の出版社の再販違反認定や出荷停止指示を受け、出荷停止は可能だし、それに従う。ただ再販違反の認定は弊社ができるものではない。アマゾンからは値引きではなく、景品のひとつだとの見解が戻ってきた。
出版協としては、日販に比べて、大阪屋は踏み込んだ回答と認めている。しかしAmazon. comの行為は明らかなる再販違反の値引きで、出版社側に求められているのは、再販契約の忠実な履行の要請であり、大手出版社の奮起も求めたい。そして出版協は公取委に対して、アマゾンのサービスに関する申し入れ、調査を求め、アマゾンへの警告、出荷停止を含め、取り組んでいくとしている。
[この問題に関して、出版協はアマゾン小委員会と出版者権利小委員会を設置し、先に挙げたことも視野に入れ、本格的に取り組んでいくようだ。
出版協は前身の流対協時代の公取委への消費税定価訴訟、グーグル問題への取り組みに続く、第3の問題とするつもりでいるのだろう。これに関しては『再販/グーグル問題と流対協』を参照されたい。
本クロニクル56でも既述していることだが、私と高須は再販制に関する評価を異にしているので、先走ったコメントは控え、まずはその推移を見守ることにする]
11.これは図書館問題につながるし、ほとんど報道もされていないと思われるので、挙げておく。
それは実質的にJR東海が刊行している月刊誌『WEDGE』3月号の回収事件である。
[この一年ほど、取引先から『WEDGE』を恵贈されているのだが、3月号が二度送られてきて、編集内容の一部に数字等の誤りがあり、刷り直したとのコメントが付されていた。
中身を確かめると、最初にあった「公共事業増で甦った自民党建設族」なる「WEDGE Report」4ページが消えていた。これは政権を奪還した自民党の経済政策からの補正、本予算9.1兆円の公共事業大幅な増加で、自民党の建設族によるバラマキ復活の懸念をレポートしたものだ。
この回収事件を『選択』4月号が「野党時代の『復讐』に燃える安倍」という記事の中でふれ、JR東海の雑誌ゆえに刷り直しを迫られた真相を伝えている。
この『WEDGE』は東海道新幹線のグリーン車の背もたれポケットに1冊ずつ差し込まれている雑誌らしいが、実は公共図書館でも定期購入されているのか、2館ほどでそれを見ている。
とすれば、図書館で、この3月号の2冊の処置はどのようになされたのであろうか。もし最初のものを求められた場合、どのように対応することになったのだろうか。最初にあったレポートはほとんど目にふれることなく、回収されてしまったのだろうか。
ちなみにCCCの武雄市図書館だが、マスコミが大きく取り上げ、地元の佐賀新聞は1ページ特集したこともあって、4月1日の開館日入場者は5517人に達したという]
12.アメリカにいる息子から、オープンしたばかりのブックオフのレイクウッドセンターモール店レポートが送られてきたので、それを写真も含め、コメント部分に掲載する。それゆえにコメントは付さない。
これは本クロニクル58でふれたアメリカブックオフの続報として読まれれば幸いである。
[レイクウッドにあたらしくオープンしたブックオフのニュースは、日本語のフリーペーパーに「全米最大規模の新店舗をオープン」」というタイトルで取り上げられていた。また同じフリーペーパーの別の号で「仕事人のヨコガオ」というコラムがあり、そこにブックオフの副店長のインタビューが掲載されていた。
レイクウッドはたしかに今まで行ったなかでいちばん大きい店舗だった。まだオープンしたばかりで客層は定まっていないように見えたが、モールの雰囲気を見るかぎり、年齢層はやや高めだと思う。これはトーランスのブックオフには10代と思われる若者がたくさんいた光景と対照的である。
どちらのモールでも、これでもかというくらいにブックオフの立て看板や垂れ幕の広告があちこちに見られた。立て看板や垂れ幕の広告それ自体はべつに珍しくもないが、ここまでモールのいたるところにあるのはかなり珍しいと思う。すくなくとも、両モールで、ブックオフと同じくらいの数の看板広告を出している店舗はない。
前回のブックオフUSAの女性経営者へのインタビューにあったとおり、アメリカブックオフの主力がDVDやゲームというのは、店内の棚配置からもよく見てとれる。メインエントランスのすぐ向うにあるのはDVDとゲームソフトの棚だ(ウェストミンスターとトーランスの場合)。レイクウッドはやや変則的だが(入口が2つあり、ひとつはモールの通路から入れる屋内のもの、もうひとつは屋外のもの)、屋外からの入口のそばに映像ソフト、屋内からのそばには書籍という配置で、レジカウンターが映像ソフトがわにあったので、やはりそちらがメインエントランス扱いなのだろう。
行ったのが土曜日ということもあり、どちらのブックオフもかなりにぎわっていた。ここまで人の入りが見込めるなら、なるほどアメリカ人相手の商売を考えてみたくなるだろうと、というほどに。客をざっと見渡したがきり、日本人はほとんどいない。というか、ウェストミンスター、トーランス、レイクウッド、どのモールも完全にアメリカ人をターゲットにしたもので、日本人自体がそもそもいない。
商品をどうやって調達しているのかやや謎ではある。客からの買い取りだけで可能なのか。新店舗のためにあらたに買い取りをかけたのか、それとも買い取った在庫がずいぶんたまってきたから、出店計画が持ち上がったのか。ともあれ、クラシックCDの棚に日本語のCDがあったのが不思議といえば不思議だ]
13.日本編集者学会のトランスビュー発売『EDITORSHIP』Vol.2が出された。「書物の宇宙、編集者という磁場」特集で、小池三子男の「河出書房風雲録・抄」、大槻慎二の「福武書店のころ」が興味深く、教えられることが多々あった。
[河出書房もまた多くの出版社と同様に、全出版目録が編まれていないこと、また二度に及ぶ倒産のために、創業者一族なども退いたこともあって、その全貌はいまだに描かれていない。それゆえに一部であるにしても、小池の回想は貴重だと思われる。
大槻の回想も同様で、福武書店における出版の実相、それが現在の出版社の姿で先駆けであったことを垣間見ることができる。私は以前に福武書店の出版物にふれ、その「『未だ王化に染はず』の真の作者は誰か」(『古本探究』所収)という一文を書いている。これは私以外まったくといっていいほど論じられていない作品であるが、3・11以後の状況と天皇制の行方を考える意味でも、あらためて読まれてほしい。まだ古書市場で安く入手できるはずなので、何人かの読者が生まれることを願う]

14.同じく編集者の回想だが、本クロニクルでもすでに紹介した『編集者=小川哲生の本』に続いて、小川哲生の『生涯一編集者』(言視舎)が出された。
[小川は大和書房から始めて、JICC出版局(宝島社)、洋泉社と40年間の編集者生活の間で、企画編集に携わったものは400冊に及ぶ。そして現在でもフリー編集者として、現役であり続けている。全書と同書を読めば、小川が送り出した本と著者たちの広大な宇宙が浮かび上がる仕掛けになっている。
13の小池、大槻文に続けて小川の本を読むと、出版業界の失われた15年が次代の編集者を育ててこなかったのではないかとの懸念に捉われる。それは次代の著者や作者も含めて、トータルな出版業界の人材ということにもつながっていくからだ]
15.ついに待望の一冊が出た。それは山本芳明の『カネと文学』(新潮選書)である。
[サブタイトルにあるように、これは初めてといっていい「日本近代文学の経済史」に他ならない。近代文学研究がようやく現在に追いついたのである。近代文学史はほとんど語っていないが、近代文学は出版資本との攻防を通じて成立したのであり、それは誕生から四十年を経た昭和初期円本時代に至って、初めて文士たちはカネと名誉を得て、家を作り、文字通り作家となったのだ。
白樺派の武者小路実篤は円本成金となり、病の母を慰めるために、これまで見たこともない巨額の印税をすべて一円札に両替し、枕元に積み上げたという。それ以前は大半が子は飢えて亡き、妻は病に倒れ、一家の生計成り立たずというのが文士の現実であった。
しかし翻って現在を考えれば、出版危機は作家や著者たちをそれ以前の世界へと連れ戻しているかのように見える。出版危機こそがカネと出版のみならず、「カネと文学」をよりあからさまに露呈することになるのだ。それゆえに近代文学研究者のみならず、作家や著者たちも必読の一冊として推奨する次第だ]
16.ようやく次の「出版人に聞く」シリーズのインタビューを公表できる。
それは濡木痴夢男『「奇譚クラブ」から「裏窓」へ』(仮題)で、彼は『奇譚クラブ』の書き手にして、『裏窓』編集長でもあった。入念に準備し、5月半ば予定のインタビューにのぞむつもりでいる。
なお古田一晴『名古屋とちくさ正文館』は出版社の事情で遅れている。もう少しお待ちいただきたい。
《既刊の「出版人に聞く」シリーズ》
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |