
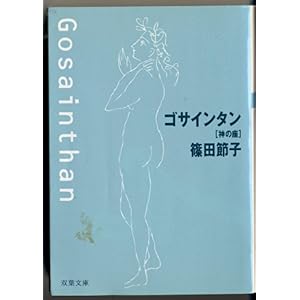 (双葉文庫)
(双葉文庫)
折口信夫が「国文学の発生(第三稿)」(、『古代研究(国文学篇所収)』所収、『折口信夫全集』第一巻、中公文庫)でいうところの神としての「まれびと」が、古代ならぬ現代の郊外に、しかも混住社会の一員となって出現することがあるのだろうか。それが篠田節子の『ゴサインタン』(以下この表記とする)を貫いているテーマに他ならない。
 (角川文庫)
(角川文庫)  (中公文庫)
(中公文庫)ゴサインタンとは山の名前で、ネパール語で神の住むところをさすが、裏側のチベットではシシャパンマ、「家畜が死に絶え、麦も枯れる地」の意味となり、「神の座」は両義性を帯びていることになろう。これは物語の後半になってようやく明かされる。
『ゴサインタン』の舞台となるのは、東京の神奈川県境に近いH市黒沼田地区である。そこでの名家結木家は江戸時代からの名主で、戦後の農地改革で土地の大半を失ったけれど、まだ一町歩の畑と二十軒の借家がある土地と山林が残っていた。バブルが弾けたとはいえ、年々宅地化が進む地域ゆえに、その土地を含めた結木家の資産は莫大なものだった。その跡取り息子の輝和は四十近くになるが、農業を営んでいることに加え、資産と旧家の重みが仇となって、嫁の来てがなく、独身のままだった。しかもかつて市の実力者だった父は脳血栓で倒れ、半身不随となり、母はその看護に明け暮れていた。
黒沼田の農業の歴史は武蔵野の赤土を耕し、畑作中心で発展してきたが、十数年前から都市化が進む中で変わり、各家ごとに農地の広さも家族構成も異なってきていた。昔ながらの米中心の専業農家、息子が勤めている兼業農家、年寄り二人だけで土地を守り、畑に出ている家、農地を売るつもりで待機している家、節税のために農地に作物らしきものを植えている家といった具合だ。だが一方では市場出荷用に野菜を一品大量生産、もしくは少量多品種生産したり、マスクメロンといった新たな作物の栽培を試みたり、住民や大手スーパーへの直販に挑む若い農家の跡取りたちも出現していた。
しかし結木家は旧来のままの畑作を続け、農業収入よりも借家や駐車場から入る不動産収入がはるかに大きい「典型的な第二種兼業農家」であり、家名の神通力も失われつつあった。それは地区の中にニュータウンができ、都心から人々が移り住み、農地にもモザイク状に新興住宅地が出現し、住民の意識が変わり、郊外と混住社会が形成され始めたこととパラレルだった。
そうした中で、数限りなく見合いを重ねてきた輝和のもとに、新たな外国人との見合い話が持ちこまれてきたのである。しかもそれは聞いたことのあるフィリピン人や中国人ではなく、ネパール人とだった。そのことを問う輝和に対し、仲介者はいう。
「陽気でかいがいしいなんて、ありゃフィリピンパブの顔だぜ。嫁さんにしてびっくり、掃除、洗濯、料理なんて、はなからする気はないし、ウインクひとつでケツの毛まで抜かれ、丸裸にされた男の話なんかけっこうあるしな。大陸の女はもっとひどい。共産主義下の男女平等のお国柄だから、男が台所に立つなんか、へとも思っちゃいない。高い金使って里帰りさせたって、お願いしますと頭下げるどころか、当然の権利だという顔をして、土産まで要求してくるそうだ。その点、ネパールはまだスレていないらしい。それに……」
それは集団見合いで、今年で四十になる六人の男たちと九人のネパール人女性が一室に集められる。彼女たちはネパールから研修目的で日本にきて、大月市内の電機部品工場で働いているのである。ナンバーをふられた彼女たちは緊張のあまり、「恐怖に近い硬い表情」をしていたが、その中に一人だけ、日本人に近い黄色い肌をした小柄な女がいた。あらためて、見ると、化粧法のせいか輝和の回りの日本人よりも日本的な、なつかしい顔立ちをしていた。脂肪の乗った上瞼は切れ長で、丸い頬や小さな口元は、慎ましやかな印象を与える。怯えたような、憂鬱な表情さえしていなければ、それなりに愛嬌のある顔かもしれない。
通訳によれば、彼女の名前はカルバナ・タミで、ネパールのカトマンズからきたという。しかし通訳が伝えられたのはそれだけだった。一応ネパール語は公用語とされているが、ネパールは多民族国家で、主としてインド系とチベット系の人々で構成されている。だがヒマラヤ山地に住む人々、インドに近い平原に住む人々、その中間の山腹や盆地に住む人々は、各民族や部族によって、言語や宗教や生活習慣もまったく異なるのだ。カルバナはネパールの山奥の未開の村からきたのかもしれない。
それでも輝和は、彼女の出身地や民族が何であろうと、一日も早く日本語を話せるようになり、日本の生活習慣になじむことが肝心だと考える。それにふさわしい女として、カルバナは輝和のみならず、彼の母親によっても選ばれたのだ。かくして輝和はカルバナに淑子という名前をつけた。それは中学三年生の時に憧れていたクラスメートの名前で、それが古風な感じを与える異国の女性に似合うと思ったからだ。
淑子の結木家への訪問と医者による健康診断を経て、輝和と淑子は現地で挙式するためにネパールへと旅立った。外国人との結婚には外国人登録証やパスポートの墓に、現地政府の発行する婚姻用件具備証明書が必要で、そのために現地で挙式し、婚姻証明を日本の役所窓口に提出することが最も簡略だったからだ。
それらの諸費用は三百八十万円で、見合い料二十万円を合計すれば、四百万円ということになる。だがそうした費用は四十歳になる農家の跡取り息子の結婚と結木家存続のための必要経費と見なせば、必ずしも高い金額ではなかった。日本人の嫁をしかるべきところからもらったら、結納金や結婚式などの費用はもっとかかるからだ。
輝和の側の結婚に至る事情は判明していたけれど、カルバナのそれは明らかになっていない。結婚式に彼女の両親は姿を見せない。それは山岳部族の村に住んでいて、山道の吊り橋が切れてしまい、川が渡れなくなったからだと説明される。カルバナは何者なのか。だが外見による判断、それに勝手な名前の命名によるネパール人から日本人への同化がこの結婚の内実であることに変わりはない。実際に彼女は「日本人に似ている」し、すでに「ヤマトナデシコ」扱いされているし、輝和にも「古風な日本の花嫁」のように見え、彼の母親もいう。「これからちゃんとした日本人として生まれ変わって、結木淑子としての人生を生きていってくれればいいのよ」と。
そうしてネパールから戻り、結婚生活が始まった。しかし淑子は母親の懸命の教育にもかかわらず、日本語も家事も上達しなかったが、彼女がきてから不思議なことが起き始め、彼女の世話する畑のかぶの根瘤病が消え、出荷できるようになったこと、死んだ愛猫が毎晩現われ、それに淑子が話かけると、成仏したらしい様子を見せたことなどだった。しかし突然彼女は失踪し、かなり離れた飯能で発見される。どうしてだと問う輝和に淑子は、「私、山、行く」と答えた。「私は山に行こうとしました」という意味だろうと彼は解釈した。
だがその後、淑子はシャーマンのような発作を起こし、異民族の意味不明の言葉を発し、密教の忿怒仏の顔になっていた。家全体が揺れ、地震が起きたようで、ブレーカーが飛び、家は闇に閉ざされた。そのようなことがあってからしばらくして、父親が「よしよし(中略)もうおやすみ、ご苦労さんだったね。もういいのよ、さい、おやすみ」という淑子の明瞭な発音の日本語に包まれ、往生を遂げる。
そして続けて母親もクモ幕下出血で死ぬ。その葬式の席で、淑子は日本語でいう。
「おまえたちは、私の子供である。私は、おまえたちを救うために、ここに降りてきた。このような神の力をさずかるために、しばらく天空に行く、子供たちよ。どうか、私が帰ってくるまで、行いを正しくして待っていなさい。(後略)」
そして彼女は香典を貧しき者へと施し、喪服のまま姿を消してしまう。しばらくして同じ姿で再び現われた淑子は、眼球がついているような丸く白い石を打ち鳴らし、どこにいっていたのだとの問いに、やはり「山に行きます」と答えた。その山がネパール人のゴサイタンであったと後にわかる。それから超能力発揮し、奇跡を示す淑子を神様と敬う信者たちが結木家を訪れ始め、輝和は「拝み屋の大将」のような立場になっていく。まだ物語は半ばほどであるけれども、『ゴサインタン』における郊外、混住社会、神としての「まれびと」の出現までを追ってみた。
このようにして、淑子を中心とする新興宗教とコミューン的な共同体が立ち上げられていくのだが、それ以後は本連載のテーマから逸脱していくので、ここで物語の追跡を止める。
 (文春文庫)
(文春文庫)
なお最初に記さなかったけれど、篠田の『ゴサインタン』は、『小説推理』の一九九五年十一月号から九六年二月号にかけて連載されたもので、九五年に起きた阪神・淡路大震災とオウム真理教事件をふまえて書かれたと見なしていいだろうし、それらがこの物語に特有な陰影とゆらぎを与えているように思える。それはたどれなかった後半の展開に投影されているのではないだろうか。その展開を確かめたいのであれば、ぜひ自ら読んでほしいと思う。
それから『ゴサインタン』を読みながら、常に念頭にあったのはパゾリーニの『テオレマ』である。一九六八年に公開されたこの映画は、ミラノ郊外の工場経営者の、一見して平和な大邸宅、夫婦、息子と娘、女中からなる家庭が舞台となる。そこにある日「明日、着く」という、発信人の名前のない電報が届く。そしてテレンス・スタンプが演じる、見知らぬ美貌の青年が現われる。彼はあたかも家族の一員のようにふるまい、この大邸宅に居ついてしまう。するとこの家の全員がおかしくなり始める。青年は女中、息子、妻、夫、娘の順に肉体関係を持ったところで、また電報が届き、青年は「明日、出発する」という。彼が去ると、家族はその不在の空虚さに耐えきれず、拒食症、抽象画への没頭、色情狂的行動、すべてを放棄し全裸での荒野への歩行と、様々な狂気への道をたどり始める。だがただ一人、女中だけは田舎に帰って断食を始め、ついには家の屋根の上に昇天するという奇跡を実現するのだ。彼女だけは青年と性的関係を結んだことで、郊外から村へと回帰し、聖女へと変貌したと解釈することもできよう。
それに対し、カルバナはネパールの村から日本の郊外に到着し、四十近い農家の跡取り息子との結婚を通じて、淑子として神へと至ったと考えられる。しかし彼女もネパールへと戻り、それを輝和が追いかけ、結末において新たなる二人の生活が夢想されている。このような結末もまた、九五年におけるふたつの大事件に遭遇した後でのひとつの希望のように思われる。
なお『テオレマ』のシナリオはキネマ旬報社の『世界の映画作家』1の『ゴダール、パゾリーニ』に田之倉稔訳、「物語+シナリオ」は『テオレマ』(講談社)として米川良夫訳がある。先に挙げた『旧約聖書』の一節は『テオレマ』の最初のナレーション、及び米川訳のエピグラムでもある。
