20年5月の書籍雑誌推定販売金額は770億円で、前年比1.9%増。
書籍は423億円で、同9.1%増。
雑誌は346億円で、同5.7%減。
その内訳は月刊誌が286億円で、同1.5%減、週刊誌は59億円で、同22.0%減。
返品率は書籍が36.5%、雑誌は46.2%で、月刊誌は46.6%、週刊誌は44.0%。
新型コロナウイルスの影響下において、奇妙なプラスというしかないが、休業書店が多く、返品が激減したことによっている。だから6月以後の返品が恐ろしいということになる。
このデータに象徴されるように、また大手書店POSデータ分析も参照しているけれど、実売による書店販売状況は把握できていない。
まさに『出版月報』(6月号)がいうように、「出版状況が大きく改善したわけではない」のである。

1.アルメディアの調査によれば、2020年5月1日時点での書店数は1万1024店で、前年比422店の減少。
売場面積122万2302坪で、同3万8570坪のマイナス。
この書店数の中で、売場面積を持つ店舗は9762店であるので、実質的書店は1万店を下回ってしまったことになる。
1999年からの書店数の推移を示す。
| 年 | 書店数 | 減少数 |
| 1999 | 22,296 | − |
| 2000 | 21,495 | ▲801 |
| 2001 | 20,939 | ▲556 |
| 2002 | 19,946 | ▲993 |
| 2003 | 19,179 | ▲767 |
| 2004 | 18,156 | ▲1,023 |
| 2005 | 17,839 | ▲317 |
| 2006 | 17,582 | ▲257 |
| 2007 | 17,098 | ▲484 |
| 2008 | 16,342 | ▲756 |
| 2009 | 15,765 | ▲577 |
| 2010 | 15,314 | ▲451 |
| 2011 | 15,061 | ▲253 |
| 2012 | 14,696 | ▲365 |
| 2013 | 14,241 | ▲455 |
| 2014 | 13,943 | ▲298 |
| 2015 | 13,488 | ▲455 |
| 2016 | 12,526 | ▲962 |
| 2017 | 12,026 | ▲500 |
| 2018 | 11,446 | ▲580 |
| 2019 | 11,024 | ▲422 |
書店数は1999年に比べれば、まさに半減してしまい、それが出版物販売金額の推移と同様であることはいうまでもないだろう。ちなみにそちらは1999年2兆4607億円、2019年1兆2360億円である。
この事実は雑誌や書籍売上が街の中小書店によって支えられていたことを示し、それらを含めて2万店を越える書店インフラが出版業界にとって不可欠だったことを、今さらながら突きつけている。その要といえる中小書店を壊滅させてしまったことの結果が、出版物売上高の半減なのである。
だからこそ、この20年の取次と書店による大型化、複合化戦略は間違っていたのであり、それが20年のコロナ禍と相乗して、さらなる書店危機を露呈していくことになろう。
2.同じくアルメディアによる「取次別書店数と売場面積」も挙げておく。
| 取次会社 | 書店数 | 前年比 増減(店) | 売場面積 | 前年比 増減(坪) | 平均面積 | 売場面積占有率 | 前年比 (ポイント) |
| トーハン | 4,257 | ▲147 | 484,483 | ▲8,806 | 114 | 39.6 | 0.5 |
| 日本出版販売 | 3,752 | ▲148 | 598,267 | ▲17,592 | 159 | 48.9 | 0.1 |
| 楽天ブックスネットワーク | 917 | ▲62 | 106,802 | ▲10,162 | 116 | 8.7 | ▲0.6 |
| 中央社 | 399 | 0 | 20,922 | ▲268 | 52 | 1.7 | 0.0 |
| その他 | 908 | ▲35 | 11,798 | ▲1,772 | 13 | 1.0 | ▲0.1 |
| 不明・なし | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 1.0 | ー |
| 合計 | 10,234 | ▲391 | 1,222,302 | 38,570 | 119 | 100.0 | ― |
本クロニクル134で、前年のデータも示しているけれど、日販はTSUTAYAの大量閉店もあって、書店数と売場面積は352店、4万6681坪だったので、今年は148店、1万7592坪だから、どちらも下げ止まったように見える。
一方で、トーハンは前年が84店、982坪減に対し、今年は147店、8806坪となっているので、両者とも倍近くになっている。
このような数字のバラつきはあるけれど、日販、トーハンを併せ見れば、書店の大量閉店の流れは変わることなく続いていくと考えるべきだろう。
それを新たに示しているのは楽天ブックスネットワークで、書店数は62店、売場面積は1万162坪減であり、後者はトーハンを上回っている。前年の楽天以前の大阪屋栗田の場合、78店減、66坪増だったことからすれば、今年は不採算書店の整理と売掛金の回収といった方向性へと急速にチェンジしていると推測できる。
しかし1にしても2にしても、まだコロナ禍が充全に反映されているとは言い難い。
来年はどのようなデータとなって現実化するであろうか。
odamitsuo.hatenablog.com
3.トーハンの決算が出された。
単体決算売上高は3834億8900万円、前年比3.5%減。
営業利益は19億7600万円、同53.8%減、経常損失は4億7200万円、当期純損失は55億9200万円。
経常損失の概況は「取次事業」が19億7200万円の損失、「不動産事業」が13億5200万円の利益、フィットネス事業などの「新規事業」が1億2000万円の損失。
それに繰延税金資産28億7100万円を取り崩したことで、最終損失は56億円弱となった。
売上内訳は次に示す。
| 金額 | 増減額 | 増加率 | 返品率 | |
| 書籍 | 167,001 | ▲2,732 | ▲1.7 | 38.9 |
| 雑誌 | 125,745 | ▲7,360 | ▲5.6 | 48.2 |
| コミックス | 47,344 | 3,404 | 7.7 | 26.7 |
| MM商品 | 43,397 | ▲6,981 | ▲13.9 | 19.6 |
| 計 | 383,489 | ▲13,670 | ▲3.5. | 39.6 |
連結決算は連結子会社28社(前期は16社)、持分法適用関連子会社12社(同5社)と拡大した。
売上高は4082億4900万円、同2.1%減、営業利益は13億1900万円、同66.1%減、経常損失は14億5700万円、当期純損失は58億8500万円。ちなみに経営書店は286店。
単体、連結とも創業以来、初の経常赤字を計上。
これらの原因に関して、物流コストの上昇、新型コロナによる出版社の刊行計画の変更、子会社書店の休業、大型帖合変更のずれなどが挙げられている。
しかし何よりもコロナ禍が露出させたのは、再販委託制に基づく近代出版流通システムの破綻のように思える。
前掲の売上高内訳にもあるように、雑誌の返品率は50%近くに及び、近代出版流通システムの根幹ともいえる雑誌の流通販売はもはや崩壊しているといっても過言ではない。
まして来期は4月から6月の第1四半期だけで、110億円の損失が見こまれていることからすれば、来期の決算はさらに悪化するだろう。
日販の決算は延期されているが、こちらもトーハンと同様に赤字を計上するにちがいない。
4.3でトーハンの「不動産事業」にふれたが、『新文化』(6/11)が「社長室」欄で、「急ピッチで進む『不動産事業』」として、それらを具体的に挙げている。
2018年度は「旧九段ビル」のホテル化、「旧九州支店」のマンション化、「旧文京営業所」の賃貸ビル化。
19年度は「京都支店」のホテル化、「旧東北支店」「旧名古屋支店」「旧岡山支店」「旧四国支店」「旧五軒町創庫」「旧五軒町駐車場」「本社隣接駐車場」はいずれもホテル、マンション化のために現在工事中。
愛知のロジスティクスセンターと千葉の初石グラウンドは売却され、大阪支店も移転し、跡地は再開発とされる。おそらく同じく移転する神戸支店なども同様であろう。
トーハンの「事業領域の拡大」の一環として、所有地の土地有効活用が全社的に進められているとわかる。それらは来年竣工するという新本社ビル、その跡地の再開発も含めた一連の不動産プロジェクトの流れがすでに形成されているのであろう。
しかし低金利バブル下の不動産プロジェクト、それに群がるゼネコンとコンサルタントたちの存在を考え、「事業領域の拡大」を長期的に見ると、今期のように順調に利益が積み重ねられていくのか、疑問である。
またコロナ禍を経た後で、ホテル事業の先行きも不透明だし、マンション計画はサブリースであっても、人口減少に向かっていくのだから、こちらも安定利回りは難しい。
結局のところ、立地の悪いロジスティックスセンターやグラウンドのように、売却したほうがよかったと後悔することになるかもしれない。
5.地方小出版流通センターの決算も出された。
今期、総売上高は9億4244万円、前年比7.77%減で、7937万円のマイナスとなり、10億円を割りこんだが、営業収入で赤字は逃れたとされる。
しかしこの決算にはトーハンと同じく、「コロナ緊急事態宣言期間」は入っていない。
ちなみに取次出荷ベースで、4月は17.3%減(2090万円減)、5月は16.2%減(860万円減)となっている。
そのような出版状況の中にあって、「地方・小出版流通センター通信」No.526は次のように記している。
「新型コロナウイルスによる感染防止のため個人も会社(仕事)も4月から5月のほぼ2ケ月活動制限を強いられ、いままで経験したことがない生活状況が続き、いまも続いています。巣ごもり生活で精神的に疲れてしまいそうです。6月に入っても基に戻っているという実感はありません。この状態が秋まで続いたら、事業を何処まで継続出来るか自信がありません。」
これこそ、取次のみならず、多くの出版社や書店の実感に他ならないであろう。
今年の出版業界の夏はどうなるのだろうか。
6.戸田書店静岡本店が7月26日に閉店。
JR静岡駅前の複合商業ビル「葵タワー」の地下1階から2階までの3フロアを占め、県内最大級の書店とされていた。
本クロニクル143で、5月閉店を伝えておいたが、様々な事情で、2ヵ月後に先送りとなっていたようだ。
それは戸田書店ばかりでなく、2の取次の楽天ブックスネットワークの事情も絡んでいると推測される。
odamitsuo.hatenablog.com
7.岐阜の自由書房が全3店を閉店し、書店事業から撤退。
自由書房は1948年創業で、岐阜県を代表する書店として知られていた。
アルメディアの『96年版ブックストア全ガイド』を確認してみると、この時代に自由書房はこの3店を含め、13店を展開していたとわかる。
やはり三洋堂書店や戸田書店に続いて、郊外店を出店し、チェーン化を図っていたのである。
最後に残ったのが、県庁店、高島屋店、大型複合店の鷺山店で、高島屋店には大垣書店がテナント入居し、新規店をオープンするという。
8.ブックオフGHDの決算売上高は843億8900万円、前年比4.4%増、営業利益は14億2800万円、同7.8%減、経常利益は18億9800万円、同10.5%減。
既存店売上はトレーディングカード、ホビー、映像、ゲーム、貴金属・時計・ブラントバックなどが好調だが、書籍はほぼ横ばいで、EC売上高は113億円に迫る10.2%増。
ブックオフも多くを見ていないので、推測であるが、書籍以外の商品をメインとする店舗が増えているのだろう。
本クロニクル140で、ゲオが古着店「セカンドストリート」を既存店舗に出店させ、その売上が500億円に達していることを既述しておいたが、ブックオフもかつての書籍から、他の商品へと比重が高くなっているのであろう。
ちなみにそれに伴ってか、店数の801店のうち、直営が404店、FCが397店と比率が逆転してしまっている。かつてのブックオフのコアはフランチャイズ展開にあったことからすれば、それもピークアウトしたことになる。
だがブックオフにしても、コロナ禍から逃れられず、来期はどのような決算となるのだろうか。
odamitsuo.hatenablog.com
9.『出版月報』(4・5月号)が特集「ムック市場2019」を組んでいるので、そのデータを示す。
| 新刊点数 | 平均価格 | 販売金額 | 返品率 | ||||
| 年 | (点) | 前年比 | (円) | (億円) | 前年比 | (%) | 前年増減 |
| 2005 | 7,859 | 0.9% | 931 | 1,164 | ▲4.0% | 44.0 | 1.7% |
| 2006 | 7,884 | 0.3% | 929 | 1,093 | ▲6.1% | 45.0 | 1.0% |
| 2007 | 8,066 | 2.3% | 920 | 1,046 | ▲4.3% | 46.1 | 1.1% |
| 2008 | 8,337 | 3.4% | 923 | 1,062 | 1.5% | 46.0 | ▲0.1% |
| 2009 | 8,511 | 2.1% | 926 | 1,091 | 2.7% | 45.8 | ▲0.2% |
| 2010 | 8,762 | 2.9% | 923 | 1,098 | 0.6% | 45.4 | ▲0.4% |
| 2011 | 8,751 | ▲0.1% | 934 | 1,051 | ▲4.3% | 46.0 | 0.6% |
| 2012 | 9,067 | 3.6% | 913 | 1,045 | ▲0.6% | 46.8 | 0.8% |
| 2013 | 9,472 | 4.5% | 884 | 1,025 | ▲1.9% | 48.0 | 1.2% |
| 2014 | 9,336 | ▲1.4% | 869 | 972 | ▲5.2% | 49.3 | 1.3% |
| 2015 | 9,230 | ▲1.1% | 864 | 917 | ▲5.7% | 52.6 | 3.3% |
| 2016 | 8,832 | ▲4.3% | 884 | 903 | ▲1.5% | 50.8 | ▲1.8% |
| 2017 | 8,554 | ▲3.1% | 900 | 816 | ▲9.6% | 53.0 | 2.2% |
| 2018 | 7,921 | ▲7.4% | 871 | 726 | ▲11.0% | 51.6 | ▲1.4% |
| 2019 | 7,453 | ▲5.9% | 868 | 672 | ▲7.4% | 51.1 | ▲0.5% |
19年のムック市場は672億円で、14年に1000億円を割りこんで以来、まったく下げ止まらず、1997年には1355億円だったわけだから、やはり半減してしまったことになる。それは販売部数も同様である。97年の1億4469万冊が2019年には6912万冊となっている。
しかも返品率は5年続きの50%超で、雑誌、それも月刊誌の高返品率の一因であることは自明だろう。新刊点数はこの2年で千点も減っているにもかかわらず、返品率は高止まりしているからだ。
『おとなの週刊現代』の大ヒットもあり、単発のヒットは続くにしても、全体的にはさらに凋落していくであろうし、コロナ以後のムックの行方も厳しいと考えるしかない。
10.『新文化』(6/4)が「コロナ『給付金』『借入れ』の留意点」と題し、出版業界の金融機関である文化産業信用組合の秋本康男理事長にインタビューしている。それを要約してみる。
| ★ 出版界は不況業種のため中小企業信用保険法の第2条5項4・5号、及び同条6項の対象となっている。 |
| 「4号認定」は最近3ヵ月間の売上が前年比20%減少した場合、「5号認定」は同5%減少した場合、「6項〈危機対応〉認定」は突発的な事故で同15%以上減少した場合に認定され、自治体が定めた限定額まで優遇融資が受けられる。 |
| ★ まずは経産省の持続化給付金を給付してもらう。月商が前年比より50%以上減少している中小企業は上限200万円、個人事業者は100万円の給付となる。 |
| ★ その他には休業補償する厚生労働省の雇用調整助成金があり、休業中の従業員の雇用を維持するために、賃金の60%以上を支払っているとき、同省から補助金が得られる。 |
| ★ これとは別枠で、今回の第一次補正予算より、3000万円まで融資を受けることができる。それは実質無担保、無利息で、5年据置き、5年返済、すなわち10年スパンの借入制度である。ただし無担保、無利息は最初の3年間だけで、4年目から利益と保証料の支払いが発生する。 |
| ★ 具体的な申請手続きとして、中小企保法の4号、5号、危機対応6項などの適用を受けるには区役所の認可が必要である。 |
| 申請書の書き方は当行に相談してほしい。保証は今年の年末まで受付けているので、まだ時間がある。 |
| ★ コロナ禍の中での出版社は今後大量返品も懸念され、短期的に赤字になるかもしれないが、借入理由が明確であれば、与信が担保となり、それに見合った融資、条件変更もできる。 |
| ただ先の3000万円融資の場合、据置き期間を終えて5年で返すのはV字回復の保証もないので辛いし、やはり心配になる。額を減らし、短期返済を考えるべきだ。 |
| ★家賃補償は第二次補正予算で決まると思うが、東京都の一店舗50万円、2店舗100万円が参考基準となるのではないか。 |
| ★ これからは売上高基準で経営する時代ではなく、キャッシュフロー経営に向かうべきで、経営者による会社への貸付金、自己不動産の無償貸与は止めるべきだ。本は水モノかもしれないが、これからのビジネス戦略を再考してほしい。 |
まさに出版業界の中小企業の金融機関に他ならない文信理事長の声なのだ。少しばかり長く紹介してみた。
耳の痛いことも含まれているけれど、読まれた上で、文信に相談して頂ければと思う。
11.『アサヒカメラ』(朝日新聞出版)が20年7月号で休刊。
1926年創刊で、94年にわたって刊行されてきた日本最古の写真、カメラ専門雑誌である。
発行部数は3万1500部だったとされるが、コロナ禍による広告収入の低迷が原因という。
なお写真界の芥川賞とされる木村伊兵衛写真賞は朝日新聞社と朝日新聞出版が共催し、引き継がれる。

『アサヒカメラ』7月号は書店で売っていないし、アマゾンでも品切だったので、新聞販売店ルートで入手した。
16人の写真家たちが語っている「私とアサヒカメラ」は、同誌が多くの写真家の揺籃の地であったことを伝え、感慨深い。
とりわけ北井一夫の「有楽町社屋の黒いソファは写真学校だった」は彼の『村へ』が連載され、それによって第1回木村伊兵衛写真賞を受賞したことが述べられている。
私は淡交社版『村へ』(1980年)を参照し、拙稿「村から郊外へ」(『郊外の果てへの旅/混住社会論旅』所収)を書いていることを付記しておく。

12.『全国出版協会70年史(1949~2019)』が出された。


戦後の全国出版協会の誕生と歴史は同書にゆずることにして、ここではその第2章のタイトルにもなっている出版科学研究所にふれておこう。
出版科学研究所は1956年に東販の出版物研究機関として発足し、59年から『出版指標 年報』、及び『出版月報』(6月号)を発刊している。
そして69年に出版科学研究所は東販から社団法人全国出版協会へ移管され、公益法人傘下の調査研究機関として新たにスタートした。
それからの出版科学研究所と『出版月報』(6月号)の歩みはその章を読んでもらうしかないが、長年にわたる本クロニクルの連載にしても、出版科学研究所のデータの集積を抜きにして語れない。
地味な仕事ではあるけれども、出版業界の長期的変動に関する第一次資料に他ならないので、さらに持続するデータの追跡を願ってやまない。
13.『股旅堂古書目録』23が届いた。

この23号には「〈丸尾長顕旧蔵〉昭和初期エロ・グロ・ナンセンス関連出版社書籍雑誌出版案内チラシ67枚」なども掲載され、いつもながら充実している。ただし古書価は20万円。
それだけでなく、『「奇譚クラブ」から「裏窓」へ』(「出版人に聞く」12)の著者の飯田豊一の旧蔵書が彼の「談」二ページを添えて出品されている。
折しも、1982年創刊のゲイ雑誌『サムソン』(海鳴館)の休刊が伝えられてきた。これは未見だが、いずれ股旅堂が特集してくれるだろう。

14.集英社『KOTOBA』 40が丸ごと「特集スティーブン・キング」を組んでいる。

キングはベストセラー作家なので、かなり雑誌特集が組まれていると思われるかもしれないが、私の記憶では『ユリイカ』(1990年11月号)以来かもしれない。現在において、もっと論じられてしかるべき作家なのに、どうしてなのか。
今回の特集はキングが新種ウィルスによる世界破滅をテーマとする『ザ・スタンド』(深町真理子訳、文春文庫)、疫病パンディミックを扱った未邦訳の『眠れる美女たち』を書いていること、及びキングの「コロナウィルスのようなパンディミックはおこるべくして起こったものだ、我々の社会のように移動が日常的に必要な社会では遅かれ早かれ、一般の人々に感染してしまうウィルスが出現することになってたんだ」というキングのSNSでの発信などにも基づいているのだろう。
そういえば、彼の小説、映画ともに、私の偏愛する『デッド・ゾーン』(吉野美恵子訳、新潮文庫)はトランプ大統領の出現を予告していたようだ。実際にキングは反トランプ主義者で、ツィッターで批判を続けているという。
もう一度キングを読み直してみようと思う。


15.ネットフリックスで大ブレイク中の韓国長編ドラマ『愛の不時着』を観てしまった。


おそらく全編が引用からなる映像シーンに覆われているが、それはひとつの前提としてのドラマツルギーのようにも思われた。
ネットフリックスでしか観られないので、まだ観ていない人も多いだろうし、本クロニクルの読者には一見をお勧めする。
それは映画におけるレンタルと配信の問題にもリンクするし、コロナ以前、以後をメタファーとして浮かび上がらせているかもしれないからだ。
16.論創社のHP「本を読む」〈53〉は「思潮社とロジェ・カイヨワ『夢について』」です。
『近代出版史探索Ⅱ』は5月下旬に刊行された。
続けて『近代出版史探索Ⅲ』が7月下旬発売予定。

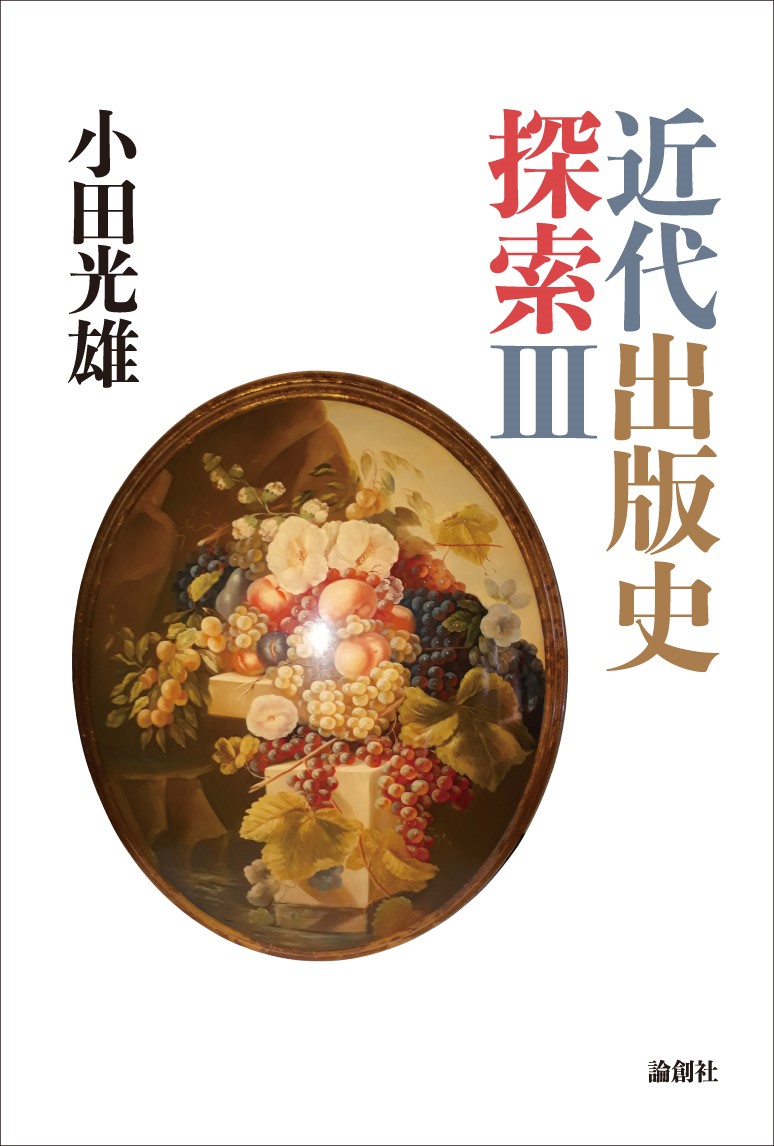
晧星社から片岡喜彦『古本屋の四季』が届いた。表紙の祖父江俊夫の絵がノスタルジーを喚起させるので、書影を示しておく。




