前々回の中里介山の『遊於処々』において、上海に向かう長崎丸の利用者に村松梢風たちがいると述べられていた。それを読み、村松に上海を舞台とした『魔都』という一冊があり、しばらく前に浜松の時代舎で入手したことを思い出した。


同書は四六判上製のかなり疲れた裸本で、背のタイトルは褪色のためはっきり読めず、本体の表紙の金箔の絵のところにようやく『魔都』が見てとれ、著者名に至っては本扉によって村松梢風だとわかる。しかも乱丁本であった。『近代出版史探索Ⅴ』899で、久生十蘭の昭和十年代の東京を舞台とする『魔都』を取り上げているが、こちらは『近代出版史探索』169の村松梢風による上海が『魔都』として描かれたことになる。

ただ介山が長崎丸で上海に向かったのは昭和六年だったが、村松の場合は大正十二年三月で、二ヵ月余り滞在し、その間の出来事と見聞をベースとして、彼ならではの情話的な『魔都』など三編の他に、「江南雑筆」を始めとするエッセイ六編を書いたのである。それは大正十三年に発行者を小西栄三郎とする神田小川町の小西書店からの刊行だが、この三〇七ページの一冊は大正十二年の上海のリアルなレポートでもあり、それに先立つ同十年の芥川龍之介「湖南の扉」(『湖南の扉』所収、文藝春秋社出版部、昭和二年)とは異なる同時代の中国物といっていいだろう。実際に『魔都』には芥川への言及も見えている。
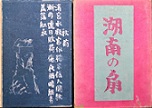
それほど期待して読み始めたわけではないけれど、この『魔都』はまるごと上海を対象としている一冊に他ならず、その同時体的臨場感は比類のないリアリティに満ちていたし、それは出来事や人物も含めてだった。村松がその「自序」で述べている言はその事実を肯っていよう。そこで彼は「変った世界を見ること」、及び「変化と刺激に富む生活を欲した」と書いている。だがその理由にはふれられていないけれど、関東大震災の半年前だったことは留意すべきだろう。上海は揚子江流域の主要な港、工業の中心地、中国人街、治外法権の国際租界が錯綜する都市だった。つまり上海は日本から最も近い「魔都」だったのだ。
私の其の目的には、上海は最も適合した土地であつた。それは見様に依つては実に不思議な都会であつた。其処は世界各国の人種が混然として雑居して、そしてあらゆる国々の人情や風俗や習慣が、何んの統一もなく現はれてゐた。それは巨大なるコスモポリタンクラブであつた。其變には文明の光が燦然として輝いてゐると同時に、あらゆる秘密や罪悪が悪魔の巣のやうに渦巻いてゐた。極端なる自由、眩惑させる華美な生活、胸苦しい淫蕩の空気地獄のやうな凄惨などん底生活―—それらの極端な現象が露骨に、或は陰然と、漲つてゐた。天国であると同時に、其処は地獄の都であつた。私は雀躍りして其の中へ飛び込んで行つた。然るに私は其処で図らずも一つの事件にぶつかつた。そして其の事件を背負つたまゝで日本へ還つて来たのだ。
この「一つの事件」は村松の上海での二十六歳の女性との出会いで、「特殊な関係」が生じてしまったことをさす。彼女は社交ダンスの教授をしていたが、「殆んどあらゆる人生を経験して来てゐる」という「美貌と情熱と本気」「凄惨な魅力」を備えていたことから、「彼女をモデルとする長編の創作を試みようと決心」し、同棲するに至る。その「Y子」のことは『魔都』においてまさに宿命の女のように描かれているのだが、ここではそれよりもやはり上海という「天国であると同時に、其処は地獄の都」に言及しておくべきだろう。それは介山が描いた上海とも色彩が異なるし、村松は書いている。
あらゆる文明の設備が完全して、華やかに美しく、そしてほしいまゝな歓楽に飽くことを知らぬ上海といふ都会は、一歩裏面へ踏み込むと、陰惨とした物凄い幕で包まれてしまふ。其処では有らゆる犯罪が行はれ、あらゆる罪悪を以て充満されてゐる。泥棒、殺人、詐欺、賭博、誘拐、密輸人、秘密結社、淫売、脅迫、美人局、阿片吸引――そのほか大小無数の犯罪が白昼でも深夜でも、処嫌はず年がら年中行なはれてゐる。そうしてそれらの悪漢共は誰れ憚らず大手を振つて歩いてゐる。
そして村松はある人の言葉として、「上海の往来を歩いてゐて、男が来たら泥棒と思ひ玉へ、女が来たら淫売婦だと思ひ玉へ」を引いている。また日本人女性が繁華街のショーウィンドーに見惚れたところ、西洋人の自動車に連れこまれ、行方不明になった話なども語られ、エドガール・モランの『オルレアンのうわさ』(杉山光信訳、みすず書房)ならぬ、様々な「上海のうわさ」が列挙されていく。上海は「かうした探偵小説の発端になりさうな話」が多く伝わる都市なのだ。

村松は「臆病者」を自称しながらも、その物騒な都市を観察し、不夜城といえる上海の夜の世界を彷徨し始める。そうした夜の果てに何が待ち受けていたのか、それは『魔都』を読んでもらうしかないのだが、残念なことに村松のこの一冊はそのままのかたちで復刻されていないと思われる。
なお念のために梢風の孫の村松友視『鎌倉のおばさん』(新潮社、平成九年)を確認したが、「Y子」は「よし子」として出てくるけれど、「鎌倉のおばさん」ではなかった。それはもうひとりの上海の女で、絹江という愛人だったのである。
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら
