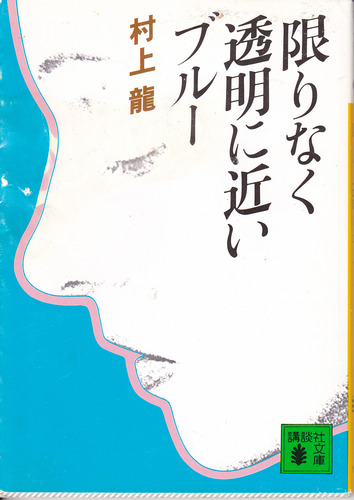(上林暁)
(島田謹介)
かなり長く武蔵野を歩いてきた。まだ武蔵野に関する戦前の文献資料として、民俗学の先達である山中共古が寄稿していた同人誌『武蔵野』、『ホトトギス』同人を始めとし、明治の武蔵野の名残を求め歩き、吟行に及んだところの高浜虚子編『武蔵野探勝』(甲鳥書林、一九四一年、有峰書店、一九六九年)などが残されている。だがこれらは別の機会に譲り、戦後に出された武蔵野の写真集を取り上げてみたい。最後に、ピクチャレスクといわないにしても、目に見える具体的な武蔵野を確かめておきたいからだ。
 (有峰書店版)
(有峰書店版)それは二冊あって、上林暁『武蔵野』と島田謹介『武蔵野』を挙げることができる。前者は社会思想社の現代教養文庫の一冊として出された小さい本で、上林の武蔵野をめぐる一九四〇、五〇年代の一連のエッセイに、大竹新助の七十点ほどに及ぶ写真を添えている。後者は菊倍判を超える大きな本で、こちらは島田個人の純然たる写真集であり、その八十三の写真は大半が見開き二ページに及んでいて、他に類を見ない武蔵野に関する写真集だといえるであろう。まったく外見の異なる二冊の本に共通するのは、両者がいずれも徳富蘆花の『みみずのたはこと』と国木田独歩の『武蔵野』の影響下に成立していることだが、ただどちらかといえば、上林は『みみずのたはこと』、島田は『武蔵野』の色彩が強い。それらを踏まえ、この二冊を見てみよう。

 (国木田独歩)
(国木田独歩)
上林の『武蔵野』は一九六二年に出されている。その「序 武蔵野をたずねて」において、武蔵野というとすぐに思い浮かぶのは「白くほうけた芒の穂が一列に長く連ってい」る風景で、それは終戦直後のことだったから、もはや十年余が過ぎているので、そうした景色も光景をなしていた杉林とその紅葉と桐畑も跡形もなく、おそらく住宅が建てこんでいるだろうと上林は始め、「武蔵野はめまぐるしく変貌する」と続けている。そして『みみずのたはこと』への言及がなされ、それが「蘆花の時代から続いている東京の触手に侵蝕される武蔵野の宿命だというニュアンスを伝えている。
その十六編からなる上林の武蔵野論は戦前と戦後に書かれたものが混住しているけれど、ここでは戦後の「聖ヨハネ病院再訪」と「蘆花墓前祭」にふれてみたい。私小説作家としての上林は病妻物の連作の一編「聖ヨハネ病院にて」を一九四六年に発表し、同年刊行の『晩春日記』(桜井書店)に収録している。この作品は四五年秋、上林が病院に宿泊し、妻を看取った記録で、『晩春日記』の「後書」もまたそこで書かれたのである。「聖ヨハネ病院再訪」はそれから八年後の五三年に書かれたものである。それは新聞社のグラフ雑誌の企画で、現代作家の主要な作品の舞台、モデル、シーンなどをカメラを携え、探訪する一編として書かれている。これを読んで、「都下K町の聖ヨハネ病院」が小金井町の桜堤の近くに位置しているカソリック系の聖ヨハネ会桜町病院であることをあらためて知った。そして同じように、彼の妻がそれに隣接した精神病専門の小金井養生院に七年間にわたり入退院を繰り返したこと、また聖ヨハネ病院からさらに多摩川に近い宇田病院へ移送され、そこで死んだことも。

上林の「再訪」は「悲しみも辛さも含めたなつかしさ」を伴うものだった。それに応えるように、聖ヨハネ病院は彼の小説よって著名になり、新しい病棟も完成しつつあったが、病室や看護婦室や教会堂は変わっておらず、日は好く、人の心は温かく、上林はそこで「脳出血の病後第一等の日」をもったのである。この「聖ヨハネ病院再訪」には「修道院の庭」と「小金井堤の桜」と題された見開き二ページの写真が二点含まれ、どちらも道が映っている。ひとつは林の中の道、もうひとつは堤の上の道で、これらを見ていて、私はこれも再読した「聖ヨハネ病院にて」の「付記」の文章を想起した。
そこで彼の妻は聖ヨハネ病院から多摩川に近い病院へと移送されるのだ。それは夫が過労と栄養失調のために付き添いできなくなり、付き添いのある病院へと移らなければならなかったからで、一緒に運送屋のリヤカアに乗っていくのである。看護婦二人と彼との三人がかりで妻をリヤカアに運んだが、驚くほど軽かった。そうしてリヤカアは出発する。
リヤカアは、街道を避けて裏路を選び、林を抜け、田圃の小径を通り、また林を抜け、屋敷の生垣の間を走り、電車の踏み切りを越えて行った。(中略)
リヤカアは、火の見櫓のところで道を折れて、多摩川の方角へ走って行った。
このリヤカアが通り抜け、走っていった道こそがこの二点の写真に映っている道に他ならないように思えてくるし、引用文の叙述をふまえてこれらの写真も撮られたのではないだろうか。
もうひとつの「蘆花墓前祭」は五七年に書かれたもので、上林は蘆花の三十年忌墓前祭に出席するために、粕谷の恒春園を訪れる。恒春園は蘆花の千歳村粕谷の元屋敷で、彼の死後、夫人が東京市に寄付し、公園となったのである。上林は蘆花の死の際に改造社に勤めていたことから、青山会館での告別式の手伝いに派遣されていたので、その時のことを思い出した。それから三十年が経ったのだ。蘆花の眠る雑木林と旧宅と書斎の前にある石仏の写真が添えられ、これらは『みみずのたはこと』の残影をとどめているかのようだ。
これらの写真を撮った大竹新助は文学写真家とでも称すべきか、同じく現代教養文庫にも正続『写真・文学散歩』などが収録されていて、独歩の『武蔵野』や蘆花の『みみずのたはこと』の他にも、本連載81 で取り上げた大岡昇平『武蔵野夫人』や谷崎潤一郎『痴人の愛』の風景を切り取っている。それらの風景もまた、最初に示した上林の述懐ではないが、大半が消えてしまったにちがいない。そうしてこの二冊のサブタイトルに「本の中にある風景」として、モノクロ写真で残されたことになる。



もう一冊の島田謹介の『武蔵野』は前述したように大型の写真集で、島田は一九〇〇年に長野の松代町に生れ、二〇年に朝日新聞社社会部写真係になり、大正から昭和の戦前にかけての二・二六事件などの大きな社会的事件に立ち合い、多くの歴史的瞬間をカメラに収めているという。五五年に退社してフリーとなり、日本の自然観照をモチーフとする風景写真を撮ることをめざしたようなので、五六年に刊行された『武蔵野』はそうした第一作品集に位置づけられるのかもしれない。
この島田の『武蔵野』に独歩の影響を指摘しておいたが、武蔵野の春夏秋冬の一年を通じて最も多く写されているのが雑木林の風景で、キャプションは別にして広義に考えれば、八十三点の半分強が雑木林とそれに準ずるものだと見ていい。島田が「あとがき」に付した一文を読むと、雑木林を多く写しているのは武蔵野に対するレクイエムのように思えてくる。
武蔵野! なんというさわやかな懐しみあふれる文字だろう。そして、なんという夢多い郷愁をさそう言葉だろう。親しまれ、懐しがられた美しい武蔵野は日に日にその面影をなくし、惜しまれながら滅びようとしている。
国木田独歩の「武蔵野」は武蔵野の自然の四季の美しさ、愉しさを書き尽して余すところがない。(中略)
独歩はよく、静かな雑木林に坐して四顧し、そして耳を傾けたと言い、荷車の音、空車の音のことを度々書いている。今はゴム輪がはまって、リヤーカーも荷車も音がしないが、その頃の荷車は鉄輪のかかったガラガラ音をたてる車だった。雑木林に坐って小鳥の囀りを聴き、蒼い空を眺め、流れる雲を楽しめる静かな空車の響く武蔵野だった。
そうした雑木林の名残りを求めて、島田は武蔵野を歩き周り、蘆花の恒春園の雑木林にカメラを向ける。だがそれは「一握り程の雑木林」としてしか残っておらず、かつての武蔵野一帯に多かった杉木立、欅の屋敷林も少なくなってしまった。写真はそれらへの愛惜の思いにも包まれているようであるし、時代は異なっているけれど、「冬の朝」とある一枚の写真は、独歩の『武蔵野』の表紙の上に描かれた岡落葉による夕暮れの風景を彷彿とさせ、これもまた挽歌のようでもある。そして農のある風景、すすきや野火の光景も同様なのだ。
しかしもはやそのような武蔵野も消え去ろうとしていて、それが雑木林の消滅に表われてきている。島田は記している。「春の新緑を訪ねた雑木林は、秋にはすっかり伐り払われて、分譲地の看板が立ち、林の奥から賑やかな鉄槌の音がひびいて、そこには公庫住宅が赤い瓦を並べていた。全く今日の武蔵野は明日の武蔵野ではない」。
その一方で、「今の武蔵野を当もなく歩くと駐留軍の大きな施設にぶつかり」、「間断なく基地から飛び出すジェット機の爆音と大型機の轟音に、流石に広い武蔵野の野も空も気違いのような騒音に包まれる」のだ。そのことも刻印するかのように、「基地の秋」とキャプションのある写真が挿入され、武蔵野の空を飛んでいる基地の飛行機が写し出されている。
この写真からは「爆音」も「轟音」も聞こえてこないけれど、武蔵野に米軍基地があることを告知する一点で、武蔵野の風景を異化する役割を果たしているように思える。拙著『〈郊外〉の誕生と死』において、村上龍の『限りなく透明に近いブルー』が基地のある福生を舞台にしていたこと、また本連載 4 の山田詠美の『ベッドタイムアイズ』が横田基地を背景としていることなどを既述してきたが、武蔵野こそは基地のある郊外を象徴していることにもなる。それが戦後にもたらされた武蔵野の現実であり、島田の『武蔵野』が刊行されてから、すでに半世紀以上が過ぎ、武蔵野の風景はドラスチックな変容をこうむらざるをえなかったが、米軍基地の現実はまったく変わっていない。