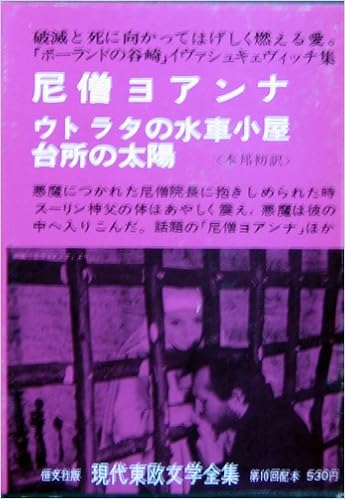18年4月の書籍雑誌推定販売金額は1018億円で、前年比9.2%減。
書籍は538億円で、同2.3%減。
雑誌は480億円で、同15.8%減。
雑誌の内訳は月刊誌が393億円で、同15.7%減、週刊誌は87億円で、同16.2%減。
返品率は書籍が35.2%、雑誌が46.6%。
雑誌返品率の改善のためにコミックやムックの送品が大幅に抑制されていて、雑誌推定発行金額は2月が11.3%、3月12.1%、4月は14.0%、それぞれ減となっている。だが返品率は3ヵ月続けて40%を超え、4月までの平均返品率は44.7%に達している。
ちなみに15年は41.8%、16年は41.4%、17年は43.7%であるから、大幅な送品調整や抑制によっても、返品率は上がり続けているのだ。
その一方で、書籍返品率はまだ30%台にとどまっているが、それでも取次にとって赤字とされていることからすれば、雑誌も赤字へと追いやられていると考えられる。つまり書籍と雑誌という流通の両輪が、赤字に陥りながら作動していることにもなる。
4月の前年同月比マイナスが103億円で、18年1月からら4月にかけての累計が、すでに425億円減である。
このマイナスがさらに加速していくと推測されるし、そのことから判断すれば、18年の書籍雑誌推定販売金額は1兆2500億円ほどに落ちこんでしまうだろう。これが18年の出版業界の恐ろしい現実に他ならない。
本クロニクルで使用している数字は周知のように、出版科学研究所のデータであり、これは取次ルートの出荷金額から書店返品金額を引いたものによっている。すなわち取次売上がダイレクトに反映され、月を追うごとに深刻さを増していく取次の危機を伝えていることになる。
1.『文化通信』(5/21)などによれば、日販懇話会で日販の平林彰社長は、取次事業が5億円を超える赤字に転落し、「取次業は崩壊の危機にある」と報告した。
商品別では雑誌の営業利益が5億円と、5年で6分の1となり、書籍は30年来の赤字が続いているとされ、取次業を作り直すための5つのキーワードを挙げている。それを要約して示す。
* 書店を増やす。
* マーケットインする。これを補足説明すれば、経営用語で、市場の要求に応じて製品やサービスを提供しようとすることをさす。
* 返品を減らす。
* 在庫の見える化と確約。
* 物流コストの圧縮。
これらに加え、出版社に対しては、書籍の定価値上げ要請とともに、仕入れ条件が70%を超えると黒字化できないことを挙げている。
これは本クロニクル119の「日販非常事態宣言」後のさらなる具体的な方針の提言であり、取次事業とは別に小売事業も本業として前面に押し出されている。
それは本クロニクル120でも記述しておいたように、CCC=TSUTAYAと「囲い込み」傘下書店の販売金額を合わせれば、日販の連結売上高の半分に達するからだ。しかも今期は小売事業が6年ぶりに10億円近い黒字に転換し、連結業績として減収増益になったとされる。
しかしここに挙げられた5つのキーワードは目新しいものではないし、それに現在の出版状況において、最初の「書店を増やす」ことは、いうまでもなく本クロニクルの発信への対応だが、可能だとは思われない。書店のマージン増やし、出店を加速するとの言も、書店市場の現実との乖離は明らかだ。もしそれがCCC=TSUTAYAと「囲い込み」傘下書店を増やすのであれば、書店はさらに減っていくだろう。
本気で「書店を増やす」ことを考えるのであれば、書籍の低正味買切制を提案実行し、保証金不要の書籍中心の中小書店の開店をアシストする方向しかない。
それからこれは『出版状況クロニクルⅤ』でも示しておいたが、日販の粗利益率は12.1%、トーハンは13%であり、大手書店は出版物だけでも、歩戻しや報奨金も含めれば、粗利益率は30%を確保していると伝えられている。それゆえに日販の小売事業が黒字化したのかもしれない。とすれば、現在の返品率から見て、出版社が最も粗利率が低いという事態を迎えているとも考えられる。
また前回のクロニクルで、「文庫マーケット」の17年の書籍推定販売金額シェアが14.7%であることを既述しておいた。この文庫マーケットは岩波文庫を除いて、大手出版社の文庫も出し正味は70%を超えていないはずだ。それに岩波文庫の場合、買切で返品がないことからすれば、70%以上でも黒字かもしれない。
このように「書店を増やす」や出版業界のマージン問題に関しても、多様な視点の導入が必要であり、日販の5つのキーワードなども、出版社や書店を含めたオープンな論議が不可欠であることはいうまでないだろう。
2.『新文化』(4/26)などによれば、全国トーハン会代表者総会において、トーハンの藤井武彦社長は雑誌コミックスが急減し、「出版業界は未曽有の事態が起こりつつある」とし、今後の基本方針を提出。
それは出版卸業を基軸とする出版総合商社としての様々な営業施策の実行と、新商品の開発によるエリア書店のサポートの強化、出版業界の構造変化に対応し、事業領域を拡大し、書店とともに勝ち残るというものだ。
具体的には17年度物流増加分は13億円に及び、出版社に運賃の適正負担や条件の見直し、定価の引き上げなどを要請しているとされる。
基本的には日販と変わらないが、トーハンは、日販におけるMPDとCCC=TSUTAYAのような存在がないこともあり、小売事業は前面に押し出されていない。簡略にいってしまえば、三洋堂のようなバラエティショップを推進していくとの表明であろう。
1に続いて、取次の動向に言及したのは、これらは取次マターではあるけれど、今後の出版業界の行方を占うものとして提出されているからで、それらの現在と今後の状況分析に関して、1で示したように、疑念を拭いきれないことによっている。
もはや前世紀の1989年のことになってしまうけれど、消費税導入時に「内税」方式を選択したことで、混乱と低迷の一年を体験しているからである。そのことによって、書籍の書店在庫がすべて返品され、出版社は新価格のためにカバーの取り替えやシール貼りに追われ、取次の検品の経費が増大した。そのために数百億円の在庫が絶版、断裁処分となり、出版業界全体で1千億円以上のロスが生じたと伝えられている。
外税とすれば、このような混乱とロスは起きなかったはずで、その真相を書協の幹部に問いただしたことがあった。それは雑協が、外税として端数が出ることを回避するために、出版物の消費税はずっと3%で上がらず、そのまま軽減税が続くと主張し、書協がそれに同調したからだという。そこで雑協は何らかの証拠となる文書や資料を示してのことだったのかとも聞いたが、それらはまったくなく、単なる風評に基づくものだったとの返事だった。その元幹部も、あの時、外税にしていれば何の問題もなかったはずで、大失敗だったと語っていた。
これは現代出版史のどこにも書かれていないと思われる。それゆえに、今回の取次の「非常事態宣言」の始まりと行方を記録し、検証するために本クロニクルは記されていることを付記しておく。
3.大阪屋栗田が、楽天と出版4社、DNPの増資を受け、楽天の出資比率が51%となり、楽天の子会社化。
前回の本クロニクルで、その後の大阪屋栗田の動向を伝えられていないことに疑念を表明しておいたが、月末になってようやくこの「ニュースリリース」が出された。その代わりのように、本クロニクルに向けられた「当社に関する虚偽情報の発信に関して」という「ニュースリリース」は削除されている。
もはや大阪屋栗田は出版業界の取次というよりも、楽天の子会社としての、出版物も含んだ物流会社へと向かっていくだろう。役員構成を見ると、前社長の大竹深夫は特別顧問に退き、会長、社長、専務は楽天出身のメンバーで占められ、取締役の一人として日販出身の金田徴が顔を見せているだけで、取次だった大阪屋や栗田の人たちは誰もいないことがそれを物語っている。
それに加えて、増資がなければ、決算発表ができなかったと推測される。本クロニクル118の発信以来、取次状況は急変し、日販は「非常事態宣言」というべき声明を出し、続いて1のような表明、それに合わせて、2に見られるようにトーハンも同様に「出版業界は未曽有の事態が起こりつつある」と公表するに至った。
わずか3ヵ月足らずの間に、日販とトーハンが「出版不況」ではなく、本クロニクルが指摘し続けてきた「出版危機」を、否応なく認めざるをえなかったことになる。しかもそれは先送りできる状況ではないのだ。
4.日書連加盟組合員数は4月1日現在で、前期比255減の3249となる。
前回のクロニクルで、2017年の公共図書館数が3292であることを記しておいたが、ついに図書館数のほうが上回ってしまったことになる。
これほどまでに民業を官業が圧迫し、このような事態まで追いやられてしまった例を他に知らない。来年の日書連加盟組合員数が3000を割ることは確実で、さらにその差は開くばかりだろう。
1986年には1万3000店あったわけだから、何と1万店が消滅してしまったのである。出版物販売金額もこの20年間で半分になってしまった。最大の要因がそこに求められるのである。
5.『出版月報』(4月号)が特集「ムック市場2017」を組んでいる。そのデータを示す。
| 新刊点数 | 平均価格 | 販売金額 | 返品率 | ||||
| 年 | (点) | 前年比 | (円) | (億円) | 前年比 | (%) | 前年増減 |
| 2005 | 7,859 | 0.9% | 931 | 1,164 | ▲4.0% | 44.0 | 1.7% |
| 2006 | 7,884 | 0.3% | 929 | 1,093 | ▲6.1% | 45.0 | 1.0% |
| 2007 | 8,066 | 2.3% | 920 | 1,046 | ▲4.3% | 46.1 | 1.1% |
| 2008 | 8,337 | 3.4% | 923 | 1,062 | 1.5% | 46.0 | ▲0.1% |
| 2009 | 8,511 | 2.1% | 926 | 1,091 | 2.7% | 45.8 | ▲0.2% |
| 2010 | 8,762 | 2.9% | 923 | 1,098 | 0.6% | 45.4 | ▲0.4% |
| 2011 | 8,751 | ▲0.1% | 934 | 1,051 | ▲4.3% | 46.0 | 0.6% |
| 2012 | 9,067 | 3.6% | 913 | 1,045 | ▲0.6% | 46.8 | 0.8% |
| 2013 | 9,472 | 4.5% | 884 | 1,025 | ▲1.9% | 48.0 | 1.2% |
| 2014 | 9,336 | ▲1.4% | 869 | 972 | ▲5.2% | 49.3 | 1.3% |
| 2015 | 9,230 | ▲1.1% | 864 | 917 | ▲5.7% | 52.6 | 3.3% |
| 2016 | 8,832 | ▲4.3% | 884 | 903 | ▲1.5% | 50.8 | ▲1.8% |
| 2017 | 8,554 | ▲3.1% | 900 | 816 | ▲9.6% | 53.0 | 2.2% |
2017年のムック市場の推定販売金額は816億円、前年比.6%減と7年連続のマイナスである。
17年の販売部数は1992年以来25年ぶりに1億冊を割り込み、8873万冊、前年比12.5%減となった。
しかしそれよりも問題なのは、返品率が3年連続で50%を超え、しかも17年は53%に達してしまったことだ。
ムックは週刊誌や月刊誌と異なり、セット商品などとして再出荷され、ロングセラー的販売が可能であった分野だが、もはやそれも成立しなくなったことを、返品率は象徴しているのだろう。
それに50%を超える3年連続の高返品率は、雑誌のうちのムックが取次にとって赤字となっていることを示唆している。
1と2に明らかなように、雑誌が黒字のうちに書籍にシフトしていくという取次提案にしても、コンビニ部門が大赤字のように、雑誌部門そのものも赤字になりつつある状況を迎えていると推測される。
6.『日経MJ』(4/30)が「縮むブックオフ」を特集している。
それは「5年で200店減、3期連続最終赤字」という見出しに表象されている。
ブックオフの創業地の相模原市で、30年の歴史を持つ「相模原駅前店」がこの2月に閉店したことに象徴されているように、ピーク時の2010年には1100店以上あったが、18年3月末時点で825店に減少した。
それとパラレルにFC加盟企業も17年3月の77社と、5年前から22社も減り、3、4年前からFC加盟店の募集も打ち切り、直営店比率は47%と高まる一方である。
ブックオフの古本ビジネスはジリ貧で、メルカリなどの競争相手が多く、市場環境も悪化し、仕入れの減少、在庫回転率の悪化、FC店舗の減少という三重苦に直面し、最終損益は9億円の赤字となったとされる。
ブックオフの成長を支えたのは、簡単な仕入れと販売の均一システム化とFC展開であり、それが両輪となって大量仕入れと販売が可能となっていた。しかしFC加盟店募集停止と脱退によって、さらにチェーン店は減っていくばかりであろう。ブックオフビジネス創業から30年近くが経過し、すでにビジネスモデルとしての寿命が尽き始めたといっていい
「相模原駅前店」の閉店の最後の数日は全商品が30円で販売されたというが、このゴールデンウィークには三洋堂がコミックと文庫を50円均一で売っていた。仕入れにしても、『日経MJ』が実例として挙げていたように、メルカリに大きく差をつけられてしまっている。
それに関連して想起されるのは、『出版状況クロニクルⅤ』で示しておいた、CCCの地域FCのビッグワングループのことで、同グループはTSUTAYA26店、ブックオフ11店を経営しているという。レンタルの不振と縮むブックオフの双方を抱えていることになり、それでいて17年12月には800坪のTSUTAYA大型複合店を開店させている。
これも日販がいうところの「出店を加速する方向」の一環なのであろうか。
7.青山ブックセンター六本木店が閉店。
いうまでもなく、ブックオフの傘下にあったわけだから、4のような事情と関連しているのだろう。
1980年のABC六本木店の開店は、中村文孝『リブロが本屋であったころ』(「出版人に聞く」4)でふれられているように、リブロの別働隊というか、サテライト店的発想で出店され、中村がマーケットリサーチを担当していた。
初代店長を務めたのは吉祥寺の弘栄堂にいた鈴木邦夫で、その後はジュンク堂に移ったようだ。
そうした意味で、ABCはそのバックヤードとともに、80年代には書店の黄金時代を体現していたといえるかもしれない。
しかしそのような時代は一時的なもの、遠い過去であったことを、今回のABC六本木店の閉店が伝えていよう。
8.『出版ニュース』(5/中・下)に「世界の出版統計」が掲載されている。
そのうちのアメリカ、イギリス、ドイツ、フランスを示す。
* アメリカ/アメリカ出版者協会1200社の16年売上高は143億ドルで、前年比6.6%減。
1800社の場合は260億ドル前後とされる。
15年出版総売上高は277億ドル、書店売上高は107億ドルで、同3.7%減。
電子書籍も成長は止まり、マイナスに転じている。
* イギリス/16年の出版社売上高は35億ポンドで、同5.9%増。
17年の書籍市場は15億9000万ポンドで、0.09%増。
電子書籍はやはり減少。
* ドイツ/16年書籍販売業者総売上高は92億7600万ユーロで、同1.0%増。
電子書籍伸び率鈍化。
* フランス/16年出版総売上高は28億3790万ユーロで、同4.25%増。
電子書籍は成長を続けている。
これは日本の出版物販売金額が半減してしまったことと対照的に、書籍を売る欧米の出版業界は売上高が近年ほとんど微増、微減にとどまり、日本のような出版危機に陥っていないことを確認するために、恒例として挙げているものだ。
それは今回も同様で、電子書籍は英語圏ではマイナスに転じ、ドイツ語圏では伸び率が止まり、フランスだけが成長していることになる。
9.日本ABC協会の2017年下半期「ABC雑誌販売部数表」が発表された。
報告誌は40社152誌、週刊誌34誌、月刊誌118誌である。
平均部数合計は1316万231部で、前年同期比6.4%減。
内訳は週刊誌が367万部で、同10.0%減、月刊誌は948万部で、4.9%減。
デジタル版報告誌94誌、総部数は12万9688部で、17年上半期同6.6%減。読み放題UU数は93誌で、971万555UUで、同245.6%増。
単純な比較はできないにしても、月刊誌平均部数合計よりも、読み放題UU数のほうが上回ってしまったのである。
それに対して、デジタル雑誌は『日経ビジネス』が3万6431部と群を抜いているものの、3.2%減、第2位の『日経TRENDY』は4737部、同17.9%減、第3位の『MAC Fan』は3430部で、同9.5%減である。
8でアメリカとイギリスの電子書籍が減少し始めていることを伝えたが、日本におけるデジタル雑誌も同様の過程を歩んでいるように思える。
それに対して、18年上半期においては、読み放題UU数は確実に1000万を超えるだろうし、すでに実際に超えていると見なすしかない。それがどこまで伸びていくのかが、雑誌の行方とともにあるということになる。
10.『週刊東洋経済』(5/19)が「フェイスブック解体」特集を組んでいる。
2004年に立ち上がったフェイスブックはSNSの代名詞となり、売上高は4兆4000億円、利益は1兆7000億円、世界の月間利用者は22億人に及んでいる。
その8700万人の個人情報データがアメリカ大統領選挙の世論工作に流用され、またイギリスのEU離脱を問うブレグジット国民投票にも使われていたことが、英国データ分析会社の幹部の告発によって明らかになったのである。
それはフェイスブックから得た情報によって、世論を扇動する方法が確立されていることを知らしめたといえる。
そのフェイスブックに加えて、グーグル、アマゾン、アップルのIT企業4社を「GAFA(ガーファ)」と呼ぶようで、フェイスブックの解体を主張するスコート・ギャロウェイのThe Four が今夏に東洋経済新報社から刊行予定となっている。これらの4社は市場独占、租税回避、プライバシー問題をめぐって、監視体制が必要だし、説明責任を果たすべきだとの内容のようで、翻訳が待たれる。
なおこの特集には横田増生「告発される過酷な労働 英議会がアマゾン批判」も掲載されている。
この特集でもうひとつの指摘は、これらのIT企業にとって「日本は草刈り場」になっているという事実で、CCC傘下のCCCマーケティングがフェイスブックに個人情報を提供してきたことも伝えている。
それは『選択』(5月号)の「経済情報カプセル」での、「フェイスブック問題の余波を食らう『TSUTAYA』の甘い情報管理」という記事と通底している。それによれば、CCCは16年からフェイスブックと提携し、子会社を通じて、Tポイントの6000万人を超える購買データを情報提供してきたとされる。
今回の事件を受け、フェイスブック側からの提携解消の申し入れがあり、先の「特集」でも触れられているが、ほとんどアナウンスされていない。
CCCによる顧客情報データの他社提供は、斎藤貴男が『プライバシー・クライシス』(文春新書、1998年)でいち早く指摘していたが、Tポイントに移行してからも続いていたことになる。
『選択』はCCCによる外部への情報提供は「ブラックボックスと化している」し、「知らず知らずのうちに、Tポイント利用情報をフェイスブックに横流しされ、危険にさらされた日本の消費者にとっても他人ごとではない」と警告している。それは日販も同様である。
この事実はツタヤ図書館利用者も同様なことを意味しているし、地方自治体が市民情報の外部への横流しに加担していることになろう。
「ブラックボックス」といえば、CCCはキタムラの全株式を取得し、上場廃止を発表している。
また『週刊エコノミスト』(5/22)も「ネットの新覇者」特集を組んでいることを付記しておく。
11.『週刊ダイヤモンド』(5/26)ば「物流クライシス」特集を組み、そのリードは「ヤマトのアマゾン切りで始まった物流の混乱は、収まる気配がない」というものである。
しかもこの特集の終章は「出版社、物流倒産の現実味」と題され、実際に同誌を例にして、ダイヤモンド社のことも語られ、「ビジネスモデルの激変に対応できない出版社は、座して死を待つのみ」と閉じられている。


確かに物流クライシスは個人も企業も巻きこむようなかたちで進行している。直販の場合、アマゾンのこともあり、送料をとれないことに加え、値上げ分を加えれば、どれだけの損失になるのか、またそれを含めた物流コスト問題を直視すべき時期に入っている。
個人に近い小出版社ですらそうなのだから、取次の「物流クライシス」はとんでもないものだろうと、あらためて実感してしまう。
なお『週刊東洋経済』(4/28、5/5)も「アマゾンの自社配送網 下請け頼みの過酷な現実」を発信している。
12.倉庫、書籍梱包会社の東京美装梱包が自己破産。
2006年には年商5億3000万円だったが、12年には4億円に落ちこみ、今年の1月に事業を停止。負債は5億円。
この出版物倉庫会社の自己破産も、出版危機と物流クライシスの双方の影響を受けたものであろう。
これも表に出てこないけれども、出版業界周辺の企業もクライシスが多発しているはずで、これからも続出してくるように思われる。
13.『FACTA』(6月号)が「『文春砲』が湿るか、文藝春秋で社長内紛劇」を掲載している。
それによれば、松井清人社長が、次期社長に経理出身の中部常務を起用し、子飼いの石井取締役を副社長として、自らは会長に就任し、院政を敷こうとしたことに起因している。
この動きに対し、次期社長と一時目されていた木俣常務など3人の役員が、編集経験のない中部社長では経営危機を乗り切れないと異議を唱え、人事撤回と退陣を迫ったとされる。
その背景には、前社長時代まで250億円前後で推移してきた売上高が、松井社長となってから、4年で40億円ほど減少し、4億円の赤字となったこと、そのために編集予算が削られ、不動産売却などで出版赤字を埋める経営状況がある。
それは5月30日の決算役員会と6月29日の株主総会で決着するが、日本のジャーナリズムの雄としての「文藝春秋」が鈍るような編集になり、「相次ぐスキャンダルに喘ぐ安倍官邸がほくそ笑むことにもなりかねない」内紛劇に、永田町も重大な関心を寄せているという。

本クロニクルにも、大手書店や出版社、取次に関する多くのリークが寄せられてくるが、不可避にして重要な事柄以外、ほとんど言及したことがない。『FACTA』の場合、文春にまつわる記事は関係者がリークしているか、書いているのであろう。
おそらくこの出版状況下にあって、大手を中心にして、このような経営と人事をめぐる問題が起きていることは想像に難くない。果たして文春の決着はどのようなものになるのだろうか。
その後『朝日新聞』(5/27)が、管理職11人による人事案再検討を求める要望書を提出したことを伝えている。
また”連判状″とともに、文春の内紛については、「YAHOO!ニュース」(5/21)でも、ジャーナリスト山口一臣によって報じられていることを、読者より知らされた。
14.同じく『FACTA』(6月号)が「『漫画村』閉鎖指揮は『首相補佐官』」という記事を発信している。
これはコミックの海賊版サイトの「ブロッキング」が憲法や電気通信事業法に明記された「通信の秘密」の侵害に当たり、「超法規措置」だとするもので、「危機感を抱いた出版社側が政府に泣きつき、今回の『緊急対策』となった」とされる。
それを言い出したのはカドカワ社長の川上量生で、「海賊版にはブロッキングが有効」と主張し、小学館、集英社、講談社が加わり、コミック系5社が内閣府の知的財産戦略本部に申し入れた。そして官邸の意向を忖度した役人によって、この「前代未聞の超法規的施策」が実現したのである。
これは「モリカケ問題と同質」で、「自助努力を行わず、旧態依然としたビジネスモデルにしがみつき、官邸に泣きつくだけの出版業界に明日はない」とまで断罪されている。
この記事が13と同じ号に掲載されているのは偶然ではないだろうし、出版業界も危機下にあって、至るところで、いわば鼎の軽重を問われるシーンが頻繁に起きていることを想起させる。
前回の本クロニクルでも、漫画村などへのサイトブロッキングは、「政府による検閲と事業者への圧力、議論なきサイトブロッキングの様相も帯びている」との疑念を表明しておいたが、図らずもそれが証明されたことになる。
『FACTA』の今月号の13、14の記事は、直販誌以外には書けないものだし、出版危機下における同誌の見識を讃えておこう。
15.山本芳明の『漱石の家計簿』(教育評論社)が出された。
これはサブタイトルに「お金で読み解く生活と作品」とあるように、夏目漱石の文学活動を経済的視点から捉え直し、さらに死後に生じた経済的効果と文化的資産としての動向を明らかにすることを目的として書かれた一冊である。
いうまでもなく、山本の『カネと文学』(新潮選書)の続編に当たる。


山本も書いているように、文学を経済活動として捉えることは重要だが、敬遠されがちなテーマとされるけれど、市場社会で活動せざるをえない文学者を考察すると、新たに見えてくる意義も大きい。
本クロニクルもそのような視座から出版の問題に取り組んできたといえる。たまたま最近、本ブログ「古本夜話」の785「河出書房『短篇集叢書』」と786「岸田国士『力としての文化』」を書き、そこで大東亜戦争下における河出書房と文学書の経済を論じている。それらを書くことで、昭和戦時下の出版と文学と経済の問題の一端にふれているはずなので、よろしければ参照されたい。
16.『出版状況クロニクルⅤ』は5月初旬に刊行されたが、当然のこととはいえ、取次によってはブロッキング化されたような扱いで、書店で見て、手にとる機会が少ないのではないかと推測される。
そのような刊行状況なので、図書館にリクエストして頂けると有難い。

今月の論創社HP「本を読む」㉘は岡崎英生『劇画狂時代』と「シリーズ《現代まんがの挑戦》」です。
本連載も多くの訪問者を得ているようで、論創社ともども多謝。