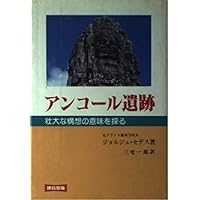続けて澁澤龍彥『高丘親王航海記』が戦前の南方論を背景とする高丘伝説を継承していることにふれたが、その南方論に関して、どうしても取り上げておかなければならない作品がある。それは昭和九年の東京を舞台としているけれど、物語の主要な人物とコード、そのコアとなるダイヤモンドは安南=ベトナムを起源とする『魔都』で、久生十蘭は本連載616などの長谷川一族、同889などの岩田豊雄の近傍にいたからだ。

この『魔都』は昭和十一年十月から一年間にわたって『新青年』に連載されたもので、なぜか戦前には単行本化されておらず、新潮社の『日本ミステリー事典』によれば、昭和二十三年に新太陽社からの刊行となっている。ここでのテキストは社会思想社現代教養文庫版である。こうした出版事情に関しての言及はないが、海野弘による『魔都』論が『久生十蘭―「魔都」「十字街」解読』(右文書院、平成二十年)として提出されている。彼はそこで、「『魔都』は奇蹟的ともいえる小説だ」と始め、「モダンなエンターテインメント、都市小説として読めるのではあるが、実は政治的陰謀小説なのではないだろうか」と述べ、この作品の謎解きに入っていく。それは同時代のモダン都市東京における丸の内と日比谷への注視であり、関東大震災後の銀座を含んでもいる。
『魔都』はそうしたトポスから書き出され、銀座のバーに移り、多くの登場人物たちが召喚されていく。海野はそれらの人々について、微に入り細を穿ち、同時代の実在の人物たちとのアナロジー化を進め、また同様にして事件をも当てはめていき、彼のいうところの「妄想と逸脱」を視座にすえ、「政治的陰謀小説」の構造を解明しようと試みている。それらは傾聴に値する「妄想と逸脱」ではあるけれど、ここではこの物語の主人公の一人とも見なしていい、日本名を宗方龍太郎とする安南王と、及び安南状況に焦点をしぼりたいので、これ以上踏みこまない。必要であれば、ぜひ海野の著作を参照してほしい。
安南王は仏領印度支那で五千二百万人の国民を統治する皇帝だが、日本贔の王様で、本国政府から強要されるフランス文化を忌み嫌い、日本から教師を招聘して日本文化に親しみ、夏冬二回の余暇に単身で来日し、文学博士も取得していた。ところが元宝塚の愛人を持つようになると、ほとんど隔月に日本に姿を現していた。「それは年のころ三十ばかりの白皙美髯の青年紳士」だが、「風格について言えば一族の韜晦的人物でわれわれが詩人とか哲学者とかいうものに近いよう」だとされる。その愛人の鶴子が何者かに殺されたことを発端とし、安南の社会状況も明らかにされていく。日本は国際連盟を脱退して以来、フランスとの関係が悪化しているにもかかわらず、皇帝が来日するのは、日本が安南の宗主権復興の尻押しをしているのではないかとフランス側は疑っていた。そして皇帝の愛人鶴子が殺されたことから、さらに事態は紛糾していく。
実は日本の新興コンツェルンの双璧である日興コンツェルンと林コンツェルンは、ともに国防産業をめざし、仏領印度支那の開発を手がけ、安南を舞台として鎬を削っていた。林のほうは宗皇帝を相談役に抱えこみ、日興は親仏派の皇甥李光明と結びついていたが、ボーキサイト採掘権は前者が先取りしたことで、日興が李光明擁立派と画策し、何事かをたくらんでいた。そこに皇帝の来日と失踪、愛人殺しが起きていたのである。
日興コンツェルンは山奥の電気会社から始まり、カーバイトや石炭窒素や硫安を製造し、朝鮮にも進出し、北鮮の事業主となり、新興コンツェルンの一画を占めた日窒コンツェルンである。林コンツェルンは房総の海藻からヨードを製造し、千曲川上流での発電事業にも参画し、マッチ鉱業やアルミニウム工業へと進出したコンツェルンのことだ。いずれも第一次世界大戦によって、化学肥料や化学工業品の輸入が止まったことで、大きく成長したのであり、それをきっかけにして新興コンツェルンの座を獲得したことになる。そしてこれもまた両コンツェルンもアルミニウム工場を有していたことから、その原料たるボーキサイトをめぐって争っていたのである。それを具体的に『魔都』から引いてみよう。
ともに国防産業を目指す二大コンツェルンは、その資源を仏領印度支那において開発すべく、昨年の冬ごろから安南を舞台にしてはなばなしく鎬を削ることになったが、小口(日窒コンツェルン)は見越しすぎて親仏派の皇甥李光明と結びついたため、いちはやく宗皇帝を相談役に抱え込んだ林(林コンツェルン)の日安鉱業に一歩立遅れ、採掘面六十万坪、年五万瓩の優良ボーキサイト(アルミニュームの原鉱)の採掘権を林に先取られてしまった。小口の日興がこれを黙って見ているはずがないと思っていたところ、最近はたして日興は裏面から李光明擁立派を突っついてしきりに何事かを画策しているといううわさが林の耳に伝わってきた。
『魔都』の背景には安南をめぐる、このような資源開発問題がすえられ、そこから皇帝の失踪、愛人殺し、安南秘宝のダイヤモンドの売却などが絡み、青山光二が『闘いの構図』(新潮文庫)で描いた鶴見騒擾事件へと結びついていくのである。その他にも二・二六事件や東京の地下大迷宮も浮かび上がり、まさに昭和十年代の『魔都』が、南方の安南から東京の大迷宮とリンクしているような仕掛けとなっている。それらを称して、海野が「一九三〇年代の東京に正面から挑んだ奇蹟的な都市小説の傑作」と呼んでいることを理解できるのである。

[関連リンク]
◆過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら