ピエール・ロティの『アンコール詣で』は佐藤輝夫訳で、昭和十六年に白水社から刊行されている。訳者の「はしがき」には、「これが訳されて、今日南方問題の喧しい折柄、少しでも曾てのクメール文化の一端を日本の読者に知って貰うことが出来たら」との主旨が述べられている。

この『アンコール詣で』は、ロティの一九〇一年十一月二十三日から十二月三日にかけての十一日間に及ぶアンコール・ワット旅行記と見なせよう。同書のパリのカルマン・レヴイ書房からの上梓は一二年なので、邦訳はそのほぼ三十年後であり、「今日南方問題の喧しい折柄」を見て、出版に至ったとも推測できる。「アンコール」もまた「南方問題」の定番のひとつになっていたとも考えられる。
そうした出版経緯はともかく、『アンコール詣で』はロティ特有の情熱的な官能に充ちたエキゾティスムと、滅びゆくものへの哀感において、本連載でずっと取り上げてきたアンコール学術書とは異なり、旅行記でありながらも、文学作品の領域に達している。それゆえに、このような官能的な、ロティのいうところの「巡礼物語」の翻訳が、大東亜戦争下で刊行されたことも奇異に思えるほどだ。
ロティにとっても、アンコールの廃墟を訪れることは少年の頃からの夢であり、植民地雑誌のアンコール寺院の絵に喚起された「シャムの森林の奥地で、わたしはアンコールの大遺跡の上に、夕べの星が登るのを見た」という言葉が、思い出の中にずっと刻み込まれていたのである。それから三十五年後、ついに実現の日を迎えることになった。
ロティはアンコール・ワットの寺院にたどり着き、その険しい階段を登っていく。美しい鑿の跡が螺旋装飾、葉形模様、唐草模様として至るところに遺され、それらはフランスのルネサンス時代の美術家が模倣したのではないかとの空想をもたらす。だがすでに三、四百年間、これらの壁はヨーロッパにその所在も気づかれず、森林の中に眠っていたのである。
眩惑と死の太陽に照らされながら、わたしはゆっくり登っていく。この苦しい登り路の上には、まあ、何と多くの怖ろしい象徴が嵌めこまれているであろう! どこを見ても怪物ばかり、怪物の闘争ばかり、到るところに神聖なるナーガが、欄干の上にその長い波型の体を横たえ、七頭の毒々しい首を扇型にもたげて立っている! アブサーラは女神として髪飾りの下で美しくかつ媽やかに微笑しているけれども、そこにはつねに隠喩的な、神秘の表情が湛えられていて、見る人の心持も落ち着かせない。……
このような描写はともかく、クメール族がインドを出自とするといったロティの歴史的記述に関して、ジョルジュ・セデスが『アンコール遺跡』の中で、ロティは「〈廃墟の神秘性〉のロマンチックな感じ」に降参してしまい、間違っているとの批判を述べている。それはロティのアンコール巡礼が一九〇一年であり、その時代のアンコール認識に基づいているからだ。一方で、セデスは一九二九年から四二年まで、ハノイのフランス極東学院長を務め、アンコール遺跡保存事務所を開設し、その研究と修復作業に携わっている。ちなみにこれは蛇足かもしれないが、セデスの専攻は碑文で、石に書かれた碑文解読を通じてのアンコールと王の実像研究である。またそれを発表した『フランス極東学院紀要』には、高楠順次郎や鈴木大拙も寄稿しているという。
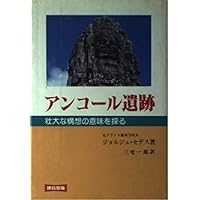
それゆえに、ロティの『アンコール詣で』がセデスたちの研究成果を取り入れていないのは当然だが、その他にも史料についての疑問も目につく。アンコールの内陣の聖なる場所に他を圧する七十メートルの高さの巨塔があるとの記述に続いて、次のような一文が置かれている。
十三世紀末つかた、この神秘的な王国をその衰微時代に訪れて、今日その栄華を知らせる唯一の記録を遺しているシナの一学者の語るところに拠れば、この中心塔の上には巨大な黄金の睡蓮が載せられていて、この聖花が空中に高く輝くさまが、今日埋もれているアンコール=トムの町のどこからも仰ぎ見られていたという。
この「シナの一学者」とは訳者の注にも見えているように、周達観であり、その「語るところ」とは『真臘風土記』
に他ならない。しかし三宅一郎、中村哲夫の『考証真臘風土記』に収録のそれに当たる「城郭」の章を見ても、「巨大な黄金の睡蓮」を載せた塔のことは出てこない。もちろんロティが読んだのは同書に「前言」や「序説」が収録クされているレミュザやペリオ訳によっているはずだが、それらの仏訳は未見なので、確かめることができない。

「睡蓮」と塔の関係を調べるために、阪本祐二の『蓮』(法政大学出版局)を読んでみたが、インダスやエジプト文明から始まる「ハスと文化」の関係は、「蓮台」や「蓮花柱頭」として仏塔にも表出していたことを教えられるし、付け焼刃の知識ではとても太刀打ちできない領域にあることを実感してしまう。

それにつけても思い出されるのは、松山俊太郎との一夜の温泉旅行が果たせなかったことで、本当に悔やまれる。そのことを連絡しようとしたら、行方不明となっていて、後に倒れて病院に担ぎこまれていたことを知らされたのである。このような質問を向けたら、きっと喜んでくれたであろうが。松山ばかりでなく、十代の頃から読んでいた著者たちはほとんどが鬼籍に入ってしまい、次には私たちの世代になっていることをこれまた実感してしまう。
[関連リンク]
◆過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら