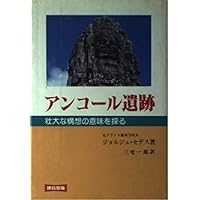本連載890のドラポルトの『アンコール踏査行』や同891のグロリエの『アンコオル遺蹟』に先駆けて、アンコールを訪れ、それを報告しているフランス人がいる。その人物はアンリ・ムオで、両書ばかりか、藤原貞朗の『オリエンタリストの憂鬱』でも挙げられている『タイ、カンボヂア、ラオス諸王国遍歴記』の著者でもある。同書もまた昭和十七年に大岩誠訳で、改造社から刊行されている。大岩は私などにとって、モンテスキューの『ペルシア人への手紙』(岩波文庫)などの訳者だと認識していたが、この時代には『南アジア民族政治論』(万里閣)を著わしているようなので、ムオの翻訳はそのことと関連しているのだろう。
 (『アンコール踏査行』)
(『アンコール踏査行』) (『オリエンタリストの憂鬱』)
(『オリエンタリストの憂鬱』) (『ペルシア人への手紙」)
(『ペルシア人への手紙」)
 (『タイ、カンボヂア、ラオス諸王国遍歴記』、まちごとパブリッシング"復刻版)
(『タイ、カンボヂア、ラオス諸王国遍歴記』、まちごとパブリッシング"復刻版)
その「訳序」は「フランスが印度支那半島に着目し、アジア制覇の基地として其の地に足場を築くまでに二百年余の歳月と幾多無名の犠牲者を数へてゐる」と始まっている。それに続く記述によれば、フランスが一八五八年に越南帝国領を侵掠するに至り、同年にフランスの科学者アンリ・ムオもメコン河流域諸地方の探査を目的とし、タイのバンコクに上陸した。それはロンドン科学協会の委託を受け、未知の国々の地理的社会的諸状態の調査を主としていた。
ムオは一八二六年にフランスのモンペリアールに生まれ、三十二歳でタイに着き、それからメコン河に入り、そこに住むアジア人の生活と性向を記録し、一八六一年三十五歳で亡くなっている。つまりムオの生涯はこの『タイ、カンボヂア、ラオス諸王国遍歴記』の中に凝縮されていることになる。大岩はこの「訳序」を昭和十七年十一月、「アンリ・ムオ八十年忌」の日付で記している。原書は「原序」に示されているように、パリで出された一八六八年版である。ムオはタイ、カンボジアを経てラオスに向かい、熱病にかかり、死亡し、その地に埋葬され、ドラポルトにより記念碑が建立された。その挿画を同書の末尾に見ることができる。
タイに関する記述と探検紀行も興味深いものだけれど、やはり最も異彩を放っているのはオンコール(以下アンコール)にまつわるものである。まさにムオの紹介によって、アンコールワットは世界に初めて喧伝されたことを考慮すれば、それに言及すべきだろう。ムオはかつてのクメール族の首都に関して、この印度支那に響きわたった「王国」の見事な遺跡は「欧州の壮麗な大寺院に比肩し得る」し、「その豪壮さに至つてはギリシャ、ローマの芸術を遥かに凌ぐものがある」と述べている。
その一方で、「かくも素晴らしい建築物を遺すほどの文化と天稟とをそなへた強国は、その後一体どうなつたのだらう」との疑問も発し、その没落原因は時の力、蛮人の侵入、シャム人の侵略、地震などが挙げられている。それに加え、この大寺院を建設したのは、「癩病の王」、もしくあは「天使の王」「巨人」だという伝説も挙げられ、その特徴の指摘もなされる。
しかし不思議なのは、この記念物のどれ一つとして居住の目的で建てられてゐないことである。そのすべては仏教思想の特徴を見せ、伽藍の中に見る像、薄肉彫のすべてが、文事或は宗教上の題材を取扱つてゐる。例へば頭にも身体にも腕環や頸環等の装身具をつけ、細い腰衣だけをつけた後宮にまもられた王の行列といふがごときものである。
そうしてムオはアンコールの中へと進んでいく。すると荘重な建物の巨大な輪郭に「一種族全体の墓を見出したやうに感じた!」のであり、それはアンコールへの挽歌のような記述へともつながっていく。
あゝ! 私にシャトオブリアン、ラマルチーヌにも匹敵する筆力、或はクロード・ロレンのやうな画才が恵まれてゐて、このおそらくは天下に比類を見ないと思はれる美しくもまた壮大な廃墟の姿がどのやうなものであるかを知人の芸術家たちに示すことが出来たなら。これらは今はすでに亡びた一民族の唯一の遺蹟なのであるが、その名さへ、この民族の名を高からしめた偉人、芸術家、政治家の名とともに、塵埃と廃墟の下に深く永久に埋もれてしまほうとしている。
そしてムオは廃墟の壁面に名工の鑿金によったに相違ない「癩王」を発見する。「まことに崇高く、均斉がとれ、顔面は美しく、感じは軟かくしかも傲然たる俤がある」裸像の挿画も添えられ、その「癩王」の名がブア・シヴィシチウォンだとされる。
しかし一九四三年にハノイで出されたジョルジュ・セデスの『アンコール遺跡』(三宅一郎訳、連合出版、平成五年)において、最後のアンコール大王ジャヤ・ヴァルマン七世が「癩王」にして、十三世紀のアンコールの建設者だったとされている。ムオ以降の研究に基づく同書にはその像も示され、また「癩王のテラス」を撮った写真も収録されている。
さてこれからは私の仮説である。昭和四十四年に三島由紀夫は戯曲『癩王のテラス』(中央公論社)を発表する。これは三島が四十年にカンボジアを旅し、アンコール・トムの荒涼たる廃墟で、若い癩王の彫像を見た時に想を得たとされている。三島の戯曲はジャヤ・ヴァルマン七世がバイヨン大寺院を建立するかたわらで、癩病にかかっていたという伝説に基づき、その肉体の崩壊とともに大伽藍が完成する対照から、「あたかも自分の全存在を芸術作品に移譲して滅びてゆく芸術家の人生の比喩」(「『癩王のテラス』について」、『三島由紀夫全集』35所収、新潮社)を描いたものだ。
 (『癩王のテラス』)
(『癩王のテラス』)  (『三島由紀夫全集』35)
(『三島由紀夫全集』35)
しかし三島はカンボジアを訪れる前に、いやおそらく戦前にムオの『タイ、カンボヂア、ラオス諸王国遍歴記』を読んでいて、そこにあった「癩王」伝説と、「癩王之像」の挿画のイメージをずっと抱えこんでいたのではないだろうか。それが『癩王のテラス』として結晶するのは、実際に現地を踏む機会を待たなければならなかったにしても。
[関連リンク]
◆過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら