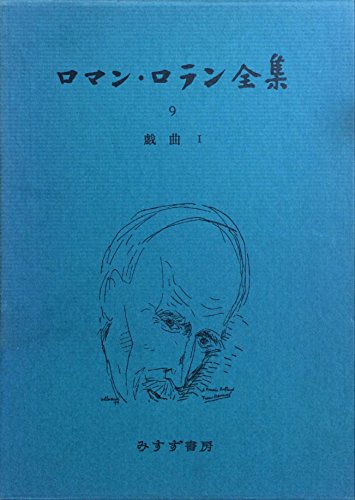もう一編、高田博厚の『分水嶺』(岩波書店、昭和五十年)を参照し、パリの片山敏彦とアランに関して続けてみる。

高田は大正九年に東京外語伊語科を中退し、コンディヴィ『ミケランジェロ伝』(岩波書店、同十一年)を翻訳する一方で、高村光太郎たちと交流し、貧しい暮しの中で、彫刻の仕事を続けていた。また片山敏彦や尾崎喜八たちと「ロラン友の会」をつくり、『近代出版史探索Ⅱ』204などの叢文閣からロランの『ベートーヱ゛ン』『ヘンデル』を翻訳刊行していた。そして昭和六年に作品の頒布会でフランスへの渡航費を捻出し、パリへと向かったのである。
 (『ミケランジェロ伝』)
(『ミケランジェロ伝』)
パリで高田を迎えたのは昭和四年に渡仏していた片山敏彦で、二年ぶりの再会だった。高田にしてみれば、日本での片山は所謂「世間知らず」で、「社会問題」はふれたくないタブーのようであったが、それから解放された感じで、「彼は変ったなあ……」と思われた。二人で「パリ見物」に出かけ、ノートルダム寺院、サント・チャペル、クリュニュー博物館などの美術巡礼の中で、とりわけサント・チャペルの「イール・ド・フランスの宝石」=魔彩鏡(カレイドスコープ)の中に入って、フランスの「洗礼(パテーム)」を受けたのである。それを見ることは片山を通じてのロマン・ロランからの伝言だった。
その「魔彩鏡(カレイドスコープ)」に加えて、高田にとってクリュニュー博物館の「貴女と一角獣」の絨毯(タペスリー)とオランジュリ館のモネの「睡蓮」がフランスの魂の「甘美」な思い出を生じさせた。またロダン美術館で見た「ロダン夫人」「思念」「ダナイド」などの実物は、それまでの「写真複製」では得られない「なんという優美(グラース)」を感じさせた。そして日本の現代彫刻はロダンに啓発され始まっているけれど、そこに至るは「なんという遠い道!」という嘆息をもらすしかなかったのである。
また高田は片山とスイスのロマン・ロランを訪ねる。日本で片山たちは「ロラン友の会」を結成することで、ロランとの長い文通を続けていた。ロランは高田の彫刻の写真を見て、彼に自分の像を作るようにと依頼した。続けて片山から「現代のデカルト」といわれるアランの存在を知らされる。そうした「パリ見物」としての美術巡礼やパリ人脈の紹介を済ませ、片山は日本へと帰国するのだが、いささか唐突に高田は「マルティネとアルクサンドルが私にアランの像を作らせる」と語り、実際に手がけることになる。この二人は前回引いておいたアラン『文学論』の片山の「訳者あとがき」にみられる 詩人と大学教授で、アランの仕事の協力者であった。
 (『文学論』)
(『文学論』)
このようにして、高田は片山、ロマン・ロラン、アランたちの織りなす一九三〇年代のパリのサロン人脈の中へと入りこんでいくのである。ここで留意すべきは高田特有の「美術巡礼」とその「洗礼」をイニシエーションとしたことで、それが他の「パリの日本人たち」と異なるものであった。
それらのことに加えて関心をそそるのは『近代出版史探索』125の「パリの日本人たち」の存在であり、多くが本探索シリーズとも関係している。高田のフランス渡航のきっかけは春秋社からロランの『ベートォヴェン研究』(これは間違いで『ベートーヱ゛ン』、昭和五年のことだと思われる)を翻訳刊行したことで、同188の春秋社『ゾラ全集』のために日本に戻っていた武林無想庵の話を聞いたからだった。しかもパリに着いた当日に中華料理屋に夕食にいくと、そこにいたのは『同Ⅳ』888、889の岩田豊雄=獅子文六であり、数日後に訪ねてきたのは、同190で挙げた無想庵の妻の武林英子だったのである。
そして高田は武林夫妻に先行する一九二〇年代からの「パリの日本人たち」の実相を見て、同74の石川三四郎、拙稿「椎名其二と「パリの日本料理店」」(『古本屋散策』所収)などの椎名にも言及している。彼らは社会主義といえば、クロポトキンのアナキズムの時代にフランスにきた「インテリ」たちだが、「大いなる水に浮いた浮草同様で、そこの土壌の中に自分の根を下せない」、「そこで自分を創りあげるためには、大いなる水の層はあまりに広く深く、そして重い」のである。「底の土壌」と「大いなる水の層」とは、高田が「洗礼」を受けたフランス芸術に象徴される文化土壌と人脈に他ならないだろう。それでいて、このちりのような「変な日本人」は帰国しても迎えてくれる「地位」もなく、「日本に帰りたくない」心境へと追いやられていく。そして高田にしても「私もその中の一人になってゆくのであった」と記す。
数百人に及ぶ日本人芸術家はパリの中で「日本人植民地」を作り、藤田嗣治式「自己顕示」を行使しているだけだから、問題としなくてもいいとして続けている。
「私たち」に問題になるのは、パリにいる日本知性人である。「知性」を試作し感覚し得るだけに、他の日本人以上に、西と東、ヨーロッパと日本との二つの「文化層」の谷間にあって、「自我」自身に深い矛盾を感じ、躊躇し迷い、絶望する壁にしばしばぶち当る 。「不安」を高い意味でも、低い意味でも体感する。ヴァレリーが言う「永遠のスファンクス」である「自我」を確かめ得るだけの「思念」の緻密性。この壁にぶち当る。
無想庵や椎名はその例であった。また、私がパリに着いた頃には、アナーキスト辻潤親子がパリで「浮浪」しており、南部外のクラマールに金子、森三千代夫妻、日本ではできそうもない奇妙な暮し方をしており、そのクラマールの森では佐伯祐三が二度木の枝に首をくくって失敗した。隣のシャティオンやフォントネ・オオ・ローズあたりには三木清やモスコーから来た中条百合子がいた。そしてマルキストの三木はフランスで精神の「彷徨」をしなかつたら、パスカルに眼を向かなかつたであらう……
このような高田の述懐と三十余年に及ぶ在仏、これらの他の多くの日本人たちの奇妙な生態とエピソードの言及を考えると、『近代出版史探索』125などの別の一九三〇年代後半の「パリの日本人たち」が、『同』121のスメラ学塾へと転回していったコアの理由がそこにあるように思われる。
なお片山敏彦編による高田の『フランスから』が昭和二十五年にみすず書房から刊行され、四十八年には朝日新聞社から新編が出版されたことを付記しておく。
 (『フランスから』、みすず書房)
(『フランスから』、みすず書房)
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら