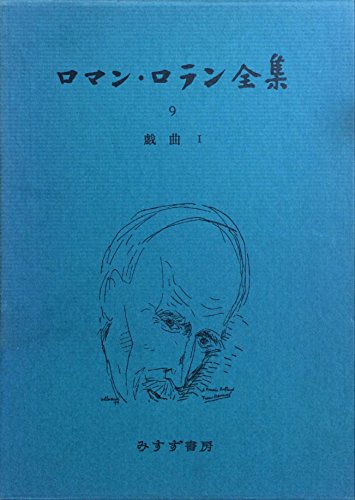前回、高杉一郎の「片山教室」体験にふれたが、私のような戦後世代にとって、片山敏彦のイメージは希薄で、翻訳はともかく、著書も一冊しか入手していない。
『日本近代文学大事典』における片山の立項は一ページ近いので、清水徹によるシンプルな『[現代日本]朝日人物事典』のほうを要約してみる。明治三十一年高知県生まれのドイツ、フランス文学者で、大正十三年に東京帝大独文科卒業後、ロマン・ロランとそのグループに深い関心を寄せ、昭和四年からフランスに留学し、スイスにロランを訪ねて親交を結び、ウィーンにツヴァイクを訪問した。帰国後の七年に一高教授となるが、二十年春には辞任し、軽井沢に隠遁し、文学と芸術を通じての魂の問題、さらには神秘主義的な姿勢から美や音楽を語り続けたとされる。

この片山の『詩心の風光』を処女出版物として始まったのが美篤書房、後のみすず書房で、創業者の小尾俊人は『本は生まれる。そして、それから』(幻戯書房、平成十五年)において、「片山先生の思い出」を書いている。そこで小尾は昭和十七年の二十歳の時に読んだ岩波文庫のロマン・ロラン『ベートーベンの生涯』の片山の解説の「一人の人間」と「土くれ」の部分を示し、次のように述べている。
この文章が私に与えた鮮烈な力、記憶に沁みこんだ印象はつよい。一人の人間とはベートーヴェンであり、人間と土くれのコントラストのイメージが、四畳半に射しこむ光と影とともに思いおこされる。これが私と片山先生との最初の出会いである。
それから小尾の軍隊生活と敗戦を経た四年後に片山の『詩心の風光』が刊行される。同書は『日本近代文学大事典』の片山の立項のところに書影としての扉の掲載もあり、小尾だけでなく、彼にとっても記念すべき戦後の最初の一冊だったことがうかがわれる。この四六判並製三九〇ページの用紙は粗末だが、内容はまさに「詩心の風光」に充ちているようで、その「序」は次のように始まっている。
戦争は過ぎた。歴史の深刻な動乱は昨日の悪夢のやうである。しかもその大きな余波はまだわれわれを揺すぶつてゐる。眼前には廃墟と新しい多くの墳墓と社会革命の相があり、内心には喪しみや驚愕や焦慮の痕が数多く残り、飢えて寒さの傷口おもまだ癒えてない。
帰つて来た平和の第一年目の春――空は碧瑠璃に澄み、丘には杏の白い花々が輝く。だが人は、自然のこの永遠回帰の余りにも明澄なふところに帰つて、聖書の中の「帰つた子」のやうに思はずむせび泣く。
最初の六行ほどの引用だが、このような片山ならではと思われる文章がさらに四ページにわたって続いていく。それは前回のツヴァイク『権力とたたかう良心』の昂揚した文学との共通性を感じさせる。それに続く第一部に当たる「讃頌と追憶――ロマン・ロランを中心として」は多くが戦前に書かれた八編を収め、その中の「ヴィラ・オルガの思ひ出」は一九二九年=昭和四年のスイスの村へのロマン・ロラン訪問記である。「ヴィラ・オルガの門まで行くとロマン・ロランが手を差し出し、微笑しなから近づいて来た。その手を握る。何も云へない。ただ、目の前にロランの碧い目を光を感じてゐる」。この五〇ページ近い訪問記を読むと、本探索1252の徳富蘆花の『順礼紀行』における、明治末のトルストイ訪問を重ね合わせてしまう。あえていってみれば、片山にとってロマン・ロランは昭和におけるトルストイのようにも思われる。

 (警醒社『順礼紀行』)
(警醒社『順礼紀行』)
そのイメージは戦後を迎えても保たれ、片山と小尾によって『ロマン・ロラン全集』が企てられていくのである。そのような戦後の翻訳状況もあって、もちろんみすず書房の全集ではないけれど、図書館でいくつかの『世界文学全集』によって、私も中学時代に『ジャン・クリストフ』や『魅せられたる魂』などの大作を読んでいる。今となっては私と同じく、信じられないかもしれないが、そのような時代もあったのだ。
小尾も先述の一文でいっていたではないか。「著者があり、訳者があり、図書館がある。それらをむすび支える無数の綱、ネットワークがある。その質と拡がりが、文明の内容をなしている。その環の一つで、私は、あったのだ」と。そのような出版インフラに支えられ、『ツヴァイク全集』全二十八巻も『片山敏彦著作集』全十巻も刊行されていたのである。
 (『片山敏彦著作集』)
(『片山敏彦著作集』)
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら