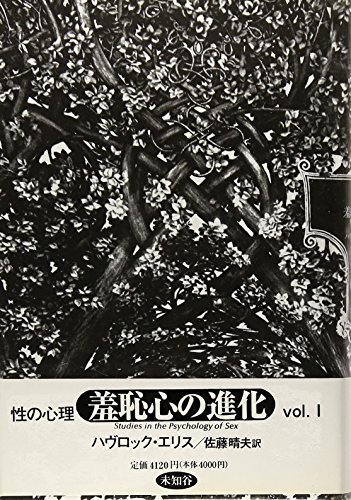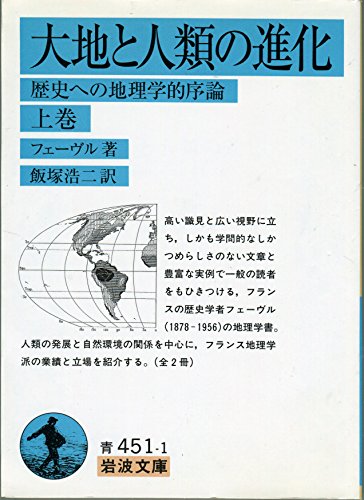エリゼ・ルクリユ『地人論』の訳者の序には当時の石川三四郎の人脈が記され、この翻訳をめぐって吉江喬松、山下悦夫、芹澤幸治郎(ママ)、古川時雄の好意と助力を得たとされる。吉江は『近代出版史探索』189などで既述しておいたように、フランス文学者で、前回のルクリユの立項のある『世界文芸大辞典』の企画編集者、芹澤は拙稿「椎名其二と『パリの日本料理店』」(『古本屋散策』所収)というパリにおけるモデル小説を書いているので、石川ともパリ時代に知り合っていたのだろう。古川は本探索1321でふれておいたが、望月百合子の同志にして夫で、ともに仏英塾や共学社古書部フランス書房を営んでいた。山下悦夫は不明だけれど、春秋社の編集者ではないだろうか。


この時代に石川の近傍にいた人物として、『ディナミック』に寄稿している、これも『近代出版史探索Ⅵ』1050などの生田春月、及び中西悟堂も挙げられるが、彼らは『地人論』の翻訳出版に直接かかわっていなかったので、ここでは挙げられていないと推察される。しかしその代わりに、ルクリユの死後に関係の深い石本恵吉の存在が語られている。
私はブルッセル新大学内に於けるルクリユの遺物たる地理学院図書館の図書全部六万巻を日本に持つて来た。石本恵吉氏の志望と出費とによって、この貴重な記念物を日本に移すことになり、五十余屯の大きな荷物は深川の倉庫まで運ばれたのであるが、不幸にして、それはかの大震災に際して烏有に帰して了つた。
ここで関東大震災において、エリゼ・ルクリユの地理学六万冊が「烏有に帰して了つた」ことを知るのである。かつて私も「地震と図書館」(『図書館逍遥』所収)書き、内田魯庵がいうところの「典籍の廃墟」「永遠に償はれない文化的大損失」(『内田魯庵全集』第八巻所収、ゆまに書房)に言及している。関東大震災は多くの図書館を炎上させ、膨大な貴重文献を消失させてしまったのであり、とりわけ東京帝大図書館はその「典籍の廃墟」を象徴するものだった。
主なものを挙げれば、『近代出版史探索Ⅲ』514などの言語、宗教、神話学のマックス・ミュラー文庫、法律、政治、経済学のデルンブルヒ文庫、エンゲル文庫、ヨセフ・コーラー文庫、ギリシア歴史、ラテン古文学のオードリー遺書、満州朝鮮地理書の白山墨水文庫などの八万冊に加えて、世界に一冊しかない満文、蒙文、西蔵文『一切蔵経』、幕府の『評定所記録』『寺社奉行記録』、足利時代から江戸時代にかけての切支丹文献などで、魯庵は「世界の大文庫の全滅」とまでいっている。おそらくルクリユの遺物の蔵書も帝大図書館に収まるはずだったので、いずれにしても関東大震災による被害は免れなかったであろう。
それでは蔵書を買い上げ、日本へと運ばせた石本恵吉とはどのような人物なのか。幸いにして『日本アナキズム運動人名事典』に立項を見出せるので、それを引いてみる。
石本恵吉 いしもと・けいきち 1887(明20)12-1951(昭26)東京市小石川区高田町(現・文京区関口)に生れる。父新六は男爵、陸軍中将。一高を経て東京大学工学部採鉱冶金学科に入学。一高時代の同級に岩波茂雄がいる。14年卒業、三井鉱山に入社。同年広田静枝(のち加藤シヅエ)と結婚し、三池炭鉱へ赴任。18年病気になり帰京。外遊して労働問題、思想問題に見聞を広める。21年頃三井鉱山を退社、洋書輸入の大同洋行を創業する。超一流の書籍のみ取り扱うという営業方針で、石川三四郎を介しブリュッセル新自由大学にあるエルゼ・ルクリュの蔵書6万巻を1万円で輸入する。また狩野亨吉所蔵の『自然真営道』などを7000円前後で購入し東大図書館に納める。商売というより不遇な学者を援助する文化事業のつもりだったらしい。だがこれらの書籍は関東大震災で烏有に帰し、大同洋行もその後まもなく解散したようだ。30年頃新天地を求めて満州に渡る。36年静枝と離婚。長男新は論理学者。
この立項が石川三四郎の『自叙伝』(理論社)によっていることは明白であり、それを反復するよりも、静枝夫人は後に加藤勘十と再婚し、加藤シヅエとして『ある女性政治家の半生』(PHP研究所、昭和五十六年復刻、日本図書センター)を著しているので、そちらのほうを確認してみる。
静枝の父は東京帝大出の工学士で、英米との貿易に携わり、母は麻布の東洋英和を卒業し、弟は鶴見祐輔であった。彼女は大正三年に女子学習院を終え、石本と結婚する。彼は軍人の家系にもかかわらず、人道主義的な考えの持ち主で、鶴見と同じ新渡戸稲造の門下生の一人でもあり、内村鑑三や山室軍平の感化も受けていたので、彼女はその縁談を承諾したのである。そして石本は三井鉱山の技師として三池炭鉱に赴任し、静枝は夫ともども炭鉱の労働問題と貧乏人の子だくさんの見本のような生活を目の当たりにして三年間を過ごした。だが石本は健康を害し、帰京して療養することになる。
彼女の証言によれば、石本は健康を回復すると、大正デモクラシーの盛り上がる中にあって革命思想に傾き、二人でアメリカに行くことを提案し、それを実行し、自らはマーガレット・サンガーに出会い、生涯の師として仰ぐことになる。しかしその一方で、石本の事業は様々な連帯保証なども含め、失敗続きで、財産の散財といった状況となり、静枝も精神的に消耗し始める。それに続いて、石本は国策に乗じるようになり、国士気取りの友人たちとの交流も盛んとなり、「満州に理想郷を作りに行く」といい、大陸へと向かってしまう。そこで彼女は離婚を決意するに至るのである。
これらの彼女の記述から、ダイレクトな証言はないけれど、洋書輸入や超一流の書籍のみを扱う大同洋行の事業が失敗に終わったことを了解するのである。
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら