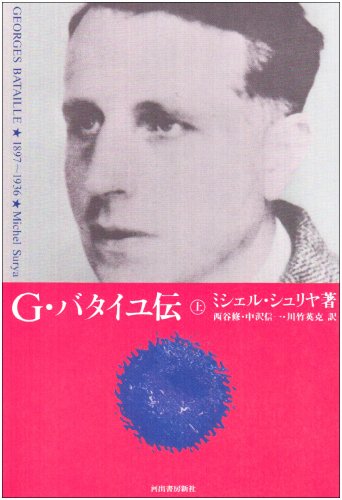ここで日本へと戻る。本探索1253の日本評論社『日本プロレタリア傑作選集』に前田河広一郎の『セムガ』があったことを覚えているだろうか。

この『セムガ』は入手していないけれど、「セムガ」はタイトル作の他に「長江進出軍」「太陽の黒点」を収録した作品集の『文芸戦線作家集(二)』(『日本プロレタリア文学集』11)や三一書房の『日本プロレタリア文学大系』4で読むことができる。それらは日本評論社版と異なり、「セムガ(鮭)」と表記されているので、タイトルだけでは意味不明の「セムガ」が「鮭」のことだとわかる。


もはや前田河と同じく、「セムガ」も 読まれていないと思われるし、こうした機会を得たこともあり、この中編を読み直してみたい。それは露領カムチャツカを舞台とし、日本から船ではこばれてきた百七十人が極北の寂寞とした土地へと上陸し、その丘の小舎にたどりついたところから始まっている。彼らのうちの七人が幹部で、一人が「船頭」、他の六人は「小頭」で、一人が「副船頭」、五人は「人夫廻し」と呼ばれ、漁場を支配する側に立っていた。残りの百六十三人は大急ぎでかき集められた「大都会の失業者や、寒い日蔭の県の貧農」で、「絶対窮乏の背景から抽出(ひきだ)されて、北へ、沖へ、カムチャツカへと、自分の労働力を捨売り」する状況にあった。
まず彼らは船から食料などの貨物を運ぶ荷役が終ると、「船頭」たちの幹部小屋、倉庫、飯場、番屋、機関小屋、罐詰工場などの小舎掛けに忙殺された。しかもオーロラゆえに夜も定かでないことから、労働時間は午前二時から午後十一時頃まで続くのだった。幹部部屋は丸太と蓆(むしろ)からなる他の小舎と異なり、近代的装置としてのガラス窓、ピストルやモーゼル銃、生活必需品も備わり、「この行政執行機関の本部は浜一般を三角形に見た絶頂点に在つて、飯場(中略)などの造営物へ、おのおの最近距離によつて達する通路を持ち、窓からはガラスと云ふ物の特質から、一目でベーリング海の沖積様が展望された」のである。まさにカムチャツカの漁場においても、ミシェル・フーコーが『監獄の誕生』(田村俶訳、新潮社)でいっているパノプティコン方式が採用されていたことになる。そうした漁場の資本と労働の対立が意識されていく中で、ひとつの事件が起きていく。

それは朝鮮人の伊がロシア人漁場から逃れてきたといって、番屋に助けを求めにきたことから始まる。「船頭」たちは彼が「赤化宣伝」のために日本人に化け、やってきたのではないかと疑う中で、番屋の寝床に「撒(まき)ビラ」が発見される。そのビラは「日本人労働者諸君! 諸君労働者ハ、誰ノ為メコノ露領かむちゃつかへ来て労働スルノカ?」と始まるもので、各人の布団や枕の下に挿入され、百八十五枚に及んでいた。これらは伏字だらけで、全文は読めないけれど、明らかにロシアの労働条件の正当例に対して、日本の惨状を訴えるものだった。
伊は姿を消していたが、その事件以後、「船頭」たちは警戒態勢に入る一方で、ロシアの国家保安部の仕官と税関吏の訪問を受ける。そしてウォツカ流用の「外交」が始まり、日本側のビラへの抗議に対して、その朝鮮人は日本国民だし、ソヴィエト・ロシアは何の責任もない。それよりもこれを本国の会社に送り、「労働者の待遇改善」を図るべきだと応じるのだった。しかしすでに「赤色労働組合(プロフインターン)」が結成されようとしていたのである。
それから「船頭」たちによるカムチャツカの漁業の「前哨兵」たる労働者への酒とぼた餅の祝宴の一夜が明けると、戦争のような鮭と鱒漁業、罐詰工場での作業、労働者たちの病いの発生と脱落、それに幹部たちの血みどろの暴力が描かれ、ついに労働者たちは立ち上がり、労働条件の改善などを突きつけ、ストライキへと突入するのだ。だがこの蜂起とクロージングに至る章もまた伏字処理が施され、検閲の時代をあからさまに浮かび上がらせていよう。
この「セムガ」は『プロレタリア文学資料集・年表』(『日本プロレアリア文学集』別巻)によれば、『改造』の昭和四年十一月号に発表されているので、同年の『戦旗』五、六月号に掲載された小林多喜二『蟹工船』とのコレスポンダンスを推測できるし、そのように読まれたと考えていいだろう。それに実はこの作品とタイトルに関して、本探索1286の田口運蔵が絡んでいたのであり、荻野正博『弔詩なき終焉』において、その事実を知ることになった。荻野は書いている。

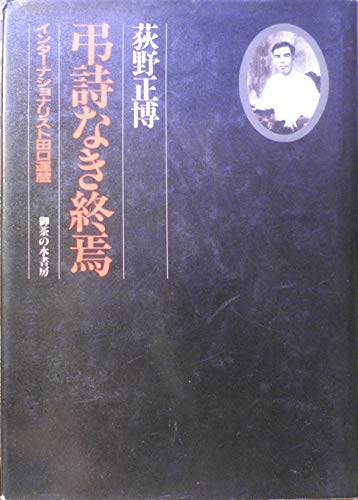
運蔵は三月十三日付「読売新聞」に「『セムガ』謝罪」と題する小文を寄せている。前田河広一郎『セムガ(鮭)』(『改造』一九二九年十一月号)は、運蔵が前年秋に上京、前田河宅に寄留していた際、創作されたものであったが、前田河はその作品中に用いるロシア語について運蔵に質問した。運蔵は「ロシア語の知識が非常に不足なので、さっそく友人Kを訪れ、色々と教えられて帰り」、それを前田河に告げた(友人Kとはソ連滞在の長い近藤栄蔵であろう)。ところが、この作が発表されると、「セムガ」なるロシア語はない、鮭なら「セヨムガ」であり、複数なら「セムギ」であるとの批判が貴司山治より、「読売新聞」紙上でなされた。(中略)運蔵は次のように釈明している。私は生来東北弁で、外国語はもちろん、日本語においてさえも難しい発音をよく間違える。前田河に伝えるとき、「ショムガ」と発音すべきを「セムガ」とやったのである。ちょっとした日本語の発音の不純がかくも重大な結果となった。「鮭」の作者と読者諸君にお詫びすると。(後略)
それではどうして単行本にあたって、訂正されなかったのだろうか。『日本プロレタリア傑作選集』版の刊行は本探索1255で既述しておいたように、昭和五年一月であり、貴司の指摘は『改造』掲載ではなく、この単行本化を通じてのものだったとわかる。そのために訂正の機会を逸し、「セムガ」でそのまま用いられてきたことになろう。
[関連リンク]
過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら