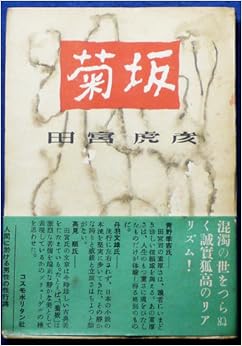田宮虎彦に関して、もう一編続けてみる。田宮といえば、昭和三十二年にベストセラーとなった『愛のかたみ』に言及しないわけにはいかないだろう。それにたまたまこの本も入手しており、奥付を見ると、四月一日初版、五月十五日二十四版とすばらしい売れ行きを示している。装丁は文明社の「文芸叢書」と同様に花森安治で、これは年譜を見ていて気づいたのだが、田宮の『足摺岬』や『異端の子』は昭和二十七、八年に花森の暮しの手帖社から刊行されている。
だが同二十九年の『千恵子の生き方』の出版をきっかけに、光文社との関係が深まったようで、三十一年からは『田宮虎彦作品集』全六巻の刊行が始まっている。そのほぼ同時期に千代夫人が胃癌のために死去し、田宮による妻の思い出、及び二人が結婚した昭和十三年から死の三十一年に交わした手紙を収録した『愛のかたみ』が送り出されたのである。
光文社の出版資料『マスコミの眼がとらえたカッパの本』は昭和三十年代前半の自社の出版状況を次のように記している。
光文社の伝統である『少年期』や『愛は死をこえて』につづく「愛情の記録」の流れとして、32年には田宮虎彦・千代、『愛のかたみ』が大ベストセラーとなり、33年には十歳の少女・安本末子が、日本中の家庭に『愛の灯』をともした。
最後の部分を補足しておけば、これは『にあんちゃん』のことをさしている。

それはともかく、おそらく『愛のかたみ』の往復書簡を含めた「愛情の記録」の流れは、昭和三十八年刊行の河野実・大島みち子の『愛と死をみつめて』(大和書房)にまで引き継がれ、藤井淑禎のいう昭和三十年代における「純愛の精神誌」(『純愛の精神誌』、新潮社)の形成に至るのであろう。
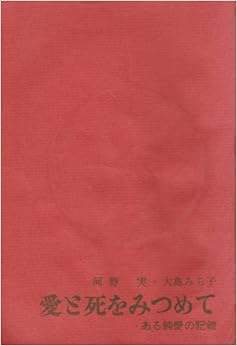
しかし田宮の「愛情の記録」に対して、批判を放った文芸評論家がいた。それは平野謙で、『群像』十月号掲載の「誰かが云わなければならぬ―『愛のかたみ』批判」は、「田宮虎彦」(『平野謙全集』第九巻所収、新潮社)として残されている。平野が手にしたのは「七月十七日五十四版発行」の一冊で、彼は読了して日が経つにつれ、「こういう特殊な、不自然な、変態的な書物が、なにか普遍的な、正常な、純愛ぶりの美談として、世に受けいれられているらしい事実に、黙っていられない気がしてきたのである」。ここでの「書物」は「結婚生活」と言い換えられる。平野は二人の往復書簡に使われている夫婦の呼び方からして、その十八年間の結婚生活に時間の経過もなく、子供たちも入りこめないようなもので、それが田宮の「絵本」や「菊坂」といった文学作品に基づき、二人が設計した結婚生活、もしくは田宮の文学に潜む「弱気をよそおって女をくどきおとした男の口説」によって、夫人が田宮の言にあるように、「自分の野心のすべてを私にのみそそぎこんだ」、「けなげな姉さん女房」を演じ続けていたのではないかと指摘している。夫の文学によって造型された妻は確かに「特殊な、不自然な、変態的な」存在であり、「普遍的な、正常な、純愛ぶりの美談」として語られるべきではないのである。
平野も引用しているが、田宮は『愛のかたみ』の中で、繰り返し書いている。
私が「絵本」を書き「菊坂」を書いた時、千代は私のそばで夜二時三時までもいっしょに起きていてくれた。私が「絵本」や「菊坂」を書いたのではなく、私と千代が「絵本」や「菊坂」を書いたといってよかったと思う。私が書きなやんでいる時、千代は私といっしょに苦しんでいた。私が作品を書き上げた時、千代はその喜びを私と共にした。
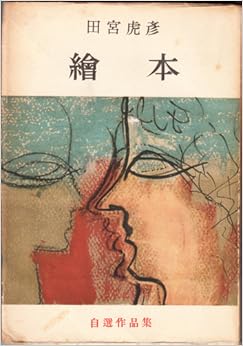
このようにして小説を書く作家を田宮以外に知らない。芥川賞候補となり、毎日出版文化賞を受賞した「絵本」や「菊坂」の内容に関して、平野は紹介していないが、ここではこの二編にもふれてみよう。いずれも昭和二十五年に発表された作品で、主人公の「私」は同一人物と見なしていい。いずれも昭和十年前後の東京を舞台とし、主人公は大学生で、下宿しながらアルバイト生活を送り、その下宿で起きた事柄が描かれている。田宮の大学時代の体験に基づく暗い青春がテーマである。「絵本」や「菊坂」も暗い青春の投影であるような下宿人たちの悲劇が語られ、物語の経糸となっているのだが、ここで問題にすべきは主人公の「私」の設定であろう。
「絵本」の「私」は父と不仲で学資を得られず、母が父に隠し、手紙にしのばせて送ってくる五円を生活の足しにしていたが、「菊坂」ではその母が死に、「私」はされに苦境に追いこまれ、彼女がいつも手紙に書いてきた言葉から、母を回想する。
私は、母の、早く大学を出ておくれ―という言葉に、幼い頃父にかくれてあまえたかった母の柔かい白い乳房を感じていた。母の手紙は、私の名前をよびかけ、よしよしと背中をさすってくれているやさしさのように思われるのだった。
そして何よりも重要なのはこのふたつの短編において、主人公の「私」は常に「―さん」であり、母も「―や」と呼んでいる。つまりこれは「虎彦さん」や「虎彦や」としか考えられず、他の名前に転化できないので、ダーシュ処理としているのだろう。しかも田宮がいうように、「私と千代とが『絵本』や『菊坂』を書いた」とすれば、この二人の文学的倒錯の実像が浮かび上がってくることになる。田宮は巧妙に千代を妻=母なる偶像へと仕立て上げ、田宮文学の支えとしたのであろう。だから妻の死後、田宮文学の集大成として、フィクション=ノンフィクションともいうべき、『愛のかたみ』を刊行したのではないだろうか。
| [関連リンク] | ||
| ◆過去の[古本夜話]の記事一覧はこちら |